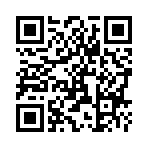スポンサーサイト
SUUNTO VECTORマイナーチェンジ考察

コロナの影響で飲み会や出張がめっきり無くなり、家にいる時間が増えたのですが、Call of Duty MWはちょっと飽きてきたので今違うゲームをせっせとやっています。
World of Tanks(以下WoT)というゲームです。

オンラインで15対15で、主に2次大戦周辺頃の戦車で戦うゲームです。



高校生の頃、PSソフトのパンツァーフロントが大好きだったので、当然このゲームもドハマりしました。

当時「パンツァーフロントでプレイヤー対戦できたら最高だろうなあ」と夢見ていたので、まさに夢が形になったようなゲームです。
ファミコン現役時代から、多感な時期に激動の進化をリアルタイムで味わえている世代なので、ゲーム史的には本当にいい時代に生まれてきたと思います。
元々はPCゲームで2011年4月にサービス開始、PS4版は2016年1月にリリースされ、今も現役の息の長いゲームです。
私はPS4版リリース直後にデビューし、今もやっています。
がっつりハマる時期もあれば、数か月ログインすらしない時期もありますが、この1ヵ月くらいはがっつり期間真っ最中です。
WN8でようやくユニカムが見えてきたので、とりあえずユニカム目指して頑張ろうと思います。

「WN8」というのはWoTにいくつか存在する「プレイヤーの技量指標」みたいなものの一つで、プレイヤーの個人戦績から自動的に算出されます。

ドラゴンボールで言う所の「戦闘力」みたいな感じです。
「ユニカム」というのはこのWN8が2450~2899のレンジのプレイヤーの称号で、人口分布としては上位0.1%に入ります。
ラテン語で「唯一無二」みたいな意味らしいです。
既に熟成されつくしておりゲームシステムの完成度は非常に高く、どのFPSともロボ対戦ゲーとも異なる独特の操作感、戦術が病みつきになります。
グラフィックや挙動、音、超マニアックな車種等、戦車への愛が滲み出ているので、戦車好きなら間違いなくやって損は無いと思います。
近年、戦車にまとわりつくようになってきた「女子高生イメージ」ですが、このゲームにはそんな「萌え」的な要素は皆無です。
乗組員は劇画調のおっさんばかりです。

少し課金すると声やビジュアルをカスタマイズできますが、劇画のおっさんを別の劇画のおっさんに変えられるだけです(笑)
ポリコレに配慮してか、いつからか女性乗組員の選択もできるようになりましたが、もれなく劇画で「萌え」の欠片すらない安心設計です。

私としては戦争モチーフのゲームは、こういう硬派な方が大好物です。
同じシステムでも、ガールズ&パンツァーみたいな雰囲気だったら絶対プレイしてないと思います。
PS4版リリース直後にガールズ&パンツァーのⅣ号戦車が配布されましたが、乗っていたのはちゃんと劇画な独軍おっさんで安心しました(笑)

基本無料なのも素晴らしいです(私は4年間で3000円も課金してないと思います)。
今まで7500戦やっていますので、インターバルやロード時間含め1戦7分と見積もると、900時間近く遊んでいることになります。
3000円を900時間で割ると、1時間あたり3.3円で遊べているという駄菓子屋も真っ青のコスパですね。
ちなみにこのゲームの総ダウンロード数は、PC版を含めると軽く1億は超えているみたいなので、一人当たりが超微課金でも塵も積もればでしっかり利益を生んで、質の良いサービスを維持できているのでしょう。
無料で気軽に始められますが、ガチでやり込むなら攻略wiki等を熟読して、各種戦術要素や各車種の諸元(装甲配置や機動力、主砲の弾種、貫通力や威力、弾薬庫やエンジンルームの位置等)を頭に叩き込んで戦場で立ち回る必要があり、奥はどこまでも深いゲームです。
今まで私がプレイした対戦型オンラインシューティングゲームの中では、間違いなく一番の完成度だと思います。
つい戦車話が長くなりましたが、そろそろ本題に入ります。
最近無性にウォッチ熱が上がっているので、また腕時計の事を書きます。
今回は珍しくCASIOではない時計の話です。
ミリタリーファンにはおなじみのSUUNTO VECTORについてです。

たまには装備でG-SHOCK(CASIO)以外の腕時計も選択肢に入れたいと思い、候補を探していたところ、VECTORの存在を思い出しました。
初期アフの頃から登場しています。


2000年代中盤以降も使用例はかなりあると思います。
ナショジオドキュメンタリーの「INSIDE THE GREENBERETS」でも着用していると思われる隊員がいます。

各種オークションサイトで見てみると、程度によりますがお手頃な価格で出回っています。
ただこれも息が長い製品にありがちな、年代によるマイナーチェンジがいくつもありそうです。
調達するにしても「数年前に生産終了した」くらいの知識しかなく、どれを選べばオーパーツにならないか分からなかったので、この機会に色々調べてみました。
大変ありがたい事に、「特殊部隊という響き」で既にVECTORの年代について考察記事を書かれておりますので、まず基礎をここで勉強させていただいた上で、私なりに肉付けしてみました。
軽くネットを調べてみると、発売年は1998年、ないし1999年という情報がいくつか出てきました。
生産終了は2015年のようで、2016年に「FINAL EDITION」という限定モデルが発売されたようです。

とりあえず最終形はこれで間違いなさそうですね。
ご丁寧に「FINAL EDITION」って入ってますし。

約15年の超ロングセラーモデルだったという事ですね。
少し調べてみたら当然マイナーチェンジしていました。
変遷を順を追って書いていこうと思います。
但し、今回ベゼル部の形状仕様のみに注目して変遷をまとめてあります。
ベゼル以外の仕様変更やソフトの変更、各年代のカラバリ展開は一切考察していませんのでご注意ください。
特にカラーはかなりの数が出ては消えているようなので、形状だけでなく「この年代には存在しない色」というオーパーツ判定が出てきそうです。
カラー展開については今後気が向いたら考察を進めようと思います。
まずは初期モデルを見極めるべく、いつもの「BACKPACKER誌しらみつぶし作戦」を実行したところ、1999年2月号に初めて広告が登場しました。


これが私が確認できた最古と思われる情報です。
おそらく本国フィンランドはじめ特定の地域では1998年の秋頃発売し、その他の地域ではタイムラグがあって1999年初頭頃に発売になったのではと想像しています。
まあいずれにせよ、9.11時点では確実に存在していた事になりますね。
ただBACKPACKER誌はわかりませんが、通常日本の雑誌は実際の発売月と「〇月号」の差が2ヵ月くらいあるので、1998年12月に発刊されていた可能性もありますね。
そうなるとアメリカでもVECTORは1998年には売っていた可能性が高そうです。
次に、同じ1999年の2月にオーストリアのどこかの旅行会社?のチラシにVECTORが載っていました。


ネットって本当に何でもありますね。
こんなモノまで拾えるとは思ってもみませんでした(笑)
では、ベゼルの特徴を見ていきましょう。
BACKPACKER誌

全体的にツルっとしていて、NとSの部分は湾曲し、外周に小さな突起がいくつも有ります。
印刷は「NEWS」と、NSの外側、WEの内側に線が引いてあります。
オーストリアのチラシ

一見同じですが、よく見るとベゼルの内周側に目盛りが振ってあります。
WEの内側の線は有りません。
同じ時期の画像のはずなのにいきなり仕様が違います...。
仮にBACKPACKER誌発刊が1998年12月だとして、チラシが1999年2月だとしても2ヵ月しか違いが無いです。
そんな短いスパンでマイナーチェンジが入るとは考えづらいです。
他にも1999年当時のVECTORの画像を漁りましたが、個人が撮影したような写真でBACKPACKER誌と同じ目盛り無しはありませんでした。


他の広告画像では、BACKPACKER誌以外でも目盛り無し仕様は確認できました。

このことから、おそらく広告用の画像を撮影したサンプルはまだ最終仕様ではなかったのではと想像しました。
広告用サンプルが完成した後に急遽目盛り印刷有りの仕様に変わったが、広告は差替える時間が無くそのまま掲載された、という感じです。
私は某メーカーに勤めていますが、結構こういうことはあります。
幻の「目盛り無し」仕様が市場に存在する可能性は無きにしもあらずですが、現時点では「ツルツルベゼル+NEWS+目盛り」が最初期モデルだと判断します。
次にネットを時系列順に探っていると、2001年秋にベゼル形状が異なる写真が出てきました。


先代に比べ非常に凸凹しているので一発で見分けが付きますね。
2020/12/4追記
某ネットオークションで2001年8月に購入したと思われる個体を発見しました。



出品情報からもおそらくこの個体に付属していた説明書である事は間違いなさそうなので、2001年8月時点でこの凸凹ベゼル仕様は世に出ていた可能性が濃厚だと考えます。
次に、2004年秋には再び初代同様のツルっとした形状に戻っています。

初代との見分け方は、NEWSが消え代わりに数字印刷が入ったところで、これも非常に分かりやすいですね。
以降、2014年の生産終了までベゼルの仕様に関しては変わっているように見えません。
私が写真で見る限りその他の部分も何も変わっていないので、早くに完成されたデザインだったということですね。
2020年の今の目で見ても洗練されているように思います。
まとめます(陸特装備目線)。
・初期アフとしては「ツルツルベゼル+NEWS+目盛り」の初期モデルが無難。
・凸凹ベゼル仕様は2001年秋登場なので、初期アフ的にもまあOKだがオーパーツのカラーはあるかもなので注意。
・初期イラクでは初期か凸凹ベゼルが該当。
・ACU登場以降は「ツルツルベゼル+数字」の後期モデルが自然。ただしこれもカラーによってはオーパーツになるので注意。
ネットでブログ等で個人所有の使用個体を見ていると、ベゼルの印刷、ケースの「SUUNTO VECTOR」の印刷がいずれもただの平面への印刷の為、すぐに剥げてしまっています。
オークションで出回っている中古個体もロゴや数字の印刷が剥げている物が多いです。


新品の高級感あるシボも見事に削れてテッカテカの個体が多いです。
使用環境や頻度によると思いますが、1、2年も使用すると印刷もシボもすっかり剥げている傾向があります。
大事な会社名と製品名を掲げたロゴや、機能上必要な数字印刷が1年そこらで剥げてしまうのは、名のある時計メーカーの製品ではあまり考えられないような気がします。
ちなみにロゴについては気になる人もやはりいるらしく、自作デカールを作成されていた方もいるようでした。


個人製作でオークションでほんの少し出品されていただけのようですが、結構需要ありそうですよね。
私も普通に欲しいと思いました。
また、風防も樹脂製の為、かなり傷が付きやすかったようです。
アウトドアでの比較的過酷な条件での使用が前提で設計されたはずですが、(機能ではなく美観を保つ意味での)耐久性は低い構造です。
日本では「フェスやキャンプに着けていきたいオシャレウォッチ」的な売られ方が多かった記憶があるので、この美観耐久性の低さは日本ユーザーのニーズには相反していたかもしれませんね(それでも人気だったようですが)。
神経質なまでにモノを大事に扱う日本人にとっては、なかなか精神衛生上良くない設計ですね(笑)
腕時計としてみたら「雑な外装設計だな」と思いますが、VECTORは腕時計ではなく実用ツールとしての「リストコンピュータ」として設計されたのかもしれませんね。
あくまで装飾品である腕時計とは、コンセプトがそもそも大きく違うのかもしれません。
よく比較されるCASIOのPRO TREKは「時計メーカーが作ったアウトドアウォッチ」で、VECTORは「コンパスメーカーが作ったリストコンピュータ」であって、見た目や機能は通ずるものがありますが、全く違う設計思想の基に産まれたのかもしれませんね。
そもそもSUUNTOは時計屋としての技術は未熟でしたでしょうし。
電池交換もVECTORはユーザーが自分自身で簡単に出来るようになっているという点も、腕時計としたらかなり大胆で常識外な仕様ですね。

ちなみに同じくらいの時期に発売され、同じく気温や気圧、方位センサーを搭載しているPRO TREKのPRG-40は、なんと4つも電池が必要です。

PRO TREKは電池交換無しで数年は使用でき、その代わり交換は専門店等で行うという設計思想なのでしょう。
もしかしたらVECTOR発売当時のSUUNTOは時計店という販売チャネルがなく、VECTORは時計店でのアフターサービスを受けづらいと想定し苦肉の策で「自分で電池を換える」という仕様にしたのかもしれませんね。
こんな感じで調べているうちにどんどん物欲は膨れ上がったので、早速品定めです。
日本でも人気でロングセラーだっただけあって球数は多いですが、上述のような仕様なので総合的に状態が良い個体は多くないです。
中には状態が良いものもありますが当然高価で、使うとすぐに剥げたり傷つくと思うと食指が伸びません。
当然壊れたら修理もできませんしね。
そんな中、初代モデルがチープカシオ並の激安&当時の説明書付きで出品されていたので、思わず即決してしまいました。


使用感がかなりあり、ロゴとWE印刷がいないですが、電動ガンのマガジン1本くらいの価格だったので贅沢は言えません。
説明書の類は年代考察資料として有用な場合が多いので、私にとってはかなり大きいオマケです。
元々やつれている上に安かったので、サバゲで気兼ねなく使えて好都合です。
それに現場で1年も使われればこれくらいにやつれていそうな感じもしますし、初期アフ装備的にはリアルと言えるかもしれませんね。
上の方で写真載せましたが、色も初期アフドキュメンタリー番組「Special Operations Force: America's Secret Soldiers」で隊員が装着していたと思われるブラックです。


無事、初期アフウォッチレパートリーが増えました。
まだ現物は日本の実家にあり、状況が状況なのでいつ帰国して確認できるか分かりませんが、中々良い買い物をしたと思います。
現物確認できたら、また詳細を記事にしようかなと思います。
お読みいただきありがとうございました。