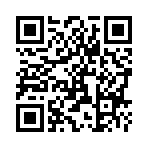スポンサーサイト
モルモット隊鹵獲ザク

先月、3年間の中国赴任を終えて帰国しましたが、今は公私ともに新生活に慣れるのが精いっぱいでブログ執筆できる余裕が中々ありません。
なのでまだ中国に居る間に別SNS(GUNSTA)で投稿したガンプラ投稿をちょい加筆でお茶を濁します(苦笑)
MGザクⅡver.1.0を制作しました。

MGザクⅡver.1.0は個人的には非常に思い入れが深いキットです。
小学生の頃に初めて出会ったMGキットで、近所のおもちゃ屋でお年玉で購入しました。
お年玉を握りしめておもちゃ屋に入ったところ、入り口すぐの目立つ位置にこのキットが置いてあり、もう他のおもちゃには見向きもせずレジに持っていきました。
その後も何度か買い直したり、シャアザクや派生キットの旧ザク等含めると、MG ver.1.0系ザクは10体近くは作ったかもしれません。
今回作った個体は数年前、今のようにガンプラ転売地獄が展開される前に、箱が日焼けした中古品を1500円で入手した物です。
今同じ状態の物を買おうとするとおそらく4000円は取られると思うので、嫌な時代になったものです。
正直、このキットが4000円なら買わないですし、ガンプラ全般今の転売価格相場は定価を知らないで見ても明らかに高過ぎる印象があります。
私は自身を俯瞰して見ても結構なガンプラファンだと思いますし、SNSで公開していいねを沢山もらいたい承認欲求も人並みにあると思いますし、趣味に使えるお金もそれなりに自由にある方だと思うので、ガンプラに注ぐ資金は世の平均より多い部類の人間だと分析していますが、その私が高くて買う気が起きないとなると、一体誰がこの相場を維持しているのか不思議になります。
それとも私のガンプラ愛(=注ぎ込むお金)なんて、世の中の諸兄姉に比べれば味噌っかすみたいなものなのかもしれませんね(笑)
単純に人気があるのは喜ばしい事ですが、メーカー~各種商流に正当な利益が回らない現状は不健康極まりない状況だと思いますので、一日でも早く状況が改善する事を祈るばかりです。
話が逸れましたが、今回制作したザクの詳細を書いていきます。
制作モチーフとしたのは、セガサターンソフト「機動戦士ガンダム外伝III -裁かれし者-」のステージ2で、ブルー2号機が持ち込まれたシャトル基地でフィリップ少尉とサマナ准尉が搭乗したザクです。
まあニッチですね(笑)
ゲーム中の画面はこんな感じです。

今見ると「なんじゃこりゃ」レベルですが、シリーズ第一作の戦慄のブルーを小学生の時発売日に買ってリアルタイムで遊んだ時は、走ったり、飛んだり、すっ転んだり、手を付いてうんしょと立ち上がる3Dのザクを見て感動した覚えがあります。
数えきれない程繰り返して遊んだ、私の中では人生でベスト1、2位を争う大好きなゲームです。
コックピット視点で非常にスピーディーなMS戦が体験出来て、とても楽しいゲームでした。
グラフィックは思い出バイアスかかっても流石にアレですが、ゲームシステム、効果音、ボイス、BGM、ストーリー演出は今でも十分通用するクオリティのゲームだと思います。
プレイ環境を整えるのは結構ハードルが高いですが、未プレイの方は機会があれば是非遊んでみてください。
オープニングムービーだけでもYoutube等で見てみてください。
大塚明夫先生の素晴らしい語りが聞けます。
特にタイトル画面への繋がり方が何度見ても鳥肌モノです。
個人的にはPS2無印ガンダム、ジオニックフロントに並ぶダムゲー神オープニングだと思います。
ガンダムゲームなのに1秒もガンダムが出て来ず、タイトル画面もジムが大写しという、当時としては(今でも?)本当に硬派でチャレンジングな構成だったなと感心します。
今回制作したザクですが、作中ではBD2号機を宇宙へ上げようとしているジオン軍シャトル基地を強襲したモルモット隊が、基地に放置してあったザクを鹵獲、識別コードを連邦軍の物に変え目印に連邦シールドを背負わせ、基地を奪還しにやってきたジオン軍の迎撃に出ていました。


モルモット隊ジムコマンドが装備していたシールドは特徴的です。


本当はジムコマンド用の曲面シールドにしたかったが、当時のセガサターンのグラフィック処理能力の都合でカクカクしたシールドにした、とどこかで聞いた事があります。
その名残なのか、設定画ではノーマルジムシールドとジムコマンドシールドの中間のようなデザインをしています。
1/100ではこのシールドは立体化されていませんので、ガンダムVer2.0のシールドを半分にぶった切って分割、切り代をプラ板で補填してパテで修正し、塗り替えました。

ちょっとしたごく簡単な工作ですが、ガンプラモチベ高い時はモリモリと一気にやってしまうのですが、モチベ低いと一向に手が動かないのが自分でも不思議になります。
ガンプラ制作はいかに自らのモチベを上げるかの修行だと思っています(笑)
本当は上下はジムコマンドシールドのように両端が尖っているのが正だと思いますが、結構工数が掛かりそうなので諦めました。
遠目に見れば雰囲気は出たかな?と思います。
全部作った後に「あれ、もしやのぞき穴無いのが正なの!?」とハッとしましたが、後の祭り、やり直す気力は起きませんでした。。
シールドのデザインは後発の作品でまちまちで統一されていないようなので、「タンカラーで下半分が黒い」という大まかな仕様が合っていればよし、と強引に自分を納得させています(笑)


バックパック裏面とシールドに磁石を仕込み脱着可能にしたので、外せば普通に冬季ザクとして飾っておける「一粒で二度美味しいザク」になりました。

最初は出撃前に大急ぎでジオンマークを塗りつぶして、上から連邦マークを手書きで描いた演出をしようと思ったのですが、ゲームのシチュエーションを見る限りそんな暇はなさそうだったのと、失敗するのが怖くなったので止めました(苦笑)
塗装は白い部分はタミヤの白サフで仕上げました。
真っ白だとどうにも味気なかったので、ノーマルザク色のラッカー塗料をドライブラシして白塗装が剥げた演出をしてみました。

戦車のプラモ等ではよく見かける演出ですよね。
本作は北米のどこかが舞台のはずなので、一年中雪景色だった訳ではないはずです。
ジオン軍が北米大陸に降り立ったのは第二次降下作戦時で、3月頃には北米主要都市を掌握していた認識です。
従って春から秋に掛けてノーマルカラーで運用されていたザクが、冬になり降雪して雪景色になった頃に現場で塗り替えられたと想像しました。
現場での簡易的な塗装作業だったので擦ったりすると簡単に塗装が剥がれてしまい、その部分はノーマルカラーが垣間見えている、といった具合です。
18mの巨人が何に擦れて剥がれたのかを想像すると苦しい所がありますが(苦笑)
ガンプラはこういう「リアルっぽさ」と「そもそもSFだし」という要素ををうまい具合にミックスするのが難しく、また楽しい部分だなと思っています。
スターウォーズのメカや設定なんかも同じ理由で大好きです。
工作に関しては各部合わせ目消し、頭部と脚部後ハメ、流石にダルすぎるモールドをちょこっと彫り直したくらいで、あとはストレート組みです。
MGですが最初期の旧いキットですので、最近のHGよりも部品も構造も遥かに単純で作りやすいですね。
その分ゲートや合わせ目処理が多くて面倒ですが、良い基礎練習になると思います。
便利なツールやテクニックが世に溢れていますが、どんな作業もコツコツと自分の手を動かして経験を積む事が何より上達に繋がるんだ、と自分に言い聞かせ、面倒な作業を頑張るようにしています(笑)
MG ver1.0ザクは可動範囲は絶望的ですが、逆にガワラ立ちさせれば最近のMGキットを凌駕するカッコよさだと個人的には思います。
足首の接地能力が足りず、カトキ立ちはそもそもできませんが(苦笑)
足首は引き出し軸くらい追加工作すべきでした。。
素組みでガワラ肘が出来るのは、このキットの非常に優れたポイントですよね。
まあ頑張って可動範囲拡張したところで知れているので、このザクは割り切って「ガワラ立ち専用ザク」として、我が家の棚を彩ってもらおうと思います。
このザクをもう2体と旧ザクをこさえて、この画像をMG ver1.0で再現するのが直近の私のガンプラドリームです。

最後までお読みいただきありがとうございました。
最近作ったガンプラまとめ PART2

ガンプラから離れていた20年余りに出たキットで作りたかったものはあらかた触ったor欲しくても昨今の品薄で手に入らずなのと、最近はゲームに余暇を割いており制作ペースが鈍っています。
品薄問題は日本のみならずこちらでも顕著で、目当てのキットが入手しづらいというのもやはりモチベーション低下要因のひとつになりますね。
taobao等の通販サイトは、日本で売っているキットを個人または業者単位で輸入しこちらで販売している、所謂転売ヤーの巣窟です。
購入代行の形式もかなり見かけます。
(正規流通品は箱の裏にラベルが貼ってあり、箱の中に中国語の説明書補足折り込みが入っていますので一目瞭然です。)
個人ではなく問屋が転売していたなんて話も浮き彫りになってきて、いよいよガンプラバブルが弾ける足音が聞こえてきましたね。
逆に今度は過剰在庫になって「ガンプラファンなら、バンダイを潰さない為にとにかく買っていっぱい積もう!」みたいな事にならないといいですね(苦笑)
ゲームは無事にゴーストオブツシマはDLC含め完了し、鎌倉時代の対馬を堪能しました。

戦闘自体はかなり楽しいのですが、最初から最後まで基本ずっと同じ立ち回りで勝てるので、流石に終盤は飽きました。
武器防具の強化は中盤でカンスト、戦闘を繰り返しても成長、収集要素も特に無いので、戦闘に関してはワクワク感がどんどん削がれていき作業感が強くなっていくのが少し残念ポイントでした。
マルチプレイもやりたいところなのですが、回線状況を考えると他のプレイヤーに迷惑をかけるだけなので自粛中です。
無事に元国を退けた後、1000万年前のアフリカにタイムスリップして人類を進化させました。
「アンセスターズ」という、人類の祖先の猿を操作して原始の自然界を生き抜き、人類に進化させるゲームです。


新しい領域に踏み出したり新しい食べ物を食べたり、道具を作ったり動物を殺したりすると実績が解除され年数が進み、たくさん実績を解除して1000万年前→200万年前まで進化を進めるのがゲームの目的です。
かなり独特なシステム&敢えてゲーム各種要素の説明がほぼ無く手探りで進める必要がある為、ある程度システムに慣れるまではかなり辛かったですが、プレーが軌道に乗った頃は時間を忘れるくらいのめり込みました。
ただ、これも終盤は作業感が強くなり、最後の数十万年くらいは完全に作業ゲーと化しました。
オートセーブのみでセーブデータ複製不可で、ちょっとした事で群れの猿の数が減って子供が増やせなくなって全滅=ゲームオーバーとなる危険が常にあります。
なので何十時間プレイしていても些細な判断ミスや不運で全滅してしまうと、また完全に1からニューゲームでやり直すしかないという何気に鬼畜仕様です(苦笑)
私は運よく一度も全滅せずクリアまで辿りつけましたが、20時間くらいやって全滅してまた1からとなったら絶対投げ出していたと思います。
続編(200万年以降?)も予定されているようで楽しみです。
人類の進化を辿った後、今はダークファンタジーの世界を満喫しています。
先週発売されたエルデンリングです。


デモンズソウルやダークソウル等、所謂「フロムゲー」と呼ばれる高難易度アクションロールプレイングです。
まだ10時間弱のプレイ時間ですが、かなり歯応えがあって期待通りのゲームです。
今作の新たな試みのオープンワールド方式ですが、いい感じの作り込みで探索していて楽しいのですが、油断するとザコ敵に瞬殺されるゲームなのでずっと緊張しっぱなしなのは少々疲れます(苦笑)
あと次にやりたいのはSTRANDED DEEPという孤島サバイバルゲームです。



PC版は2015年に発売しているようですが、昨年SWITCH版が北米等で発売したようです(日本版は未発売)。
北米版でも日本語が入っている事が分かったので、ニンテンドーの北米アカウントを作ってダウンロード購入しようと思います。
再来月21日間中国のホテルで隔離される予定なので、その時の楽しみに取っておくつもりです。
前置きが長くなりましたが、ご覧のように今はゲームメインの生活ですが、亀ペースながらここ数か月で作ったキットを記録しておきます。
前回の記事は去年の8月の旧キット 1/100ハイザックでした。

「ハイザック 火力支援型」
今回はその後制作したキット達をまとめて記録しておきます。
まずはHGUCジムスナイパーⅡをミキシングしてスタイル&可動範囲UPさせたジム・コマンド宇宙用です。



両機は同作品に登場しデザインは似ていますが、HGUCとしての発売時期は大きく違い、先に出たジム・コマンドは今の目でいるとどうしても古臭い構造です。
そこで、比較的新しいジムスナイパーⅡの各部品を移植する事でアップデートを図ったものです。
まあよくある凡庸な発想のミキシングですね。
下の基本工作終了時の写真を見ていただければどうミキシングしたか一目瞭然だと思います。

頭部、胸ダクト、前横腰アーマー、膝から下、武装はジムコマンドで、後はジムスナイパーⅡのものです。
ちょっと手間だったのは胸ダクトの合わせと膝関節部の加工くらいで、あとはそのまま小加工で素直にバランス良く組みあがりました。
ミキシング入門教材としてはかなり良質かもしれません。
ミキシングにより狙い通り可動範囲拡大、スタイルアップできましたが、右肩のアンテナを忘れたのが痛恨のミスです(苦笑)
次です。
伝説のアーケードゲーム「連邦VSジオンDX」に登場した鹵獲アッガイをHGUCで再現しました。




当時「アガえもん」と呼ばれ人気を博し、昨今のアッガイ=可愛いキャラの礎になった認識です。
塗装は勿論、デカールもゲームCGをなるべく再現しました。
キットはクローが片腕しか入っていませんが、ゲームは両腕クローのZZで出てきたハマーン様搭乗機仕様なので、わざわざ2機調達しました(笑)
もう一機はミリタリー色強めに仕上げるつもりです。
いつかの記事でも書いた記憶がありますが、私は連ジリアルタイム世代(無印とDXの過渡期あたりからデビュー)で、高校生時代は毎日のようにゲーセンに通って対戦に明け暮れていました。
稼働当初は連邦軍は連邦の機体のみ、ジオン軍はジオンの機体のみ選択可能でしたが、ある日突然「鹵獲モード」が解放され、両軍がどちらの機体も自由に使えるようになりました。

奇抜なカラーリングのジオンMS達を初めて見た時の衝撃は今でも覚えています。
制作にあたり、家にあるPS2とソフトを引っ張り出してきて細部を観察しました。

ゲームの方はキットより頭がデカくて胴が短くて、よりコミカルな印象ですね。
セーブデータは消えてしまっていたので、一回ストーリーモードを全クリして鹵獲モードを解放する必要があり、約20年振りにプレイして超懐かしかったです(笑)
旧いゲームなので素直におススメはし難いですが、数多あるガンダムゲームの名作中の名作であることは疑いようがありませんので、ガンダムファンの方は一度プレイする価値はあると思います。
特に効果音はかなり拘りを感じ、各武装の発射音やブースト音、被弾音、各MSの足音の違いまでも劇中とまったく同じです。
ファーストファンには必ず響くと思います。
次です。
HGUCジムⅡを小改造し、オラジム(オラが設定のジム)を制作しました。




HGUCジムⅡは肩でかくて胴短くて、肘関節が破綻している動き方をするところがイマイチです。
キットを修正しようとも思いましたが、家に転がっている余剰パーツ達を使ってミキシングした方が早いなと思ったのが制作のきっかけです。
HGUCジムⅡとオリジン系キットをミキシングして「要撃機(インターセプター)に現地改修されたジムⅡ」というコンセプトで組み上げました。
考えたオラ設定は下記です。
各部スラスター増設により、要撃任務に必要とされる機動力と運動性を確保しています。
胴体:ジム・ナイトシーカーに採用された胸部スラスターシステムを装着
肩部:高出力アポジモーターを搭載
脚部:ふくらはぎ部にスラスターを増設
バックパック:ネモの物に換装


艦隊直掩や施設防衛向けの機体の為、航続距離は重視されておらず、各種スラスターは効率よりも瞬発力重視のセッティング、各関節のフィールドモーターの出力設定はAMBACを最大限活かす為にリミッターを解除してあります。
運用の汎用性、安定性は失いますが、その代わりに量産型機体をベースにして、パーツさえあれば前線で任務中の艦艇内でも行えるレベルの改修作業で運用特化したMSを構築する事が可能です。
しかし本来の設計思想を完全に無視したピーキーなセッティングとなる為、必然的に乗り手を選ぶこととなりました。
輸送部隊が前線の艦隊にパーツを補給さえすれば、その場で即時改修実施でき、支給されたジムⅡでは能力を存分に活かしきれない上級パイロット達に喜ばれました。
といった感じの設定を妄想しながら制作に勤しみました。
HGUCジムⅡとオリジン系キットの異時空ミキシングでしたが、大きな加工は不要でバランスも問題無く、手間はほぼ掛かりませんでした。
全部塗った後に、オリジン系部品はある程度モールド埋めといた方がバランス良かったなと思いましたが、面倒だったのでそのまま突き進みました。
次です。
MG陸戦型ジムをリアルタイプガンダムカラーに塗ってみました。
カラーリングは悩んだ末、半ば勢いでこの色で塗りましたが、結果かなり好みな仕上がりになりました。



元は他のキットに武装を取られて「ただの緑色の陸ジム」となったジム・スナイパーです。
キットのパーツだけでは通常陸ジムバックパックは組めないので、プラ板で補足してバックパックを仕上げ、家に在庫している武装を持たせました。
武装はガンダム用の物を持たせました。
折角なので下記のような設定もでっちあげてみました。
このRGM-79[G]先行量産型ジムは、第11独立機械化混成部隊「モルモット隊」や第20独立機械化混成部隊「スレイヴ・レイス隊」と同列の、ジャブロー直轄の第6独立機械化混成部隊で運用された機体です。
当部隊を含む第4、5、6独立機械化混成部隊はV作戦の補助的な役割を担い、V作戦で開発されたMS用装備の実戦データ収集が目的の部隊です。
ホワイトベース単艦では短期間での各種試作品の十分な評価は不可能と判断され、RX-75、RX-77、RX-78それぞれの装備を個別に評価する補助部隊が設立されました。
第6独立機械化混成部隊はRX-78用の武装評価を担当し、保有するRGM-79[G]にRX-78用の試作武装を装備させ、地球上の各戦線を転々とし実戦運用データを収集しました。
といった感じの妄想設定機体です。


旧いMGなので可動範囲や関節部の見た目は今の基準だとイマイチですが、全体的なプロポーション、ディテールは素晴らしいです。
目立つ合わせ目も頭部の単純な前後割りだけで、あとは処理しなくて問題ないレベルです。
頭部は後ハメ断念し、パーツ単位で塗装→全部組んで合わせ目消し→合わせ目消しした部分のみ再塗装で凌ぎました。
あと手首パーツは初期のMGでは標準的だったPC素材で、造形悪い、表面仕上げ難しい、塗料乗らないと三重苦なので社外品に換装しました。


MGは初期キットでもストレート組みで十分なディテールで、安定してますね。
パーツ数の多さやゲート&PL処理は少々面倒ですが。
最後です。
MG F2ザクを組みました。






戦後に残党軍がキンバライト基地で運用していた想定で、ツギハギ装甲にして補給の困窮具合を演出しました。
プレバンのキンバライトザクを購入し、主要パーツは成形色で楽しました。
劇中のキンバライトザクのカラーリングもシブくて好きなのですが、プラモにするとちょっと情報量が少なくて味気なくなりそうな気がしたので、胸部を少し塗り替え通常量産カラー+砂漠カラーのツギハギにしました。
今回スポンジチッピングに初挑戦しましたが、中々いい感じに仕上げられて満足です。
シュツルムファウストラックは本来腰に着けますが、小改造してバックパック側面に移設しました。

赤いマーキングシールの下がスミ入れの影響で割れてしまってますね...。
スナップフィットは軸が圧入なので常に雌側の部品に応力が掛かる状態になり、スミ入れ塗料等で強度が下がると割れてしまう場合があります。
組立時にちゃんと圧入具合を調整しないといけないのですが、手抜きしたツケが回ってきました。
あとはモノアイをビルダーズパーツに置き換えディテールアップ、ショルダーアーマーの合わせ目消したくらいで超簡単仕上げです。


塗装もろくにしていない手抜き作業ですが、元々のキットの出来の良さに助けられてそれなりに見られる一体になりました。
こんな感じで、相も変わらず1年戦争期のガンダム以外のMSのキットばかり作っています。
現在部屋にキットを結構積んでいますが、そろそろ日本に帰るので嵩張るランナーから部品を切り離し、とりあえずひたすら素組みしてコンパクトにしています。
表面処理や塗装は帰国したら時間を見つけてゆっくり進めようと思います。
ガンプラ制作ペースはさらに落ちてしまいそうですが、これからもちょこちょこ触り続けようと思います。
息子をガンプラに引き込めればこっちのものなんですが(笑)
まだまだガンプラを作れるような歳では無いので、しばらくは細々と活動することになりそうです。
お読みいただきありがとうございました。
ハイザック 火力支援型

アフガンが大変な事になりましたね。
カブールの空港の様子はベトナム戦争終結時のサイゴンに重なりますね。




Zガンダムのジャブロー攻略戦時に、核の時限爆弾があると知り逃げ惑う連邦将兵達も全く同じ構図ですね。


まあこのシーンはベトナム戦争時のサイゴン退去の様子をモチーフにしたらしいので、似ていて当然なのでしょうが。
「ここにいたら確実に死ぬ」と思ったら、余程達観した人間でもない限り正常ではいられないのでしょうね。
私もその場にいたら、他人を押しのけてでも助かろうと藻掻くことになると思います。
タリバンと聞くと「厳格過ぎてヤバイ人たち」というイメージしかありませんが、今後どうなるんでしょうね。
個人的に興味深いなと思った考察記事を貼っておきます。
https://www.jiji.com/jc/v4?id=20210817world0001
きっと近い内に池上さんがTV特番で分かりやすく説明してくれると思うので、それ見て勉強しようと思います(笑)
タイムリー過ぎて不謹慎と言われちゃうかもですが、ミリオタ的にはタリバン兵の装備は少し気になりますね。
随分と西側チックな装備の人もいるようです。

右手に持っているのはU字スイングストックのAKだと思われますが、プレキャリにはSTANAGらしきマガジンが入っているのが謎です。
U字ストックでSTANAGマガジン対応のAKなんてあるのでしょうか?
AR系のライフルを携えている兵士も結構いるようで意外でした。


ちなみに一番後ろで右向いている黒ターバンの人は56-2式ですね。
ストックが特徴的なので判別が楽ですね。
PEQ2らしき照準装置をのっけている人もいました。
暗視装置まで使っているんですかね?上の写真の兵士はメットにNVマウント付いてますし。

それか我々が触るレプリカみたいに可視光レーザーのパチモンとかですかね。
ゴテゴテに盛られたAKも使ってたりします。

めっちゃ指トリガーですね(笑)
こうして大々的にメディアが入り込むと装備考証は捗りますが、直近サバゲで再現して着ていくのはかなりの勇気が必要ですね(苦笑)
では本題に入ります。
この度、ようやく1年戦争時代以外のガンプラを作りました。

昨年初夏頃にガンプラ復帰し、今まで30体以上作ってきましたが、ザクが全体の1/3、ジムが1/4、ドムグフで1/4を占めており、全て設定上1年戦争時に存在した機体しか作っていません。
ガンダムに至っては未だに1体も組んでいません(苦笑)
小さい頃は今よりはまだガンダム系も好きでキットもいくつか組んだことはあったのですが、今は全然食指が動きません。
今回もザクといえばザクですが、れっきとしたZガンダム世代の機体となります。
組んだキットは旧キットの1/100ハイザックです。
ガンプラ界隈ではしばしば「神キット」と崇められているキットです。
36年前に発売した旧いキットですが、今の時代でも通じる先進的な構造がふんだんに盛り込まれ、造形も古さを全く感じさせません。
どでかいバックパックが最高ですね。
フィンもしっかり可動します。
大人になって色んなMSのバックパックに非常に目がいくようになりました。
歳を取って異性の体の部位の好みが変わる話はよく聞きますが、MSの部位の好みも変わるものなんですね(笑)
ディテールも申し分なく、5本指独立可動や手首カバー、スリッパの前後独立可動等、現代のキット並に作り込まれたギミックに驚かされました。
可動も部分的には現代キットすら凌駕する驚異的な可動範囲を誇ります。
こんな股割り出来るキット、最新キットを含めても数える程ではないでしょうか。
邪魔な動力パイプがある割りには非常によく動きます。
スカートアーマーを別体化し、各関節部を少しだけいじればかなり動くポテンシャルは持っていると思います。
各関節も挟み込みながらPCで回転軸を保持する構造になっており、グリグリ動かしても削れてユルユルになってしまう事はありません。
足の付け根は現代キットでは標準的ですが、なんとロール軸があります。
35年以上前のキットに既にこの構造があったなんて本当に驚きました。
股関節の進化は、単純な軸差し→ボールジョイント→軸差し+ロール軸→軸差し+ロール軸+軸スイング、といった感じだと思いますが、このキットはボールジョイント時代に突入する前の発売のはずなので、完全に時代をすっ飛ばして先取りしていますね。
ちなみに足首もちゃんと関節が3軸(裏ワザ的に足首引き出しも入れれば4軸)あるので、無改造で綺麗なハの字立ちが可能です。
頭部はシンプルなモナカ構成で、モノアイはカバー状の部品にデカールを貼る方式になっています。

ここは流石に時代を感じたので、カバー部品は使わず脳天に軸を挿して回転するモノアイユニットを新造しました。
中身スカスカだったのでとりあえず艶消し黒で内側を塗り、下側に黒く塗ったプラ板で蓋をして真っ暗にしてごまかしました。
モノアイレールのディテールをスクラッチできる技術がある人がうらやましいです。
キットのカバーパーツは、UVレジン等でクリアパーツで複製すればそのまま透明のモノアイカバーとして成り立ちそうな構造です。
まさか当時そこまで見越した設計だったとしたら戦慄しますね(笑)
クチバシのダクトも左右で真っ二つで接着合わせ目消しでは対応しきれないので、一度くり抜いてプラ板で新造して置き換えました。
私は出来るだけ目立たない部分は手抜きしたがる性分ですが、頭部は細かい所も目が行きがちなのでここは少し手間をかけて作り込みました。
頭部以外はMGハイザックと並べても全く遜色ないというか、知らない人が見たらどっちの方が新しいキットか分からないレベルだと思います。
1200円でこのボリューム感と緻密感、噂に違わぬ名作キットだと体感しました。
ちなみにMGハイザックはこんな感じです。

顔の大きさはかなり違うので好みが分かれますが、その他は優劣つけがたい造形だと思います。
MGハイザックも隠れた名キットとして有名ですね。
今は品薄でバカみたいな転売価格が付いていて買う気起きませんが、いつかちゃんとした小売価格で手に入れて組んでみたいです。
ガンプラは基本的に絶版は無く、何十年前のキットでも再販を待てばいつか手に入るというのは希望があって良いですね。
旧い絶版初期アフ関連アイテムを集めている身からすると素晴らしい環境です。
箱絵もカッコイイですね!

全ガンプラ100円くらい高くなってもいいので、パッケージは全て手書きの情景風にして欲しいです。
MGは一部を除いていいですが、HGUCは発売当初から味気ないですし、プレバンは白黒印刷を即刻廃止して欲しいです。
何か深い意図があるのかも知れませんが、私のような凡人にはただのコストカットにしか見えずケチだとしか思えません。
店頭に並べないので豪華なパッケージで客の購買意欲をそそる必要が無く、質素なパッケージは合理的と言えば合理的ですが、商品が届いてワクワクしながら開梱して、出てくる箱がショボいのはやはり寂しいものがあります。
特にプレバン商品は買える時期が限定されるので、「とりあえず確保しとかなきゃ」で、永らく部屋に積んでおく方も多いと思います。
なので尚の事カッコイイ箱絵がいいなあと思うのですが、少数派なんでしょうかね。
ガンプラに限らず、中身が同じならパッケージは金を掛けず1円でも安い方が良いという向きは一定数あると思いますが、個人的にはパッケージ含めて「その商品」と思うので、ちゃんと力を入れて欲しいなと思います。
最近ではSDGsという言葉が流行っていますので、逆にしっかり作り込んですぐ捨てるのではなく、「商品の一部」として永く使えるパッケージにした方が時代の潮流に合う気がします。
その点、マルイのAKMはパッケージがそのまま銃のカバーに出来るようになっていて面白いなと思います。

話が脱線してしまいましたが、キットを見ていきます。
超優良キットなので、ゲート処理や合わせ目消しを丁寧にして素組みでも全然良かったのですが、せっかくなので手持ちの在庫パーツをやり繰りして、下記のようなちょっとしたオラ設定を付け加えました。
連邦宇宙軍所属機で、旧ジオン軍から接収したビームバズーカを装備し、中距離火力支援を担当する機体です。
ハイザックはグリプス戦役勃発前、対ジオン残党の不正規戦に対応する設計思想で開発された為に、大規模な艦隊戦向きの武装開発は重視されていませんでした。
しかしグリプス戦役が勃発し組織的な艦隊戦に対応できる武装が急遽必要となり現地改修された機体、といった妄想を発端にしたオラザックです。
ベースが超名作機のザクⅡなので、その遺伝子を継いだハイザックも、本来想定されていなかった武装運用もお手の物だったはずですね。
ちなみに、一応ハイザックも対艦用?兵器として2機1組で運用する大型メガバズーカランチャーが劇中で登場します。

自分の体よりも大きく、1機分のジェネレータでは駆動できないので電源用としてもう一機随伴が必要という、ちょっと運用が特殊過ぎる兵器です。
「電源用にもう一機必要」という野暮った過ぎる設定は個人的にかなり好みではありますが(笑)
本機はそれよりも低威力短射程ですが、単機で十分な柔軟性を持った運用が出来る、という位置づけで妄想しました。
この旧ジオン軍製ビームバズーカは、開発当時から巡洋艦の主砲並の火力を有するので、想定される運用上威力は十分と判断し、作動安定性のみチューンナップされ出力の増強は施されていません。
1年戦争期のMSよりも高性能のジェネレータが搭載されているハイザックが装備する事でチャージ時間の短縮が実現しており、単位時間あたりに発揮できる火力は大戦期のジオン製MSが扱うより増加しています。
ジオンの兵器にEFSFマークを貼るのって、なんか背徳感ありますね(笑)
鹵獲繋がりで余談ですが、高校生の頃ゲーセンである日突然「連邦VSジオンDX」で「鹵獲モード」が解放され、ドラえもんみたいな色のジオンMSを見た時は衝撃でした。

ちょうどHGUCアッガイを家に積んでいるので、今度作ってみようと思います(笑)

ビームバズーカはMGリックドムから持ってきました。
実は以前リックドムを作った際に、誤発注でリックドムが2機届いてしまいました(笑)
一機は制作済で、ビームバズーカはディテールダウンして旧キットのドムに持たせました。
「ドム→リック・ドム換装機」

「旧キット 1/100ドム」

もう一機は全然制作モチベが上がらなくて困っているのですが、とりあえずビームバズーカは今回のハイザックで供養できました。
バズーカのグリップがかなり太いので、握らせる為にハイザックの指関節を第一関節で一度切り離し、開かせて表情を付けて再接着しました。
手首って小さい部分ですが意外と全体の印象に大きく関わってくるので、いつもちゃんとしようと力を入れて取り組んでいます。
残念ながらキットの指の保持力ではとてもこの巨体を握って保持は出来ないので、グリップと掌はスーパーXで接着固定しました。
肩に担がせる為の改造は手首の傾きを大きくする為に袖口を少し削り込んだくらいで、ほぼ無改造でいけました。
この辺り、本キットの懐の深さを感じました。
バズーカ運用に邪魔な右肩シールド、左肩スパイクは外しています。
右肩はバズーカの保持安定と肩関節への負担を軽減させる為にショックアブソーバーを装着しています。
MGジム・スナイパーカスタムの余剰部品を使い適当にでっちあげ、ハイザックのシールド接続部をそのまま流用し接続しています。
デフォルト装備のハイザックは、一年戦争を戦い抜いた生粋の連邦パイロットにとって「いかにもザク然」とした外観が不快で、ザクの象徴でもあるスパイク等の装備を外す事は茶飯事だったかもと妄想しました。
今回の制作にあたり最初の構想時は、「ザク頭も嫌で頭部をジム改かジムⅡあたりに換装した」というのも面白いかなと思ったのですが、同じような考えを持っている方は私の他にもいたようで、ネットで下記画像を拾いました。
思っていたよりめちゃくちゃサマになっていて驚きました。
このセンス抜群で完璧と言える作品を見て満足したというか、これを越えられる自信が完全にゼロなのでジムヘッド案はボツにしました。
ハイザックはジオン系列MSの駆動形式である流体パルスシステムと、連邦系列のフィールドモーターシステムのハイブリットという設定です。
量産機で駆動方式を2種積むなんてなんかムダに贅沢じゃね?とは思いますが、その設定のおかげでジムヘッドでも納得が出来ます。
今回キットを制作するにあたり、ハイザックの事を色々調べて勉強しましたが、かなり面白い立ち位置のMSですね。
アニメの都合上、ガンダムと相対する敵役としては一つ目のザクが分かりやすいですが、Zガンダムは連邦軍内の組織抗争が舞台です。
なので連邦軍なのにザクがいる、という歪な設定する必要があったそうです。
戦後アナハイムエレクトロニクスがジオンの技術を吸収し、ザクⅡの生産ラインを活用し連邦技術と融合して生まれた機体、という無理があるんだか無いんだか絶妙な設定が付随しています。
カラーリングに関しては、ティターンズの正式カラーは元々のザクに似た緑色ですが、アニメ的な理由は「ガンダムの敵として分かりやすいから」ですが、(多分後付け)設定上は「ジオン残党に対して心理的効果を与える為」という、これまた無理があるんだか無いんだかな絶妙な設定があります。

この辺りの設定は後作品の0083に反映されているのかもしれませんね。
トリントン基地強襲時に、連邦のF2ザクを見たジオン残党兵ゲイリーが「連邦に下ったその姿、見るに忍びん!」と言って両断するシーンは有名ですね。

ジオン公国軍の象徴であったザクは、ジオン将兵にとっては一際特別な存在だった事を伺わせ、上記のティターンズハイザックカラーの裏付けとして読めなくはありません。
ちなみに連邦カラーはこれまた絶妙な色合いです。

ジムと同じ胴体赤、手足白にしないあたり、アニメの都合なんでしょうかね(似たような色のMSばっかりだと見栄えしない)。
目視確認が重要な戦況判断材料になる宇宙世紀の戦場をリアルに考えれば、当然似たような色で統一する方が良いとは思います。
そんなアニメの都合と陣営設定の歪みの狭間で生まれたハイザックに思いを馳せながら、制作に勤しみました。
バズーカを撃ち尽くした後や、不意の接近戦となった場合の自衛兵器として、ジム用の二連装ビームガンを腰に装備しています。
パイロットは1年戦争時から連邦軍のMSパイロットとして従軍し、ジム・スナイパーカスタムから本機に乗り換えている為、当時から使い慣れているビームガンを使用しています。
近接武器も使い慣れたビームサーベルを使いたいところでしたが、ハイザックの泣き所である「出力の関係で2つのビーム兵器の同時駆動は不可」という制約の為、泣く泣くヒートホークを装備しています。
この制約も「ザクなんだからヒートホークだろ」というアニメの都合の産物なんですかね。
ハイザックが生まれる5年以上前に既にジムとかゲルググがビーム刃を出しながらビーム兵器撃ちまくってるのに、ハイザックが出来ないなんて冷静に考えると不自然過ぎですよね(笑)
ヒートホークは1部品構成でがっつり肉抜き孔が入っていて、もうちょっと凝って欲しかった思いはありますが、キットの価格を考えれば十分な完成度だと思います。
MGハイザック1体分+数百円のお金でこっちは3体買えてしまいますからね。
ヒートホークは磁石を埋め込んで背面腰部に付けられるようにしました。
ただ、バックパックとの位置関係をあまり考えずに磁石配置してしまったので、干渉してしまっています(汗)
カラーリングもパイロットの意向で以前の愛機のスナイパーカスタムをオマージュしたものにしています。
本当は正式連邦カラーのハイザック色に塗りたかったのですが、あの絶妙な青紫色を出せる塗料が無く、泣く泣く諦め悩んだ末に「元スナカス乗りだったパイロット」という苦し紛れの設定をしました。
キット自体は頭部以外ストレート組みですが、ボリューミーなガチムチ体型は今の目で見ても十分イケてると思います(ほんの少し頭デカい印象ですが、好みの範囲かと)
MG並に部品数が多く、組み応えがありました。
後ハメは各箇所かなり悩みました。
というかほぼ後ハメ化できず、完全に組んだ後だとマスキング塗装も難しい箇所が多かったので、まずバラバラの部品単位で塗装した後組み立てて合わせ目を消し、合わせ目消しした部分だけマスキング塗装、という工程で凌ぎました。
各部の動力パイプも挟み込み構造ですが、これは嵌合部を一部切り取る事で簡単に後ハメ化出来たので助かりました。
動力パイプが後ハメ化できなかったら心折れてたかもしれません(笑)
缶スプレー基本塗装、細かい部分はエナメル筆塗りで塗り分けしています。
塗装→デカール→艶消しクリア→ウォッシング、スミ入れ→艶消しクリア→ドライブラシで完成です。
これが35年以上前に発売されていたとは、にわかには信じられません。
そして部品数の多さにびっくりです。片方の足首だけで16パーツもあります。
初期~中期のMGより多いのではないでしょうか。
説明書も詳細解説が付いて読み応えがあってお得感があります。
もちろん最新のキットに比べれば構成の古さや部品精度の低さを感じますが、発売時期を考えるとまさに「オーパーツ」と言っても過言ではないキットですね。
当時設計された方は天才か、もしくは未来人だと思います(笑)
現状品薄な感じですが、あまり人気は無いのかオークションサイト等に出ても定価+α程度が相場のようですね。
元々がバリューが超高いキットなので、数百円上乗せ程度だったら入手しても十分満足できるとは思います。
成形色分けも優秀なので、素組みでも十分見栄えするという点でも時代を超越した異様な完成度のキットだと言えると思います。
ある程度子供が大きくなったら、さりげなく見える所でガンプラ拡げて作ってみせて興味を持たせ引きずり込みたいですが、それで私のようにニッチなオタクになってしまうのもそれはそれで生きづらそうなので、悩む所です(笑)
いずれにしても、こんなに毎日自由気ままにガンプラいじっていられるのは、今の中国赴任が終わったら次は20年30年後だと思いますので、今の内に飽きるくらい触っておこうと思います。
お読みいただきありがとうございました。
最近作ったガンプラまとめ

当ブログのアクセス数が40万を超えておりました。
10万桁の更新は少なからず達成感がありますね。
2017年5月に開設したので、平均約250アクセス/日という事になります。
流行りのトイガンのレビュー等は一切なく、ニッチな記事ばかりのマイナーブログに足を運んでいただきありがとうございます。
こうしてネットの海に自分の頭の中身を垂れ流す以上、どれくらいの方が覗いてくれているという指標となるアクセス数は、やはりモチベーション維持の大きな要素になります。
ただ、アクセス数を稼ぐ事をブログ運用の主目的としてしまうと、個人的には本末転倒だと思います。
これは他のSNSでも言える事だと思います。
個人が非営利目的でSNSで投稿する事は、なるべく多くの「いいね」をもらって快感を得る為ではなく、文字や写真で自分を表現し、共鳴する仲間と繋がったり、有意義な情報や意見を交換する為であるべきだと思います。
多くの人に(良い意味で)注目されたり称賛されたりすることで快感を得るのは人間の本能と言えるでしょうし、そのおかげで人間社会は発展を続けているのは間違いないとは思いますが、快感を求めるあまり手段を選べなくなってしまっては、その先は「豊かな人生」とはかけ離れた、ある種の「不幸」とも呼べるものしか待っていないのではないかなと思います。
食欲や性欲もそうですが、ある程度の金銭を差し出せば如何様にでも欲を満たせるように構築されている人間社会において、「理性的に欲を満たす」という能力は今後さらに必要とされてくるかもしれませんね。
なんか賢そうな文言をとりあえず並べてみて悦に入ったところで(笑)、そろそろ本題に入ります。
すっかりガンプラ記事更新が滞っていましたが、制作自体は一定のペースで続けています。
ここ最近制作したガンプラ達をメモ程度にまとめておこうと思います。
ちなみにトップ画像は最近作って撮った中で、抜群にお気に入りの1枚である高機動型ゲルググ改君です。
まずはHGオリジンのブグです。




ブグはオリジンで新たに設定された、旧ザクの先輩にあたるMSです。
「旧ザクよりも高性能だったが、高コストの為量産化は見送られた」という、中々憎らしいツボを突いた設定の機体です。
劇中ではランバ・ラルが専用機カラーで乗っているのみですが、ワンオフ機ではなく複数機試作され、実戦投入もされたという設定があります。
そこからインスパイアされて、1年戦争序盤に実戦投入された機体という設定で少しだけいじりました。
各種武装はザクのものに換装されています。
両肩の装備はブグのままでも良かったのですが、ブグ肩アーマー側面の梯子みたいな突起が意味不明過ぎてすごく嫌なのでザクの物に換えました。

カラーリングは当初オリジンザクの量産カラーにしようと思ったのですが、思い付きでリアルタイプカラーにしてみました。
シールドのデカールはわざわざガンダムベース限定のHGリアルタイプザクを入手し、使用しています。
今までブグはなんか顔が気に入らなくて敬遠していましたが、実際に組んでみたらかなりの良キットで、緑色にしてみたら一気に愛着が湧きました。
次に制作したのはジムキャノン空間突撃仕様です。




MGジムキャノンの脚部を改造しました。
ジムキャノンを宇宙で効率よく運用する為、重力下でキャノンを発射する為のウエイトである脚部装甲を外し、代わりにバーニアを装備したという設定の機体です。
MSV-Rに出てくる公式機体ですが、まあ地味な設定ですね。
HGオリジンでMSDとしてリファインされキット化されていますが、多くのファンが「コレジャナイ」と思ったはずです(苦笑)

普通にノーマルジムキャノンを出して空間突撃はプレバンにするか、もしくはコンパチで組めるようにして欲しかったですね。
HGUCバーザムが出たと思ったら、3年もしないうちに何故か完全新規のAOZ版バーザムを出したりと、未だにバンダイのキット化の意向がよく分かりません。

3年経たずに似たようなバーザムのキットを2体出すくらいなら、他にも出すべき人気機体があるだろうと思うのですが。。
(AOZバーザムは出版社との関係とかの大人の事情があるのかも?しれませんが)
それともバーザムって個人的には影が薄いというか変化球的な立ち位置だと思うのですが、意外と人気あるんですかね??
話が逸れましたが、MGジムキャノンにはジム用の余剰外装パーツが大量に付属するので、それを利用して脚部装甲を改造しました。

設定画やHGオリジンキットを見本にプラ板を切った貼ったしてこしらえました。
バーニアは設定通りジムスナイパーカスタムの部品を持ってきました。

次は上記のジムキャノンのバーニア部品取りをするために調達したスナイパーカスタムを作りました。


脚部バーニアを取られてしまったので地上戦仕様という事にしようと思いましたが、スナカスは1年戦争終盤に登場したので、戦争中に地上での運用は無かったと考えました。
そこで、デラーズ紛争終結後ティターンズ発足直後の所属機という設定を考えてみました。
ティターンズはエリート部隊といえど、デラーズ紛争で疲弊した連邦軍で潤沢な装備は揃えられなかったと思います。
そこで、既存兵器の組み合わせで有効な運用法を模索した結果生まれたのが本機です。
1年戦争時、陸戦型ジムで運用された大型ビームスナイパーライフルユニットを高性能センサーを装備するスナイパーカスタムに装備させ、狙撃特化の運用とする事で、UC0084年においても十分実戦で通用する機体だった、という妄想をしました。

陸戦仕様の為脚部バーニアは外され、代わりに強化型フィールドモーターを搭載したという設定とし、ジャンクパーツで蓋をしました。

セカンダリも100mmマシンガンも連邦軍初期のMS兵装ですが、この頃の製造品はコスト度外視で開発、生産されていた為造りがよく、後発の武装よりも信頼性が高かった、というこコジツケをして家の在庫のマシンガンを持たせました(笑)

MGキットは単価が高いので、HGのように部品取りの為にホイホイ買えないのが少々辛いですね。
このスナカス制作の為にジムスナイパーを調達し、武装無し、バックパック無しの真緑の陸ジムが残ってしまったので、どうにかしてあげないといけません。
次です。
ガンプラでは無いですが、ROBOT魂というフィギュアを塗装しました。

ジョニ―・ライデン専用高機動型ザクを量産機カラーに塗りました。
ジョニーのR2型は公式設定上4機しか作られておらず、全機に搭乗者が設定されてしまっているので、公式設定に矛盾しないようにオラ設定を作りました。
ジョニーはキマイラ隊に転属する際、部下のエマァ・ダイス少尉に高機動型ザクを引き継いだというのが公式設定です。
その設定を利用し、引き継いだ後にエマァ少尉は量産カラーに塗り替えて使っていたという妄想をしました。
ジョニーカラーのままだと敵味方からジョニーに勘違いされてしまうので、塗り替えたというのはまあ自然かなと思っています。
搭載艦であるムサイ級プリムス内の簡易設備で塗装されたので塗膜が弱く、デブリの接触等で簡単に剥げてしまっているという設定です。

バーニアや武器発射のエフェクトパーツが付属していて遊び甲斐があります。


子供の頃あったらさぞ楽しかったんだろうなあと思いましたが、もし子供の時にこれが売っていても値段的に指を咥えて羨ましがる事しかできなかったですね(苦笑)
これを作ったタイミングから小型の撮影ブースを導入し、シンプルな背景で撮影できるようにしました。
次です。
HGUCリバイブ版のシャアザクと旧ザクをミキシングして、最新フォーマットの旧ザクを作りました。



リバイブザクですが、このフォーマットでどんどんバリエーション機出してくるかと思いきや、発売から1年経ってようやく年末に色替えの量産型が出る始末です。

しかも本当にただの色替えのようで、全塗装する身としてはほぼ何も得る物がありません。
せめて新規で脚部ミサイルポッドくらい付けて欲しかったですね。
この調子では旧ザクリバイブなんて夢のまた夢なので、自作した次第です。
頭部と胸部パネルをHGUC旧ザクから持ってきて、シャアザクの方は動力パイプを取っ払い穴を埋めたのみのお手軽ミキシングです。



アニメっぽい造形なのであまりリアルなミリタリー的考察はせず、1つのキャラクターモデルとして仕上げました。
終始そこまでモチベーションが上がらず適当に表面処理したので、パテ埋め部がモロ分かりで恥ずかしいです。
今振り返れば表面処理時にもっとしっかりやっとけばと思いますが、後悔先に立たずというやつですね。。
ミキシングの具合は良好で、もうこのままのデザインでキット化して出してくれればいいのにと思えるくらいのフィット感でした。
金型は新規に起こさなければいけませんが、設計期間とコストはほぼ無しでキット化できて省エネだと思うのですが、旧ザクなんてそんなに売れないんですかね?
(少なくとも上の方に書いたAOZバーザムよりは確実にメジャー機体だし売れると思うのですが...。)
次です。
トップ画像にした、高機動型ゲルググ改または高機動型ゲルググR型と呼ばれる機体を制作しました。





B-CLUBというバンダイ公式のガレージキットブランドが出していた改造キットが偶然激安で手に入った為、チャレンジしてみました。


レジンキャストキットは初挑戦でしたが、インジェクションキットとは全く勝手が違い苦戦しました。
脱脂や歪みの矯正等、色々学べて良い経験になりました。
特に大きな失敗は無く、何とかカタチにできました。
高機動型ゲルググ改といえばキマイラ隊ですが、キマイラ隊のデカールは持っておらず知識も中途半端だったので、一般的なア・バオア・クー防衛隊所属機という設定で仕上げました。
ソロモン戦にて連邦軍のパブリクによるビーム攪乱膜の運用を確認したので、対策として実弾兵装多めの装備というイメージです。
胸部はパネルを貼って情報量増やしたりしましたが、いい加減スジボリできるようにならないとなと思います。
綺麗に複雑なスジボリが出来る人は本当にすごいなと羨ましく思います。
まずはちゃんとした道具を揃えて、しっかり練習しないとですね。
以上がここ最近コツコツ作っていたガンプラ達です。
各キットの詳細はGUNSTAというガンプラ専門SNSで書いていますので、よろしければ覗いていただけると幸いです。
https://gumpla.jp/author/4039
最近、素組みして艶消しトップコートをしてスミ入れしただけのような「完成品」をフリマアプリで売る、という商法を薦めているwebサイトが見受けられます。
所謂プロが膨大な時間をかけて制作した「作品」と呼べるレベルの物なら、キットの原価よりも多くのお金を出して買うのはまだ理解できます。
しかし、小遣い稼ぎ目当ての付け焼刃の素人が組んだガンプラなんてただのジャンク品だと思ってしまうのですが、実際付加価値が付いて需要と供給が成り立ってしまうのですから世の中分かりませんね(苦笑)
キットを買ってきて、自分で組み立てる事も含めてプラモデルの楽しみだと思うのですが。
ただ、転売や「完成品ビジネス」の為に品薄となったり、ガンプラ売場でスマホを見ていると問答無用で価格相場を調べている転売ヤーに見なされる事故があったりと、純粋なファンの活動が阻害されていると思うと残念な気持ちにはなります。
お読みいただきありがとうございました。
PGザクⅡ改造 旧ザク

がっつりリアルタイム世代のクセに、今まで全く触れて来なかったエヴァンゲリオンを今更になって見始めました。

スパロボで出てきた要素(シンクロ率、ケーブルで動力供給、ATフィールド、暴走等)と、TV放映版最終話のラストで皆が拍手しているシーンを何かでたまたま見て「なんじゃこりゃ」と思った程度の予備知識でNETFLIXでTV放映版を見始めました。
とりあえずTV版は全話観終わりましたが、確かに伝説的なアニメだけあって面白かったです。
大学生の時にリアルタイムで新劇場版あたりから入っていたら、もっと熱量ある感じでハマったんだろうなあと思います。
現状TV放映版のみ観終わった段階なので、まだ「え、結局人類補完計画って具体的に何なの?碇ゲンドウは何がしたかったの??」的な疑問符だらけの状態で、ある意味今が一番楽しい時なのかもしれませんね。
これから旧劇場版、新劇場版を観進めて、じっくりエヴァ世界を探求してみようと思います。
思春期の頃は天邪鬼な性格ゆえ「流行りものアレルギー」というか、流行っている物を貶すのがカッコイイと思っている節がありました
(まあ今も抜け切れていませんが(笑))
鬼滅の刃も超超遅ればせながら今読んでいますが、面白いですね。
この歳になってようやく「世間で流行っている物は一定の確かなクオリティがあるんだろうな。いちいち屁理屈こねて食わず嫌いしてたら勿体ないのかもな。」とちょっと思えるようになってきました。
歳を重ねて余計な角が取れて丸くなるのも、まあいいもんだなと思います。
ただ、尖るところはしっかり尖り続けていたいなとも思いますが。
では、本題に入ります。
PGザクⅡを改造して旧ザクにしました。


PGザクⅡは1999年発売の1/60キットです。
定価12000円で「パーフェクトグレード」の名に恥じない、当時としては最新技術がぎっしり盛り込まれた最上級キットでした。



私が小学生の頃発売されましたが、プラモに1万円強も出せる財力は当然無く、模型屋やおもちゃ売り場で巨大な緑一色のパッケージを見つめては「いつか必ず」と思い続け、結局三十路も半ばになって中国の地で遂に手にしました。
ウキウキしながら箱を開けた瞬間、「なんか普通に組んでもな。。」という思いが突然頭をよぎり、その勢いのまま旧ザクに改造してしまいました。
旧ザクがあってザクⅡが生まれた、という経緯を意識しつつ各部形状変更しました。

古いキットだけあって目立つバリやヒケも多かったですが、どっしりとしたスタイルは今見ても非常にカッコイイと思います。
ショルダーアーマーの前後分割やマシンガンの左右分割等、多くのキットによくある合わせ目に加え、このキットは外装が取り外し可能というウリの為にスネや頭部、前腕が「ザ・モナカ構造」で、下図の赤丸部のように大量に堂々とした分割線が主張してきます。


20年以上前のキットとはいえ、あまりにも気遣いの無いおもちゃ然とした分割ばかりなので、ほぼ全箇所取り外し機構をオミットして合わせ目消しました。
内部は非常に緻密でリアルなメカっぽい演出なのに、装甲の構成はてんで破綻しまくってるというのがなんともアンバランスというか、片手落ちな印象はあります。
普通では許されないようなあからさまな分割線も、PGザクは「装甲が外せる!」という機構を免罪符に見て見ぬ振りをされるきらいがあると思います。
ですが、私にとって少年期に買いたくても買えなかった憧れのPGザクなので、妥協せず消しました。
基本は後ハメ加工化、無理な所は塗装前に組んでマスキングして対応しました。
主な加工箇所は下記です。
・頭部
パイプ除去
センターステー、トサカ追加
合わせ目消し
・胴体
胸部パネル形状変更
腹部バックル形状変更
胸部パネル開閉機構オミット
・腕部
左肩アーマースパイク除去
右肩シールド接続部埋め
二の腕外装合わせ目消し
前腕装甲合わせ目
・脚部
後ハメ加工し、スネとふくらはぎ装甲を一体化
モモ装甲合わせ目消し
ふくらはぎバーニア部埋め
スネ部モールド埋め
ザクⅡ→旧ザクは基本引き算のみなので、改造としては簡単な部類だと思います。
塗装~ウェザリングのレシピは以前制作したMG旧ザクと同じです。
頭部はまず左右を貼り合わせクチバシのパイプ接続部を除去し、エポキシパテとラッカーパテで埋めました。



後頭部はパイプ接続基部が無くなるのでプラ板で塞ぎパテを持って成形し、そこにプラ板を切り出したトサカを接着しました。
センターステーはプラ板を切り出してつくりました。
最後に下側をくり抜き、メカ部を被せられるように後ハメ加工しました。
モノがデカいので、頭が出来上がった時点で1/144キット1個作ったくらいの達成感がありました(笑)
エポパテとプラ板工作はもっと技術を磨いていきたいです。
この2つを使いこなせれば、基本どんな形も立体化できるようになりますからね。
胸部はザクⅡの物を削って形状を変えました。

大改造すると失敗が怖い、手間が掛かる、苦労に見合った仕上がりになる自信が無かったのでなるべく簡単に済ませました。
ザクⅡとの繋がり的に大きく形状変えちゃうとな...と自己暗示を掛け、余計な色気は出さずシンプル工作で終わらせました。
ザクⅠの運用評価をフィードバックし、ザクⅡの胸部パネルはコクピット開口方式を改めてコストダウン&対弾性UPした、という脳内設定です。
腹部バックルはパイプ接続部を埋め、エポキシパテを盛ってそれっぽい形状に成形しました。
ここが今回の改造で唯一、大きめな足し算が必要な部分だったので一番悩みましたが、結果としては大幅な形状変更やディテール追加はせず、元のザクⅡのパーツをベースに少し切った貼ったで留めました。
二の腕は後ハメ加工し、外装を一体化し合わせ目を消しました。

肩と前腕は後ハメ出来なかったので組んで合わせ目消し→マスキングして塗装しました。
スケールが大きいのでマスキングは結構楽でした。
右肩はシールド装着基部を省略し、空いた装甲をプラ板で埋めています。

階級章もうちょっと大きいのを貼りたかったのですが、1/60に合うビッグサイズの持ち合わせがありませんでした。
前腕と肩装甲の分割線はキットのままだとあまりにも格好悪いので、何が何でも消す覚悟で挑みました。
脚部もスネと後ろ側のフレア部、ふくらはぎ装甲の分割線が絶対許せなかったので、頑張って後ハメ加工して全て消しました。

特にふくらはぎ装甲とスネ左右のハッチモールドの位置関係はひどいです。

このスネの四角いモールドは実際はパネルのはずですから、横の部分は肉が無さ過ぎで構造破綻してますよね(苦笑)
どう見ても強度足りないと思います。
後ハメは干渉する所をとにかく切除さえすれば、位置決めも自然と出来たので思ったより苦労しませんでした。
ふくらはぎのバーニアはよく作り込まれているので残しても良かったのですが、旧ザクには無いイメージなので埋めました。
モモは左右分割だけ一体化し、ちょこっと内側を切除すれば後ハメできました。
基本工作はゲート処理した程度で、ヒケ埋めや面出しはしませんでしたが、艶消し塗装してウェザリングすればほぼほぼ目立たなくなりました。


ツヤありで仕上げたいとなると、そのままではグネグネに歪みまくった仕上がりになると思います。
武装は120mmとヒートホークしか付いていません。


バズーカやフットミサイル、シュツルムファウストはクリア外装パーツとセットの「カスタムセット」なる別キットを買わなければいけません。
しかもカスタムセットは1と2に分かれており、武器も2セットに振り分けられています。



1セット当たりがMG並の価格なので、お財布に優しくない仕様です。
せめて全クリア外装をセット1、全武装をセット2にしてくれればと思うのですが、それは売る側も分かって敢えてこのセット分けにしているのでしょう。
バズーカを持たせてあげたいですが、そのためにMG1体分のお金を出すのに躊躇しています。
子供時代、お年玉等の機会に何度も買いたい候補には入りましたが、プレステソフト約2本分のプラモはコスパが悪く結局買わずじまいでした。
そんな憧れのキットでしたので、通販で届いて緑一色の外箱を抱えた瞬間はめちゃくちゃテンション上がりました。
時代なりの組みにくさはあり、そのスケールからどの部品も単純作業の量が多すぎ途中飽きて作業ペースが落ちたりもしましたが、完成した時の達成感はひとしおで迫力抜群な佇まいには惚れ惚れします。
まだまだ足りない部分も多くありますが、制作を通して良い経験になりましたし、自分だけの旧ザクを手に入れられたので総合的には満足です。
お読みいただきありがとうございました。