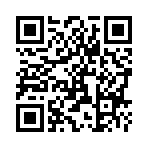スポンサーサイト
パスファインダー騒動

先週土曜日に発売されたNew Balanceの5年ぶりのM1300復刻版(M1300JP3)ですが、見事に抽選外れました。

発売日の朝から、早速国内オークションにずらっと転売商品が並んでいますね。
定価4万弱に対し、サイズによっては8万程度で落札されています。
ネットで10分程度手続きすれば抽選完了し、当たればほぼ確実に3~4万円儲けられ、売れるのが数年後だろうと原価割れして損する可能性はゼロという、転売物件としてはかなり優良商品でしょうね。
5年に1回ですし、定価1万ちょいプラスの5万円程度なら転売屋から買ってもいいかなと思っていたのですが、考えが甘過ぎました(苦笑)
まだ発売して1週間も経っていないので、落ち着いたらもう少し相場は下がるかもしれませんが。
まあ4万円のスニーカーを履いていたら、道の泥とか水たまりとかに常に気を付けなければいけないし、汚れたり傷つけてしまった際の精神的ダメージは計り知れないわけで、いくら「雲の上を歩いているような履き心地」だとしても、貧乏人が履いたら街を歩くだけで際限なくストレスが溜まるから逆に買えなくてよかった!と自分に言い聞かせています。
振り上げた拳(お金)のおろす先と言ってはなんですが、慰めに限定版ではないM1300の復刻版を購入しました。

M1300CLという、数量限定ではないですが限定的な展開(流通店舗が限られる)がされているモデルです。
5年に一度のM1300JPが「完全復刻」を謳っているモデルで、M1300CLは「オリジナルのフォルムを継承しつつ、現代技術を取り入れアップデートする」モデルのようです。
JPに比べると安いとはいえ、スニーカーのくせに税込みで3万円オーバーする中々の重鎮です。
今回、新古品でかなり安く手に入れることができました。
New Balanceの上位モデルは公式でソールや履き口の修理が可能な上、M1300CLであればボロくなったら比較的容易に買い替えも可能なので、5年後か10年後か、いつの日かJPが手に入るまで永く付き合っていきたいと思います。
ちなみにM1300CLも来月日本で再販されるようですね。
公式サイト特設ページ:https://shop.newbalance.jp/shop/e/eEnb-m1300cl
たぶん今日から先行予約開始だったはずですが、公式サイトでは既にかなりのサイズが売り切れになっていました。
CLの方もどんどん人気になって、いずれJP同様入手困難アイテムになってしまうのでしょうか。。
それでは本題に入ります。
前回に引き続き、ニッチなCASIOの時計ネタです。
ちょっと調べたい事があり、久々にアメリカのアウトドア雑誌(BACKPACKER)のバックナンバーをしらみつぶしに読み漁っていたところ、目当てのモノ以外で発見がありました。
1998年10月号に、トップ画像にもした下記広告が出ていました。

CASIOの腕時計です。
「ふーん、CASIOも宣伝してたんだ」程度に思い、とりあえず後でモデル考察できるよう画像だけキャプチャしようとふと見ると、「PATHFINDER」と書いてあります。

「ああ、そういえば北米向けのブランドにPATHFINDERってのがあるって、どこかで聞いた事があったな」と思い出し、何気なくebayで「PATHFINDER」で商品検索してみました。
すると、下記写真が出てきたのです。

機種名は「PAG-40」とあります。
これは日本ではPRO TREKブランドで「PRG-40」として売られていた物に違いないでしょう。

このモデルに関しては過去、初期アフドキュメンタリー番組「Profiles From The Front Line」に出てくる隊員が着用していると考察しました。


過去記事:「初期アフガンお宝映像考察 PART3」
このPAG-40を見つけた事によって、私にとって不都合な真実を知ってしまいました。
私は以前、初期アフ装備用にPRG-40を入手し、サバゲに限らず普段使いでもたまに着用している程のお気に入りの時計です。

しかし今回の発見で、米軍装備としてはPRG-40ではなく、正確にはPAG-40を着用しなければいけないという結論が導かれてしまいました。
しかもPRG-40とPAG-40の外観に大きな相違点があったならば、これは一大事です。
慌てて両者の外観を比較しました。
私が把握できた、すぐにわかる相違点は3点です。
1.バンドに書いてあるブランド名印刷


2.遊環のブランド名印刷


3.裏側の樹脂カバーのブランド刻印


モジュール番号はPRGが「2272」、PAGが「2271」で違いますね。
調べてみると、モジュールの中身は単位をフィートや華氏等、向こうで一般的に用いられる単位に切り替えできる違いがあるようです。
困った時のwikipediaに載ってました。
URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/PRO_TREK
裏側はまあ着用すれば見えないから妥協できるとしても、バンドの2箇所の印刷は個人的にはかなり気になります...。
こうなったらPAG-40を買い直すかと思いましたが、死ぬほどボロボロのクセに結構なお値段のものばかりです。


「よくこんな状態の時計を人に売ろうとするよな」と思います(苦笑)
比較的安い不動品を入手し、部品取りだけで考えても二の足を踏んでしまう費用対効果です。
前回記事にしたばかりですが、この機種もバンドはウレタンなので劣化している可能性も高そうですし。。
「この事実を知ってしまったからには、もうPRG-40は米軍装備で着けられない」と途方に暮れました。
本当に装備趣味は「知らぬが仏」だと思います。
知りさえしなければ、そのまま米軍装備で着用し続けて満足したまま人生を全うできた事でしょう。
知っている方が私のブログを見た時に「あーあ、こいつ米軍装備なのにPATHFINDERじゃなくてPRO TREK着けてるよw」と思われたとしても、直接コメントされなかったり、たとえSNSで陰口を叩かれても目にすることが無ければ、平穏にPRG-40で満足できていたはずです。
しかし私は知ってしまいました。
知ったが最後、手に入れるまで終わらない旅が始まります。
新しい発見をし、新たな事実を知るという事はすなわち成長を意味しますが、同時に新たな苦行の始まりでもありますね(苦笑)
つくづく恐ろしい趣味です。
良い条件の本体が無いのであれば、バンドだけでも無いかと探してみると、なんとヤフオクで気軽に買える状態で出品されていました!


新品のスペアパーツのようです。
PAG-40(PRG-40)のバンドは現役生産モデルのPAG-240(PRG-240)と共用なので、このバンドも比較的新しいものだと想像しました。
最近はebayで出品されている品物を業者がヤフオクで代行出品(というか転売?)しているんですね。
いずれにせよ、購入代行サイトにいちいち登録せず、いつものヤフオクの手順で買えるのでありがたいです。
ebayで直接買う事も今まで何度もしていますが、トラブると面倒な上、今は中国で購入手続きして日本に届けさせるという遠隔操作でイレギュラー対応が難しいので、これはありがたいです。
しかし、同じバンドで印刷が「PRO TREK」の国内正規品の2倍近くしました。
印刷が違うだけで数千円違います。。
これも全ては知ってしまい、見つけてしまった自分がいけないのです。
まさに「進むも地獄、退くも地獄」状態ですね。
ただここで買わずに、無くなった後で死ぬほど後悔するのが一番の地獄なのは痛いほど経験しているので、意を決して即決しました。
次の帰国の楽しみがひとつ増えました。
まだ裏側カバー刻印が「PRO TREK」という課題は残りますが、ひとまず今回の私の中での「パスファインダー騒動」はこれにて一件落着としようと思います。
米軍装備でPRO TREKを着けられる方、ご注意ください。
この記事をここまで読んで「知ってしまった」方は、是非私と同じ苦しみを味わってください(笑)
買った後で気づきましたが、海外仕様バンドはオークションサイトではなく、国内の普通の大手通販サイトで国内仕様と同じくらいの値段で売られていたりしますので、気になる方は是非探してみてください。
私は焦って買い物して見事に損しました(笑)
お読みいただきありがとうございました。
G-SHOCKのメンテナンス

先月帰国した際に、東京の家からG-SHOCKを1つこちらに持ってきました。

15年くらい前に買ったDW-5600Eです。

学生時代、富士山に登る事になった際にタフな時計をしていこうと思って買いました。
選んだ理由は5600の形がカッコイイと思い、たしかAmazonで一番安かったからだったと思います。
逆輸入品だったらしく、防水表記は海外仕様の「M」表記です。

ご存知の方も多いと思いますが、G-SHOCKは国内向けは「BAR」表記、海外向けは「M」表記で分かれているものがあります。
国内向け

機種によっては向け地に関わらず全て「BAR」の物があったりもしますが。
ちなみに「FOXFIRE」も確か日本仕様のみにしかない表記で、ELバックライト機能付を意味しています。
豆知識ですが、製品タグ等に書いてある製品名の末尾に「JF」か「JR」が付いている物が日本向け正規品になります(FとRは梱包に関する仕様表記)。

「V」や「ER」「DR」などが付いているものは海外向けで、記号によって向け地が異なります。
「J」はJapan、「E」は確かEurope、「D」はCASIOが販社を介さず直接流通させている地域向けで「Direct」の意味だったと思います。
「V」はたしか防水表記が「M」を指す=海外向けという認識です。
ただ、この命名ルールが出来る前の製品については特に何も記載が無かったりして、すべてのモデルが必ずしも上記の通りではないようです(特に古いモデル)。
皆大好きDW-6900-1Vは「V」付きしか展開されていません。
つまり海外専用モデルということになります。

こういうモデルは逆輸入品を買うしかありません。
まだカタログ落ちしていませんが、海外専用なので日本のG-SHOCKのサイトでは調べても出てきません。
ちなみに絶版の旧モジュール品で今度は中国製の個体(以前は韓国製)を発見したので、またDW-6900-1Vを買ってしまいました(3本目)。
今日本の実家にあるので、いつか帰国出来たら記事にしようと思います。
Amazon等ではよくJF、JR以外の仕様も売っているのを見かけます。
これらが逆輸入品です。
逆輸入品も基本的な性能や仕様は同じですが、最初に書いたように防水表記が違ったり、梱包箱が違ったり、あと一番大きいのは保証書が異なる(保証内容が異なる)ことです。
説明書も日本語が無かったりします(よく販売店のサービスで日本語説明書をコピーした紙が付いていたりしますが)。
また、海外向けの安いG-SHOCKは下写真のようなボール紙の外箱の中に缶に入れられている場合がほとんどです。

何度か逆輸入G-SHOCKを買った事がありますが、十中八九外箱はボロボロです(苦笑)
豆知識はこのくらいにして、話を進めます。
当時は特に何も考えていませんでしたが、本格的に2000年代グリーンベレー装備を集めている今となっては海外仕様の「M」表記で大正解でした。
昔の自分を褒めてあげたいです(笑)
現在も普通にメーカー生産されていてプレミアのプの字も付かず、相変わらず数千円で買える「安物時計」ですが、私にとっては自分のお金で初めて買った思い出のG-SHOCKです。
富士山登頂後も日常使いで使い倒したので、外装はかなり年季が入っています。


ただ、幸いベタツキは無く、装着したり多少引っ張ったりしても割れたり千切れたりしませんでしたので、まだ十分実用可能です。
今では2本の腕では有り余る数の腕時計が家にあるので(多分30本以上)、このDW-5600Eは時計入れの奥底に永い間眠っていました。
この間初期アフミリフォトを考察した際に久方ぶりに引っ張り出して来たので、いい機会なのでちょっとメンテしようと思いました。
基本的にG-SHOCKの外装の大部分はウレタン樹脂で出来ています(ケース部は基本金属がインサートされたエンプラです)。
ウレタン樹脂は水分や熱、紫外線、皮脂汚れ等によって劣化します。
着用時間が長い個体は皮脂汚れが激しいです。
このDW-5600Eも、思い返してみるとおそらく一度も清掃していなかったです。
G-SHOCKはこの界隈で使用している方も多いと思いますので、せっかくなのでメンテ過程を写真を撮りながら記事にしました。
G-SHOCKは20気圧防水なので、手洗い石鹸や中性洗剤と冷水やぬるま湯で丸洗いしても問題ありません(お湯は推奨されていません)。
私は下写真のGMW-B5000TFC-1をほぼ毎日着用していますが、1ヵ月に1回くらい、気が向いた時に手を洗うついでに手洗い石鹸を付け手で擦って丸洗いしています。

このモデルはG-SHOCKでは数少ないフルメタルの外装なので劣化は起きづらいですが、隙間や隅部等(ボタンの隙間等)は汚れが長期間溜まるとステンレスといえど錆びるので、頑固な汚れになる前にマメに落とすようにしています。
また、このモデルの表面処理であるDLC処理(ダイヤモンドライクカーボン)は、皮脂が付着すると指紋の痕等が良く見えて目立つので気になるのもあります。
ただ、構造上ベゼルとセンターの間やバンドの穴部に水が溜まりやすいので、洗ったあとはしっかり水気を払うようにしてよく乾燥させています。
後で詳しく書いていますが、通常のG-SHOCKもバンドと本体を繋げている「ばね棒」という部品はステンレス製で、水や汚れが溜まりやすく錆びやすい箇所です。

丸洗いした場合はこの部分に水が残らないよう、よく振って水気を切ったり、ティッシュの先を尖らせてしっかり拭き取るようにした方が良いと思います。
スケルトンモデルの場合は、ここが錆びると外側から見えるのでみすぼらしくなってしまいますね。

今回の私の個体は買ってからずっと、つまり15年近くノーメンテだったので、しっかり分解して清掃します。
分解の手順を下記に書いていきます。
まずはバンドを外します。
本体裏側のバンドの付け根を操作して外します。
裏側付け根を見ると、先ほど載せた「ばね棒」の先端が露出しています。

ばね棒は読んで字のごとくばねが内蔵された棒です。
中央の筒の中にばねが内臓されており、両端子を突っ張っています。
ばね棒をバンドに通し、端子を圧縮させながらセンターの穴に引っ掛けているという構造になります。

作業は「ばね棒外し」という専用の器具を使います。

先端形状から俗に「豚足」と呼ばれたりもしていますね。

「ばね棒外し」で検索すればネット等で安いもので数百円で購入できます。
先が細く幅の狭いマイナスドライバーでも代用できますが、作業難易度は上がります。
ばね棒外しをばね棒が露出している部分に突っ込み、ばね棒を圧縮しながらバンドをひねるとバンドが外せます。

ばね棒の先端が錆びていますね。

外観から見えない部分に汚れが溜まっています。


砂や埃、ばね棒の錆びや染み込んだ汗の成分等でしょう。
次にバンドの美錠を外します。
美錠もばね棒で固定されています。
ただ、バンドと違いフランジを引っ掛けるのではなく、側面の穴から細い棒で圧縮します。

穴に細い棒を押し込みながら美錠をひねると外せます。
全体的に綺麗なままですが、ばね棒の先端がほんの少し錆びていました。
酷い個体になると、ばね棒は全体が錆びまくっていて固着してしまったりしています。
電動ガンのメカBOX分解時に比べればリスクは相当低いですが、取り付け外しの際にばね棒が吹っ飛んでしまう可能性があります。
眼に当たると危険なのはもちろんですが、物が小さいので紛失するリスクもあります。
ただ、無くしてしまった場合でも数百円でネット等で購入できるので、そこまで不安になる必要はないです。
今回のように錆びてしまった場合は買い替えするのも手ですね。
次にケースからベゼルを外します。
ベゼルを外すには4隅にあるプラスネジを外していきます。

普通に細めのプラスドライバーで外せます。
ここで注意なのは、ねじ穴がプラだということです。
分解組み立て時、特に組み立てる際は斜め入れや締め過ぎに注意しないとすぐねじ山がバカになってしまいます。
4つのねじを外したらあとはベゼルを剥がすだけです。
ここでの注意点は、ベゼルはボタン部の下にも回っている事です。

なので一度ベゼルをボタンから剥がすように引っ張って、ボタンを超えさせてあげる必要があります。
ここに気づかず無理に外そうとするとボタン下の部分が伸ばされて白化したり、最悪千切れてしまいます。
ベゼルもケースも裏側に汚れが溜まっていました。

あらかた分解できました。

本来であればここで終了するのが望ましいです。
銃でいうところのフィールドストリップといった感じでしょうか。
しかし、今回は永らく放置したツケが回って裏蓋周りも錆びが進行していました。

なので、今回は裏蓋も外して状況確認します。
裏蓋を外すのもプラスドライバーで4つのねじを外すのみです。
同じくねじ山はプラなので、作業は慎重に行います。
ねじを外すと裏蓋が外せ、防水Oリングが出てきます。

私の個体は内側まで錆が進行して、Oリングに固着していました。


Oリングも裏蓋も持ち合わせていた道具では錆びは取れなかったので諦めましたが、本来であれば裏蓋は錆取りや研磨で錆びを落とし、Oリングは交換がベストだと思います。
可能な限り汚れを拭き取り、元に戻します。
戻す際はシリコングリスをOリングに塗布し気密を確実に確保することと、裏蓋を閉める際にOリングを噛まない事が注意点です。
Oリングが所定の場所に収まっていないと、防水性が著しく損なわれてしまいます。
異物や埃が挟まっていないかも要チェックです。
本当であれば裏蓋を閉めた後にエアリークチェッカーで気密確認が必要ですが、そんな設備を家庭で持つのはまず不可能ですね。

なのでどんなにちゃんと組付けたつもりでも、確実に気密を確認する術がないです。
DIYで電池交換等で裏蓋を開けた場合、この点が最大のリスクになります(作業的には電池交換自体は簡単ですが)。
修理を請け負っているような時計屋等に持ち込めば、専用の設備で気密確認だけしてもらえるかもしれません。
私の個体は気密面まで錆があるので、おそらく本来の20気圧防水は保てていないと思われます。
まあそんな事は気にせず、他の部品を清掃していきます。
ぬるま湯で濡らした後、中性洗剤を付け、使い古してヘタった歯ブラシでシャカシャカと隅々までブラッシングし洗い流しました。
「かため」のようなコシの強い歯ブラシを使って力を入れて擦ると傷を付けてしまうかもしれませんので注意です。
おそらく完璧に20気圧防水が取れていないケースも丸洗いしましたが、浸水することはなく特に異常は起きませんでした。
一応防水は保ててはいるようです。
ティッシュ等でよく拭き取った後、確認していきます。


隅や溝に溜まっていた汚れはほぼ取れました。
しかし今回は暦年のガンコな汚れの為、バンド裏側の落ちにくい隅っこ等にはまだ汚れが残っています。

このような汚れは爪楊枝で擦って削り、湿らせた綿棒等で拭き取ります。

ついでにばね棒を通す穴の中やケースのネジ穴も爪楊枝で擦っておきます。
爪楊枝は汚れと一緒に水分も吸収してくれるので、穴の中の水気取りも出来て一石二鳥ですね。
確認し終わったらしっかり乾燥させ、逆の手順で組み上げて終了です。


長年の使用によりシボはかなり取れ、テカテカで使用感MAXな感じは変わりませんが、汚れが取れたおかげで「ボロい」というよりは「使い込んでいる」という表現がマッチする印象になりました。
手入れする事で愛着も湧いてきて、末永く大切にしたいという気持ちを強くできます。
「自分のお金で初めて買ったG-SHOCK」という何気に思い出深いG-SHOCKなので、これからも大切にしようと思います。
現在、我が家の安物G-SHOCK達は無造作にスニーカーの空き箱に乾燥剤と一緒にぶち込んであるだけなので、そろそろちゃんとしたケースを用意してあげようと模索しているところです。
サバゲでG-SHOCKを着用されている方も多いと思います。
エアガンや装備をこまめに清掃される方は多いと思いますが、腕時計を清掃する人はそこまでいないのではないかと思います。
腕時計、とりわけG-SHOCKのようなプラ時計は汚れによって劣化が進行しやすいです。
ミリ界隈では、SUUNTOの絶版モデルなんかもよくバンド千切れていますよね。。
永くG-SHOCKを使える状態に保つ為に、年に一回くらい(夏場が終わった後くらいに)上記のようなオーバーホールをしてみてはいかがでしょうか。
分解するのは面倒だという方も、防水時計という事を活かし月1回くらいの丸洗いでも全然寿命は違ってくると思います。
あと、ソーラー充電機種は基本的には日光を浴びせて充電が必要ですが、日光=紫外線でウレタン劣化の要因ですので、ずーっと窓際に置いておくのはやめた方が良いです。
一度満充電すれば、普通に使っていれば1年以上は余裕で持つはずなので、そこまでマメに充電はしなくて大丈夫です。
機種や季節、天候によりますが、夏場の良く晴れた日なら1、2日程度の日光浴で大半の機種はゼロ→満充電になると思います。
最後に、注意事項として下記まとめておきます。
・今回DW-5600やDW-6900等の安い機種はネジ穴がプラなので、雑に分解組み立てするとねじ山がバカになります
・防水面(裏蓋やガラス)はなるべく開けない方が無難です(専用の検査機器が無いと気密再確認できない為)
・あくまで自己責任なので、自信のない方、絶対失敗したくない方はオーバーホールをしてくれるお店等を探した方が良いと思います
・今回のような古くて安い機種は分解も最小限の道具で簡単にできますが、最近の高額機種は非常に複雑で専用の治具が無いと組み立てられないような構造も多く、部品破損や紛失のリスクが高いので、そこも慎重に判断してください
G-SHOCKに限らず腕時計は長時間肌に密着している機械ですので、気が向いた時にちょこちょこ手入れしてあげると清潔ですし長持ちすると思います。
お読みいただきありがとうございました。
Mechanix ORIGINALマイナーチェンジ変遷まとめ

新型コロナウイルス騒動は日々拡大していますね。
私の会社も、中国から移動してきた場合は2週間弱の自宅待機後の出勤許可となりました。
なので、実質日本出張は不可能ということになりました。
逆もまた然りなので、結構仕事に支障が出そうです。
まあこの時期に中国から帰っても周囲からは完全に「エンガチョ」扱いになると思いますが。
そんな中、ネットを駆使して日本のオークションサイトで下記グローブを手に入れました。


Mechanixの旧型ORIGINALです。
どちらも黒のMサイズですが、手首部が異なります。


さらに旧いカタログも手に入れました。

以前何回か記事で書いていますが、複数の記事に分かれていて分かりづらいので、この機会に改めて整理しておこうと思います。
下記、あくまで数あるMechanixグローブの中で「ORIGINAL」のみに言及しています。
特にタグの変遷に関しては、グローブの種類によって異なるようなのでご注意ください。
1999年以降のORIGINALのデザインはどの年代もぱっと見同じですが、2、3年おきくらいのペースで大きくマイナーチェンジされているようです。
特に手首部のデザインは大きく異なります。
手首部以外も細かい部分はマイナーチェンジされているようですが、まだ把握しきれていない&遠目では分からないので、この記事では手首部のみにフォーカスして仕様変遷を考察します。
私の把握している範囲で、時系列に沿ってORIGINALの変遷を辿っていこうと思います。
まずは私の把握している中で最も古いMechanixの資料であるカタログになります。

Mechanix創立は1992年ということが分かりました。

また、裏面に「NASCAR 1996 AWARD SPONSOR」とあります。

全然詳しくないですが、少し調べてみるとNASCARは年間通してレースが行われているようなので、このカタログは1997年以降のものの可能性が高そうです。
後述しますが、1999年のカタログも入手済でラインナップが異なりますので、このカタログは1997~1998年のどこかの物だと思われます。
現在と同じ手の甲に「Mechanix」と並んだグローブは既に存在しています。

ただ、この時点ではまだORIGINALという名称にはなっていないようです。
手首部には何もタグが無いように見えます。
以前考察した初期アフグリーンベレーと思しきミリフォトのMechanixグローブも手首に何もタグがなく、その時は迷宮入りしていました。


もしかしたらこのタグ無しの時期のグローブを着用していたのかもしれませんね。
1997年に市場に出回っていたとしたら、2002年前後で使用されていても不思議ではないですし。
次です。

新品未使用、フルパッケージ品で手に入れたORIGINALです。
カタログまでしっかり同梱されていました。

「1999」とあるので1999年のカタログでしょう。

ということはこのグローブは1999年には存在した仕様だと思われます。
Mechanixは本体に製造年が分かる表記が無いので、カタログの存在は大変ありがたいですね。
今ではもう見かけない「Pit Guy」というキャラクターがちょいちょい出てきて

ちなみに上記のカタログにはいないので、この頃から
主な特徴は手首部のタグと手首を留めるベロです。
タグはこの後の仕様も似たようなデザインがありますが、ロゴのMの字が白地に黒抜きというのがこの仕様の特徴です。

ベロです。モールドの無いツルっとした合皮に文字がプリントされています。

次です。

これも幸運な事に新品パッケージ付きで手に入れました。
カタログも同梱されていました。

2001年のカタログですので、2001年には存在していた仕様と考えられます。
この仕様のタグとベロを見ていきます。
タグは1999年仕様と同じようなデザインですが、ロゴが黄色くなっているのが1999年仕様との大きな違いです。

ベロはモールドが追加され、文字も立体化しました。

ちなみにPit Guyはこの時点ではまだ生存しております。

次です。



冒頭でも書きましたが、先日入手した個体です。
ミリタリーで使いやすい黒、Mサイズで状態も良くしかもかなりお安く入手でき、久々の大ヒットな掘り出し物でした。
残念ながらカタログは付属してないので、カタログから年代特定はできません。
以前google検索の年月日フィルターを駆使して、この仕様は2005年あたりから登場したと考察しました。
以前の記事「Mechanixグローブ年代考察」
タグはロゴの下に「ORIGINAL」のみでシンプルになりました。

ベロは大きくデザイン変更され、ロゴが黄色く着色されています。

時期的に陸特装備で言えば、ACU採用初期の頃の装備と相性ピッタリだと思います。
グリーンベレーで言えば、UCPにCIRAS+SFLCS以外のポーチ装備にこのグローブを嵌めたいですね。
次のサバゲはUCPのODA装備をしたいです。
次です。

これも前述の仕様と同時期に超格安で入手しました。
この仕様も前述仕様同様、google検索で2006年春には存在していた事を突き止めています。
前述の仕様が2005年だとすると、2006年にマイナーチェンジはさすがにスパンが短すぎるような気がします。
あくまで私のネット検索調査した際の印象ですが、こっちの方が信憑性が高そうなので、前述の仕様は2005年より前から存在していたのかもしれません。
2003年頃に登場してくれていると、1997→1999→2003→2006→2009(後述)→2012(後述)→2015(後述)と、ほぼ均一な仕様変更スパンになっていたと想像できます。
タグの特徴は「ORIGINAL」の文字が小さく赤くなったことと、四角いマークの中に手の甲と同じように斜めに「Mechanix」という文字が並びました。

ベロは前仕様とほぼ同じデザインですが、ロゴの隣の携帯電波マークのような三本線も黄色になりました。
(前仕様は三本線のモールドはあるが黒地)

以前考察した2007年のナショジオ製作のドキュメンタリー番組「INSIDE THE GREENBERETS」に出てきた隊員のMechanixは、この仕様かこの一つ前の仕様の可能性が非常に高いです。


ベロの特徴を捉えた瞬間は出てくるのですが、この2仕様を見分けられる3本線の部分がちょうど見えません。。

せっかく実物をどちらも入手できたので、今度気合いを入れて見返して、どちらの仕様か特定したいと思います。
いずれにせよ、2000年代後半の装備でMechanix ORIGINALを嵌めるならこの仕様が鉄板でしょう。
次です。

google検索で2009年終盤に登場しはじめました。
この仕様に関しては、2009年11月に仕様が変わったとして前仕様と比較しているブログ記事を見つけたので、かなり信憑性は高いと思います。


私はこの仕様はまだ持っていません。
買おうと思えばまだまだオークション等で安価で溢れかえっている上に、2010年以降の装備に今あまり興味が無いので後回しになってます。
ただ、油断していると枯渇して泣きを見そうなので、そろそろ入手しておこうと思います。
ここからタグとベロが一体式になりました。
大きな特徴は表面の白い四角い部分で、非常に判別しやすいですね。

ベロは真っ黒になりました。

真っ黒なベロは、今回の記事で紹介した仕様の中で実はこの仕様だけです。
なので、解像度の悪い写真であっても、ベロが真っ黒であればこの仕様の判断材料になるでしょう。
(カラーによっては他にも真っ黒仕様があるかもしれませんが)
次です。

この仕様も私は持っていませんが、同じくgoogle検索では2012年半ばあたりから登場しました。
タグは白い四角が裏側に行き、ベロと繋がる部分が蛇腹状になりました。

ベロは白いマークが特徴になります。

この仕様を最後に、現在まで大きくデザインは変わっていないです。
ただ、この前仲間内でLINEをしていた際に、手の甲の生地のマイナーチェンジが話題に上がりました。
2012年時点の手の甲の生地は横方向に無数の溝が入っています。

2014年2月時点ではまだ同じ生地のようです。

2015年7月時点では格子状に変更されていました。

現行(本日時点の日本公式HP画像)も同じ格子状に見えます。

変更時期はちゃんと調べてないので正確にいつかは分かりませんが、おそらく2015年前半あたりだと思います。
2012年→2015年にマイナーチェンジしていたとなると、2018年あたりにも何かしら変わっているのかもしれませんね。
最近の装備には現在全く興味がないので私には関係ない話ですが、2012年~2015年頃の装備で現行手首仕様のORIGINALを着ける際は注意が必要ですね。
「あれれ?2012~13年の装備だよね?この手の甲の生地オーパーツじゃーん」と、指摘オジサンにヤラれてしまうかもしれませんよ(笑)
Mechanix ORIGINALは安価でどこでも簡単に手に入るので、安易に現行品を装備に取り入れてしまいがちですが、各仕様の外観上の違いは2015年の生地変更以外はそれなりに目立つので、特に2012年より古い装備をする場合は配慮する必要があると思います。
グローブ周りは拘っている方が多そうなので、結構じっくり手元を見られているかもしれませんよ(笑)
今回まででかなりORIGINALの変遷に関してまとめられたと思いますが、調べれば調べる程奥が深いですね。。
まだまだ私の認識していない範囲でマイナーチェンジがあると予想されます。
世界各国の色んな部隊が使用している超メジャーグローブにも係わらず、かなり安く入手しやすいので、これからもコレクションを増やして研究を続け「Mechanix ORIGINALの事なら何でも俺に聞け」くらいにまでなれるのが理想です。
知識を付けるとオークション等での売り買いでも有利ですしね。
話は変わりますが、先日抽選が始まったNew Balance M1300の5年ぶりの復刻版、当たればラッキーと思い宝くじ気分で応募してみました。

もう10年以上New Balanceのスニーカーばかり履き続けているので、そろそろ最高峰を履いてみたいと思った次第です。
NBマニアでも何でも無いので今回の復刻の凄さをそこまで理解できていませんが、縫い目の数に至るまでオリジナルに倣っている
倍率は何倍くらいなんでしょうね?
まあ今回も今のマスクと同様、組織的な転売集団&小遣い目当ての個人が買占めて、発売日当日からオークションサイト等で定価以上の値段で出回るのでしょうね。。
転売の存在によって「運や時間、手間を金に変えて目当てのモノ、コトを手に入れられる」というのは、一つの資本主義の見方として筋は通っているとは個人的には思います(貧乏人なので僻む気持ちは当然ありますが)。
公式にメーカーがシステムとして、例えば今回のM1300で言えばNBが公式に「〇〇足分はオークション形式で販売します」とすればまあ腑に落ちるのですが、自分用に欲しいユーザーと同列に転売目的の人間が混じっているという構造が、なんか個人的には気に食わないです。
うまく言えませんが、「俺は純粋に使いたくて欲しいのに、楽して金儲けを企んでいる連中に邪魔されるなんて!」といった感情ですかね。
ただ、何が何でも欲しくて金に物言わせれば誰でも転売構造の恩恵に与れるわけで、現実その需要があり転売構造が成り立っているわけですから、何でもかんでも「転売屋は悪だ!」の一点張りは主観的過ぎる意見なのかな?と思います。
抽選で当たらなかった時のストレスのぶつけ先としては、転売屋は最高の捌け口ですけどね(笑)
「お前らがいなければ俺が当たってたのに!!」という、根拠のないたられば理論全開で叫びまわる事ができます。
実際、会社の半休を取ってPSVRの抽選に並び見事外れた時は、行き場のない怒りを心の中で転売屋にぶつけた経験があります(笑)
「運を金で買える」と言うとまるでファンタジーの話のようですが、実際構造としてはそうですから、需要が一定数あるのは仕方のない事だと思います。
どんなに熱意があっても、誰よりも一番それが欲しいと自負していても抽選運は誰にも平等です。
その熱意をお金で示せば、己の運すら捻じ曲げられるわけですからね。
「世の中金が全て」とまでは言いませんが、やっぱりお金は大事ですね(苦笑)
マスクのような人命に係わる物を転売構造に引き込む行為は倫理的にどうかと思いますが、スニーカーやおもちゃのような嗜好品であれば、時と場合、程度によりけりではありますが「まあ転売があってもいいっちゃいいんじゃない?」と個人的には思う今日この頃です。
超脱線しましたが、復刻繋がりでMechanixも過去、映画「アメリカン・スナイパー」の撮影時に当時の仕様を映画用に特別に復刻したようです。



参考URL:https://www.mechanix.com/us-en/discover/special-projects-american-sniper
この時は映画用の製作で一般販売は無かったようですが、これが出来るのであれば是非NBやCASIOのG-SHOCKのように復刻モデルを発売して欲しいところです。
2022年あたりに「Mechanix創立30周年記念」としてワンチャンあるかもしれませんね!(笑)
そんな淡い期待を胸に、本記事を締めくくろうと思います。
お読みいただきありがとうございました。
(2020/2/13追記)
やはり2018年後半あたりにもマイナーチェンジがあり、タッチパネル対応になったようです。
詳細調査中ですが、メモ程度に書き残しておきます。
(2020/4/21追記)
・手首ラベルで赤文字で「ORIGINAL」が入っている仕様と2009年登場仕様の間に、「ORIGINAL」が「THE ORIGINAL」になった仕様があるようです。

・本文で2009年仕様登場は2009年終盤と記載しましたが、新たに2009年4月時点のネット情報を発見しました。
・2009年仕様は手首部に加え、生地も伸びやすい物に変わっていたようです。

左が2009年仕様、右がそれ以前の仕様です。
外観上はほぼ変わってないようですね。
今度実際に手に取って確認してみようと思います。
(2020/4/29追記)
下記仕様を新たに確認しました。


四角マークの中に「MECHANIX GEAR」と入っています。
裏側ベロは三本線に黄色が入っています。
この2者の特徴から、白文字ORIGINAL&無地四角マークと赤文字ORIGINAL&斜めMechanix四角マークの間の仕様と思われます。
もしくは模倣品の可能性もゼロではないですね...。
(2020/5/8追記)
2012年以降の仕様だと思いますが、超些細なマイナーチェンジを発見しました。
「THE ORIGINAL」の横についている商標マークに注目です。
上の個体は「TM」、下の個体は「®」が付いています。
TMは商標登録前、®は登録後に付けるもののはずなので、上の個体の方が古いということになりますね。
この両者の裏側です。
下が古い方のはずです。
この「THE ORIGINAL」が商標登録された年月日を調べれば、おのずと切り替わり時期が分かると思い、アメリカの特許商標庁のサイトで検索しました。

詳細検索方法がよく分からなかったので、「THE ORIGINAL」で検索を掛けて出てきた7088件をしらみつぶしに調べましたが、残念ながら見つけられませんでした...。
おそらく探し方が悪かったと思うのですが商標周りは全くの素人なので、今回はひとまずここで断念しました。
またやる気に満ちた時に、商標関係勉強して再挑戦しようと思います。
下記ロゴは2000年7月に商標登録されているのは確認できました。

ちなみに日本の特許庁で検索したところ、日本では下記ロゴが2016年1月に公開されていました。

本気で全分類を整理しようとすると、果てしない泥沼の気がしてきました。。
CONFRONT 参加装備

新型コロナウイルスの影響で日本滞在が1週間延びました。
CONFRONTの前々日に日本帰国したので、まさかの3週間滞在になりました。
昨日ようやく広東省に帰ってきましたが、今週いっぱいは政府から企業の稼働を止められているので人も車もほぼ走っておらず、ゴーストタウン状態です。
羽田→香港経由で大陸に入り、車で住居のある東莞市に移動する際中、市境に防護服を着た人員のいる検問があり体温測定をされましたが、人気のない街に防護服姿の検問というのはさしずめウイルスパニック映画やゾンビ映画を彷彿とさせました。
連休の最初に買った日本土産は全て実家に置いていき、空いたトランクのスペースは全て会社から支給されたマスクをぎゅうぎゅうに詰めてきました。
無事中国に帰って来たはいいものの部屋に籠るしかないので、ブログでも書こうと思います(笑)
前回に引き続き、今月開催された装備ゲーム会「CONFRONT」について書きます。
前回は当日の様子をまとめましたが、今回は自分の装備についてまとめておきます。
前回の記事:「CONFRONT」
一言で言うと、実在する軍隊の装備モチーフの「MILITARY」陣と、架空の設定で装備を極める「FICTION WARRIOR」陣に分かれてのゲーム会でした。

そんなCONFRONTに、私は今回もいつもと変わらずマイペースに初期アフODAモチーフで出陣しました。


ようやく実物になったBALCSをベースに、当時モノのBHIの5.56mm用チェストで拡張しました。
2002年末~2003年初頭の20thSFGと思われる装備をなんとなく頭にイメージして装備を組みました。


最初スピアーフリースを着ようと思ったのですが、今回はドレスコードがあり、MILITARY側は黒っぽい装備はNGだったので断念しました。
それでは詳細を書いていきます。
下記装備品のリストです。
1.SPEAR BALCS SF
2.BHI M4マガジンチェストリグ
3.CAMELBAKハイドレーション
4.OLYMPUS μズーム in TAC-Tグレネードポーチ
5.ICOM IC-F3Sポーチ
6.IC-4008 with F3S変身キット
7.PRC-148 with RACAL URBANヘッドセット
8.BHI DUTY BELT
9.SAFARILAND 6004
10.GERBER ツールポーチ
11.BHI ピストルマガジンポーチ
12.BHI M4レッグマガジンポーチ
13.SPEAR UM21 サイドポケット×2
14.DCU
15.コールドウェザーアンダーシャツ
16.ASOLO FSN95
17.ALTA 二―パッド
18.ノーメックスフライトグローブ
19.SILVA リストコンパス
20.CASIO DW-8700
21.M4
22.M9
めぼしいところを詳細書いていきます。
1.SPEAR BALCS SF
2.BHI M4マガジンチェストリグ
3.CAMELBAKハイドレーション
上記3つをストラップやダクトテープを駆使して一体化して使ってみました。
BALCSは今回からついに実物になりました。
今までは(おそらく)SPECWARCOM製のレプリカでした。

色合いこそ若干違いますが、高品質な生地と実物サイドバックル、頑丈で丁寧な縫製で気に入っていました。
大きさは実物Lサイズと同寸ですが、フロントのパルステープの位置が実物より低い位置にあるのが惜しいところですね。
詳細は先日BALCSのサイズ見分けポイントを記事にしたので、もし気になった方がいらしたら下記よりご覧ください。
過去記事:「初期アフミリフォト考察⑮ BALCSサイズ分析」
BALCS(ELCSも)のレプリカは2000年代前半に色んなメーカーが出していたようで、上記のように完成度の高い物もあれば、パッと見でびっくりするくらい低品質な物もあります。
今でもたまにオークションサイトで出品されたりしていますが、低品質レプを数万円で出品している例もたくさん見かけます。
BALCSはなかなか出てきませんが、痺れを切らして損な買い物をしないようにお気を付けください。
最近出たトイソルレプはお得で買いやすいのですが、結果的に満足できる方は少ないと個人的には思います。
過去レビューしましたので、参考になれば幸いです。
過去記事:「BALCS トイソルジャーレプリカ」
ちなみに私は国内オークションサイトで実物をレプ並の価格で手に入れられました。
待てばチャンスは来るはずですので、辛抱強く待つことが大切ですね。
ただ、一度上がってしまった「装備熱」を抑えるのはそう簡単ではないと思いますが(笑)
インスパイア元は以前手に入れた実物カスタムBALCSです。

合体する事によりまとめて着脱できたり、ズレないので着心地は向上しますが、任務に応じて臨機応変に装備の差し引きが出来なくなります。
今回イメージした2002年~2003年初頭頃の19thや20th SFGの初期アフODAは車両でFOBを出発し、近隣の村をパトロール等していた任務が多そうでしたので、一日の中で「フル装備が必要」「アーマーのみで大丈夫」といったような場面があったのかなと想像しています。
そうなると今回の私のやった合体術はあまり合理的では無いかもしれませんね。
ただ、2002年19thでもBALCSとCAMELBAKを合体していると思われる事例はありますので、隊員個人の好みに依るところが大きかったとは思います。

19thや20thは予備役だからなのか、結構歳いったおじさんが多い印象です。
普通にODAの隊員でアラフィフの隊員もいました。

私はまだ30半ばですが、20代と比べると体力の衰えを感じます。
40代になればもっと如実だと思いますので、必要のない重い装備を着て無駄に体力を消耗するのを避ける為に、アーマーのMOLLEを使わず瞬時に着脱できるチェストリグを併用していた人が多かったのかもしれませんね。
M4マガジンはフルロードで1本約0.5kgのようなので、6本持っていたとして3kgです。
ずーっと3kgをお腹にぶら下げているか、手軽に着脱できるかの差は地味に肩とか腰に効きそうですね。
チェストリグはBHIのもので正式名称は不明ですが、おそらく型番55CP01だと思います。

HOBBY BOXさんのブログで入荷情報記事が上がった10分後に購入完了しました(笑)
タグはこれです。

汚れていてほとんど見えませんが、ちっさい鳥さんはかろうじて確認できます。
恥ずかしながらこのタグがどのあたりの年代なのか分かりません。
ファステックスの製造年も確認できませんでしたが、黒色で裏面にパッド無しなのでオーパーツではないと踏んでいます。
実際の使用例はこのあたりです。


1枚目は2002年8月の3rd SFG隊員のアフガンでの写真です。
2枚目はCQB-Rを持っているので今回私が想定した年代(~2003年初頭)よりは少し先かもしれませんが、それなりに古い時代だと思われます。
このチェストリグのストラップを一旦解き、BALCSの背面MOLLEに通して肩部でダクトテープでぐるぐる巻きにして固定しました。

背中に回す紐は元々欠品だったのですが、実際の隊員も背中には回していないので「無い方が逆にリアルなんだ」と自分に言い訳しています(笑)

ただ、背中に紐を回さないと屈んだ時にポーチ部がお腹から離れて垂れ下がってしまい、非常にサバゲしづらかったです。
私のイメージしている部隊の隊員は、サバゲのようにバリケードからバリケードをダッシュして屈んでという事はしなかったでしょうから不便が無かったんだと思います。
「リアルな装備」と「サバゲしやすい装備」の板挟みは実在装備好きゲーマーあるあるですね。
ちなみにおまけ要素としてスニッカーズをチェストリグのピストルマガジンポーチに仕込みました。
一度中身を食べた後洗浄し、ウレタンを中に仕込んでいるダミーです。
ピストルマガジンポーチが寂しい時におすすめです(笑)
CAMELBAKは何かを買った時におまけで付いてきたと記憶しています。
背面にタグはなく、ストラップにこんな感じであります。

官給品ですね(MOLLE2)。
SDS社製という事なのでしょうか?
一応同年代でおなじような物の使用例は確認しています。

普通に背負っても芸がないので、これもストラップを一度解いてBALCSのバックパネルを抱き込む形で固定しました。
かなりしっかり固定でき、ストラップのわずらわしさを解消できるので実用的なアイデアだと思いました。
4.OLYMPUS μズーム in TAC-Tグレネードポーチ
先日記事にした、下記写真のフィルムカメラ「OLYMPUS μズーム」をTAC Tのグレネードポーチに入れチェストリグのストラップに付けました。
ジャンク扱いでしたが、ちゃんと撮影できました。
なかなか味があっていいです。
日付設定をし忘れていたのが惜しまれます。
フィルムが1000円弱、現像(写真プリント、CD焼き含む)で2000円くらいかかりました。
たった20枚やそこらの枚数で3000円とは、超高いですね...。
ただ、「現像してからのお楽しみ」という感覚はとても懐かしく、撮影時の得も言われぬ緊張感は趣があり楽しかったです。
5.ICOM IC-F3Sポーチ
6.IC-4008 with F3S変身キット
今回も昨年のギアフリ同様特小無線携帯推奨だったので、BALCSの胸部にIC-FS3用ポーチを着け、中にIC-4008を仕込みました。
IC-4008はIC-F3Sに対して小さくアンテナも全然形が違うので、F3Sのアンテナと段ボールで作った「変身キット」を4008とポーチの隙間に詰めます。


受信のみに特化しマイクは非装着、イヤホンは100均で買ったシンプルで線の細い片耳タイプを使用しています。
クリアに聞こえて実用性は十分でした。
一緒に初期アフ装備をしたMUNAGEさんはIC-F3Sが支給された「ソルジャーインターコム」キットに入っていたTELEXのSTINGERヘッドセットを使用していました。
何も加工せずICOMの特小無線で使用可能とのことです。
私もSTINGERは持っていますが、断線してバラバラだったものを形だけ繋ぎ合わせただけなので不動品です。


いつか可動品を手に入れたいところです。
8.BHI DUTY BELT
9.SAFARILAND 6004
10.GERBER ツールポーチ
11.BHI ピストルマガジンポーチ
12.BHI M4レッグマガジンポーチ
13.SPEAR UM21 サイドポケット×2
腰周りです。
DUTY BELTはおそらくオーパーツなので、いいかげん更新しないとですね。
基本的にはもう何度も使いまわしている構成です。
チェストリグだけでは微妙に携行弾数が心配だったので、レッグマガジンポーチを装備しました。
UM21は小さい方は貴重品入れ、大きい方はダンプポーチ運用しました。
UM21サイドポケットは初期アフ装備ではかなり優秀なダンプポーチです。おすすめです。
15.コールドウェザーアンダーシャツ
DCUだけだと寒そうだったので、DCUの下に着込みました。
実際のミリフォトでもDCU下に着こんでいる例はありますね。

今回Sサイズを入手しましたが、丈はかなり今風の短さで、下着1枚(LEP LAYER1)の上から着ましたがほんの少しタイトに感じました。
私の体型的(170cm強、75kg程度)にはMが適切だったようです。
ただ、このシャツは製造年やメーカー?によってサイズ感がかなり違うようですので、現物を見て選ぶのが一番良さそうですね。
ちなみに私の入手した個体のタグは下記です。

このシャツ単体で着まわしている使用例もあり激安ですので、初期アフ装備のバリエーションを増やすのにうってつけだと思います。
私は吉牛一杯並の価格で手に入れられました。
18.M4
基本は今まで使っていたのと全く一緒です。
次世代M4リコイルウエイト抜きLIPO化ハイサイモータ―追加スプリング&ピストン変更です。
グリップはどちらもVFCのスリムグリップ、ストックはマルイの旧型に変えています。
今回の新アイテムとして実物サイドスリングスイベルを装着しました。
ひと昔前は激安で投げ売りされていたイメージですが、いざ探してみると中々見つからず、しかもそれなりにしました。
旧型ストックも15年程前に実物が秋葉原のエチゴヤで1500円程度で売っていたのを覚えています。
大変惜しい事をしましたが、きっと今安く売っていて見向きもしていない物も数年後に「なんであの時買わなかったんだろう。。」と思う物があるんでしょうね。
いつまでも後悔が溢れ続ける恐ろしい趣味ですね(笑)
そろそろM4だけだと飽きてきたので、M16A2あたり一本調達したいところです。
今回は中国から帰国して半日足らずで全ての装備の準備が必要だったので、全体のバランス感を調整する余裕がありませんでした。
写真で客観的に全体を見てみると、ちょっと下半身がゴテゴテし過ぎていてあんまりODAっぽくないなと反省しています。
また、昨年のGEAR FREAKS GAME同様、今回もMUNAGE師匠が初期アフODA合わせをしてくれました。
BALCSの上から(確か)BHIのOMEGAベストを羽織るスタイルです。
BALCS+タクティカルベストの組合わせは初期アフ時代では結構メジャーですね。
得物は次世代M4で、アッパー交換でMk.12 mod.0風に換装していました。
アーマーにベストを羽織るスタイルは思いの外動きづらいらしく、途中でベストを脱ぎ捨てマガジンはパンツに突っ込むという、これまた現場感MAXなスタイルでゲームに臨んでいました。
私も今度アーマー+ベスト装備を試してみたいと思います。
盟友Bucket Head氏は古めのデルタモチーフでした。
またもや元ネタを忠実に再現していました。

彼のRAV姿はかなり久しぶりに見た気がします。
今回はグローインプロテクターまで付けたフル装備でしかも実物ソフトアーマー入りだったので、相当バテていました。
これに実弾詰めて命のやり取りをする本職の方々は本当に凄まじいですね。
久々のサバゲでしたが、天候にも恵まれ素晴らしいイベントのおかげで、大変楽しむことができました。
この後日山梨でキャンプも予定していたのですが、大雪が直撃したため断念し、急遽普通の温泉旅行になってしまいました(苦笑)
家族ともゆっくり過ごせ、大変リフレッシュできた春節休暇となりました。
リフレッシュし過ぎて仕事を忘れかけてますが、週明けから新型肺炎に気を付けて頑張っていこうと思います。
お読みいただきありがとうございました。