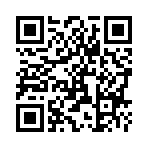スポンサーサイト
初期アフリストコンパス問題 解決編
過去2回記事にした「初期アフリストコンパス問題」について、非常に大きな進展がありましたので続編を書きます。
「初期アフ リストコンパス問題」
「初期アフリストコンパス 加工編」
今回が「解決編」と言える内容になります。
まずは今までの経緯を簡単におさらいしていきます。
下記写真達は所謂「初期アフといえば」の代名詞的なミリフォトと言っても過言ではないと思います。



19th SFG ODA961の2002年時の写真という認識です。
この中で一際異彩な存在感を放つヒゲもじゃの隊員、通称「cowboy」氏の変なリストコンパスが何か?疑問を持ち調べました。



そこでGoogle先生に対し「りすとこんぱす」と問いかけて出された無数の画像をしらみつぶしに見ていくという、情報弱者の悲しいまでの肉弾真っ向勝負で挑んだ末、奇跡的に下記画像を発見しました。

しかし画像を見つけたまではいいものの、各種通販、オークションサイトを血眼になって探し回っても見つからず、すぐに痺れを切らし「自作」という暴挙に出ました。
SUUNTOのM9コンパス(新型)をバラして文字板の色を塗り替えて組みなおし、「SUUNTO M9 Silva-ish」なるものを作り上げました。
コレでひとまず溜飲を下げて、使っているうちになんだかんだ愛着も湧いてきて平穏な日々を過ごしていた、というのが今回に至るまでの経緯です。
そんな平和に暮らしていたある日、インスタで仲良くさせていただいているtom69beardさんから「あのコンパス、出てますよ!」とのご連絡をいただき早速チェックすると、そこにはなんと新品未開封のあのコンパスの姿がありました。

商品説明や他の出品物等の情報と、こんなレア物今の日本に2個とないだろうと考え、出品者はナイロンが気になっているお年頃のあの方に違いないと思い連絡を取ってみると、見事的中でした。
リコさんは過去の私の考察記事をきっかけにこのコンパスを調査され、見事2個調達されたそうです。
そして今回、その内の1個を放出されたというわけですね。
無論当時私も記事をアップする前にあらゆる場所を探しましたが、私の調査能力では見つけられませんでしたので、
もし私がブログで考察記事を書いていなければリコさんも入手されることはなく、そうなると今私の手元にあることは叶っていなかったということになります。
コツコツとニッチなブログをやっていて本当に良かったと思いました(笑)
このように思うところもあり、「絶対に負けられない戦い」と自分と財布を奮い立たせ決戦に臨みました。
大激戦を予想していましたが、蓋を開けてみると入札したのは私の他に1名のみでした。
しかもその方は私のブログにコメントしてくださっているTEGUさんでした。
世の中狭いですね(笑)
まあこの界隈では結構あるあるだったりしますよね。
競らずに私にチャンスを下さったtomさん、そしてなにより今回貴重な品物をお譲りくださったリコさん、ありがとうございました!
おかげさまで思いの外早く私の「初期アフドリーム」のひとつが叶いました。
ただ、お宝過ぎてゲームで着けるのがはばかります。
直近ヴァイブス師匠のM9コンパスが被弾して割れたという事故もあったようで、それがこのSILVA君に起こったらと思うととてもじゃありません。
なので、ここぞという時以外は自作の方を着けようと思います。
着ける為に買ったくせに、破損が怖くて着けられないという大いなるジレンマに頭を抱えています(苦笑)
前置きが長くなりましたが、そろそろ物を見ていきましょう。
泣く子も黙る新品未開封品です。
私は涙を流しながらも、しかし躊躇無く開封しました。
パッケージの型紙を貼り合わせている糊が完全に風化していたおかげで、無理に破ったりせずに開けられました。
このパッケージも超大事な資料なので、宝箱に保管です。
全体的なレビューは既にリコさんがしてくれていますので、私は細かーい所を書いていきます。
気になったのはやはりSUUNTO M9との関係性です。

そっくりですよね。
そっくりを通り越してもしや全く同じなんじゃないかと思い、色々観察してみました。
まず一番最初に目についたのは、側面に縦に入った傷です。
SILVA

SUUNTO M9

赤丸の部分に全く同じ形状で入っています。
成形金型から離型する際についたものだと思います。
パッと見でこの面は抜き勾配も全然取ってなさそうですし。
おそらく意図したもの(加飾や機能上のデザインで、図面に描くような形状)ではないはずなので、金型が別なら全く同じにはならないはずです。
ちなみにパーティングラインの上にあるので、この傷が入っている部分はキャビティ側の金型だと思われます。
次です。
足の裏にある「FINLAND」刻印部を見てみました。
SILVA
SUUNTO M9

歪んでいて汚いですね。
この歪みの形状も全く一緒です。赤丸した部分が分かり易いと思います。
こちらは先ほどとは逆にパーティングラインの下にあるので、コア側の金型になります。
以上より、金型は上下どちらもSILVAコンパスとSUUNTO M9で全く同じ物が使われている可能性がかなり高そうです。
ちなみにフロントにある「Silva」刻印については金型を追加工したと推測します。
この部分は「Silva」の文字部が凹んでいて、そこにゴールドの塗料が色埋めされています。
製品が凹ということは、金型はその逆で凸になっています。
金型は肉を盛るのは難しいですが削るのは比較的容易ですので、SUUNTO M9に転用する際に金型の刻印部を削り落とし、シボを打ち直したのだと思われます。
ちなみに上記の金型由来と思われる特徴は新型M9(大体2015年~)でも確認できました。

つまり現在まで金型は更新せず、ずーっと同じものが使われている可能性が高いです。
材質は何かは分かりませんが、金型消耗が激しそうな材料(グラスファイバー入り等)ではなさそうですし、公差もかなり甘いと思うので、一部スライドが必要そうな形状ではありますがそこまで複雑でもなさそうなので、平気で数十万ショットは持つのではないでしょうか。
仮に30万ショット以上持つと仮定して、このコンパスの発売が20年前だと仮定すると、MAXで年間約1.5万本以上は生産されている計算になりますね。
リストコンパスは需要が限定されると思われる商品ですし、デジタルガジェットの台頭で年々売り上げ本数も下がっていると思うのでいい線かな?と思います。
wikipediaによると設立から約60年で累計2500万個のコンパスを作ったようなので、そのあたりの桁数を考えても、1機種、しかも需要の少なそうな機種の生産数としては見当外れな数字ではないとは思います。
そう考えるとSILVAの時代から今まで金型を更新せず、今日までずーっと使っていると考えても自然かなと思いました。
次に注目したのは風防が嵌まる箇所のバリです。
SILVA
M9
大きさは若干違いますが(SUUNTOは中古だから使用で削れた可能性もあり)、全く同じ場所、傾向のバリの出方をしています。
バリは金型同士の隙間に樹脂が入り込んで、「たい焼きの羽」のようにハミ出ている現象です。
たい焼きだと嬉しいですが、プラモやトイガンだと目の敵にされる部分ですね。
バリは金型要因もありますが、成形条件(射出圧や射出速度、樹脂温度、保圧力や時間、型閉め力やペレットの水分量等の管理)も大きく影響するはずです。
そこまで詳しくないので断言はできませんが、バリの出方が全く同じということは、両者は金型のみならず成形条件も同じなのではないかな?と推測しました。
あまり自信ないですが、たとえ成形条件を全く同じにしても、違う場所、違う成形機、違う作業者でやったらここまで同じバリの吹き方はしないのではないかな?と個人的には考えています。
そして更なる考察材料として、足裏の「FINLAND」刻印です。
この辺の表記の法律はあまり詳しく無いですが、きっとフィンランド国内で部品製造、組立されて出荷されているのだと思います。
そしてSILVAはスウェーデンのメーカーで、SUUNTOがフィンランドの会社です。
両社の工場が何処にあるかは不明なので不明瞭ではありますが、上記現物の形状踏まえた私の推論としては、
「SILVAがSUUNTOにOEM or ODM生産させていたリストコンパスの商品権利を、何らかの事情でSUUNTOに譲渡し、SUUNTOは刻印を削り落し製品名を変えたのみで同じ場所で同じように作って売り続けている」あたりの考え方が自然なのかなと導き出しました。
いずれにせよ、ケース部品は全く同じ金型が用いられている可能性は高いと思います。
そしてSILVAとSUUNTO M9はフロントのロゴ刻印の有無が異なりますので、どこかのタイミングで金型に不可逆な加工をした(刻印を削り落とした)と考えられます。
つまり、SILVAとSUUNTO M9は同時期に生産されていた可能性は低く、SILVAが廃版になりSUUNTO M9にスライドした可能性が濃厚だと思います。
そしてその「変わったタイミング」ですが、下記ミリフォトのように2001年時点で既にSUUNTO M9が米軍特殊部隊の腕に巻かれている認識です。

なので、SILVAとSUUNTO M9が切り替わった時期は2001年よりも前ではありそうだという所までとりあえず突き詰めました。
今回はここまでとします。
一回で書き上げるつもりでしたが、手に入れたのが嬉しすぎて死ぬほど細かい話で長くなってしまいました(苦笑)
かなり貴重なアイテムだと思うので、せっかく手にさせてもらったからには詳しく考察して記事にまとめて、同志の皆様に広めなくてはという義勇感もあります。
リコさんはじめ、今回このコンパスを見送ってくれた方が「ああ、この変態に譲っといて正解だったな」と少しでも思ってもらえるよう頑張って深く掘り下げてみました。
まだまだパッケージや説明書から分かった事とかも色々書きたいので、「解決編PART2」に続きます(笑)
まだ記事構想段階ですが、コンパスの話なのに我々に身近なある台所用品の話も出てきたりして、またまたディープめな話になりそうな予感です。
次回も今回に引き続き「初期アフを深堀りし過ぎて初期アフ要素ほぼゼロになっちゃった記事」という、ニッチ・オブ・ニッチな誰得な記事になりそうですが、よろしければお付き合いください。
お読みいただきありがとうございました。
ナショジオODA装備 in サバゲーバイキング

先日参加したサバゲーバイキング時の装備をまとめておきます。
1ヶ月近く前に注文した「INSIDE THE GREENBERETS」DVDがようやく到着しました。

ご存知の方も多いと思いますが、ナショナルジオグラフィックが2007年に放映したアフガンODA密着ドキュメンタリー番組です。



後日詳細考察していこうと思います。
今回はこの番組に出てくる隊員達をイメージソースとして、盟友Bucket Head氏と揃って「ナショジオODA」装備をしました。
背景も雰囲気があってテンションが上がり、色々寸劇チックな写真を撮影してみました。
あのポーズを真似るヒゲ
地図を確認するヒゲたち
村人への贈り物を持ってくるヒゲ
中身を確認するヒゲ
双眼鏡で遠くを見るヒゲ
実は手で「丸」を作って覗いてるだけです(笑)
先日のイベントでFIRE BALLさんから伝授してもらったそうです。
素晴らしい「ゼロ円DIY」ですね!
あとトップ画にもしましたが、番組中のインタビュー風にテロップを加工してみました。


アスペクト比もちょっと拘って番組と同じ(?)16:9にしてみました。
今回加工して感じましたが、アスペクト比って雰囲気に大きく関わってくるんですね。
ミリフォトっぽくしたい時などは、このあたりもしっかり考えてみようと思いました。
きっとそのうち画角も気になってきたりして、こうやってカメラ沼に嵌っていくんでしょうか...。
今のところはコンデジとスマホで満足できていますが。
そんなテンションの上がったナショジオODA装備を以下にまとめておきます。
車両移動で邪魔にならないよう、腰足周りに何も着けていないところがポイントになります。
背中にチャージポーチは付けていますが、中身は敢えてほぼすっからかんです。
アンテナも車の乗降車で邪魔にならなさそうなイメージでコンパクトに仕込みました。
今回は映像で見られるかなり具体的なイメージソースがあったので、あまり悩むことなく装備がまとまりました。
下記レシピです。
・CIRAS MAR
・MICH2000
・MSA SORDIN
・OAKLEY FACTORY PILOT GLOVES
・OAKLEY SI M FRAME2.0
・ASOLO FSN95 GTX
・ACU(UCP)
・GARMIN Foretrex101
・SUUNTO M9 COMPASS
・CASIO PROTREK PRG-40
・M4
・M9
・シュマグ
・ヒゲ(GEN6)
順に詳細を書いていきます。
CIRAS MAR
2005年製のKH、Mサイズです。
構成は下記になります。
SFLCS SAW 200RDポーチ
SFLCS 9mmピストルマガジンポーチ(2本用)
SFLCS チャージポーチ
TAC-T MAVユーティリティポーチ(2001年製)
SAFARILAND 6004 with MOLLEアダプター
PARACLETE GPアップライトポーチ SG(Pre MSA)
PARACLETE ラジオポーチ SG(Pre MSA)
以前記事にした状態とほぼ同じです。
腰足周りに何も装備したくなかったので、CIRAS君に全ての収納を担っていただきました。
おかげでかなりヘビーになり、10ゲーム以上こなした夕方あたりは流石に肩とか足が痛くなりました。
大容量で汎用性が高く、触って感じる丈夫な質感と安定感のある着心地は「ヘビーデューティー」という言葉を具現化したような印象で非常に頼もしいです。
反面、肩周りのカットが後発のRBAVやその後の軽装化された他のアーマーに比べると小さく、ライフルを構えるのに若干違和感がありました。
着脱も脇腹部分で前後分離させるので、体が硬い人間だと毎回難儀する構造なのも少し時代を感じさせます。
古い設計故か随所にやや不便さはありますが、そんなデメリットは非常に些細な物だと思える圧倒的な存在感、魅力が溢れ出るマスターピースだと思います。
MICH2000
J-TECH製のレプリカです。
レプリカの中では高級品で、ツブツブの塗装感までしっかりあります。
チンストラップも出来が良かったはずですが、数年前の馬鹿な私は捨ててしまい、OPSCOREのX-NAPEに換装してしまっています。
官給ストラップを買わねばと思いつつ後回しになっています。
NVGマウントはカマボコ板で、これもJ-TECH付属の物だったはずです。
実物に換えようかとも思ったのですが、見比べても区別が付かないほど似ているので、これも後回しになっています。
中のパッドはオレゴンエアロのものにしていますが、かなりおススメです。
あとはベルクロを貼ったりランヤードを引っ掛けたり汚し塗装したり小物を盛り付けています。
ゴテゴテのヘルメットも大好きなんですが、今回のようにすっきりシンプルなのもコレはコレでいいですね。
最近初期アフばかりやっていてキャップしか被っていなかったので、久々のヘルメットは新鮮でした。
MSA SORDIN
Z-TACのレプリカです。
ステッカーカスタムされた中古が激安でしたので買ってみました。
ODAヘッドセットの鉄板はCOMTACと思いますが、ここはちょっと奇をてらってみました。
ウワサ通り、設計者の頭を疑いたくなるほど電池交換が激ムズですね。。
私は一度付けたが最後、その後まだ取り外せていません。
INSIDE THE GREENBERETSの劇中でもROB隊長がSORDINを使っています。
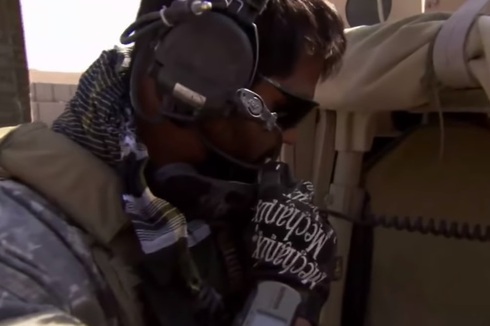
が、DUALでしかもマイクが右側についているレフティ仕様っぽいです。
レプリカは絶望的ですし、仮にあったとしても右利きだと右側マイクは実用上も不便(銃を構える際邪魔)があるので地獄です。
ROB隊長はホルスターの付け方から右利きと思いますし、ラジオも1個しか使ってないのですから、大人しく左マイクのシングルにして欲しかったと心底思います。
偶然イーベイにDUALレフティの実物がありましたが、流石にここは妥協してシングルの左マイクのレプにしました。
OAKLEY FACTORY PILOT GLOVES
米軍御用達の鉄板グローブですね。
劇中の隊員も嵌めています。

特徴的なデザインなので分かり易くてありがたいですね。
ただ、これも年代で仕様が2回以上変わっているっぽいです。
2005年時の写真

2012年時の写真

掌の縫製も変わっていたりするようですが、一番分かり易いのはナックルガードのカーボン素材のツヤ感です。
古いモデルはテカテカで、新しいものは艶消しになっています。
私の個体は確か2011年頃購入しましたが、艶消しナックルガードです。
まだ確証はありませんが、映像から見るにナショジオODAの時代はおそらくテカテカバージョンが正解なので、私の仕様はオーパーツかもしれません。無念です。
掌はぶっちゃけどうでもいいですが、手の甲は目立つ部分なので何とかしたいところです。
まあ旧バージョンMechanixを手に入れちゃうのがこの時代のグローブ問題解決としては一番早そうです。

OAKLEY SI M FRAME2.0

Mフレーム2.0は2006年から採用されている認識なので、年代的にはOKだと思われます。
まだちゃんと確認できていませんが、劇中の隊員はMフレームだとは思いますが2.0ではなさそうです。
ASOLO FSN95 GTX
購入してから50kmくらい履き込みましたが、履き始めよりかなり足に馴染んできて歩きやすく、相当お気に入りな一足になりました。
若干の重さ硬さはあるものの、足とのフィット感は抜群でゲーム使用でも何も問題ありませんでした。
しかし、どんな保管をされていたか分からない中古なのでソール劣化に一抹の不安はありますので、いざ交換した時の為にトゥのASOLO刻印複製や色合わせの手法の開発を進めておこうと思います。
Bucket Head氏もFSN95を履いてきていました。
劇中の隊員もこぞって履いていますね。
幅広い年代をカバーする鉄板ブーツとして、末永く使っていこうと思います。
ACU(UCP)
久々に着ましたが、やっぱりいいですね。
軽くてすぐ乾いて体の動きを阻害せず、S-Sサイズであれば全ての丈が私のような短手足の日本人でもちょうどよいです。
陸軍特有の迷彩柄で分かり易く特徴出しが出来るのもナイスですよね。
自分の知らない分野の装備をしている方と話す時は皆さん大抵「陸ですか?」とか「海ですか?」の属性確認から入ると思いますが、そこでいきなり間違えるとなんかすんごい気まずいですよね(私だけ?笑)
UCPであれば畑違いの方でも「とりあえず陸だろう」までは分かってもらえるので、スムーズなコミュニケーションが取れるのではと勝手に都合よく解釈しています。
そこで「いえ、PJです」や「実はMARSOCなんですよー」等の変化球であれば、それはそれで逆にしたり顔で喜んでもらえたりしますよね。
装備好きってめんどくさいですね(笑)
パッチはBucket Head氏と合わせてODA3124パッチを貼りました。
ODA表記が4桁に変わったのはグリーンベレーが改編された2008年以降の認識なので、このパッチは今回の装備ではオーパーツということになりますね。
でもどうしても貼りたかったんだからしょうがないんです(笑)
GARMIN Foretrex101
e湾から無事に到着しました。
購入してから到着まで色々勉強していたおかげで、入手後スムーズに使えました。
私は毎日職場まで片道10km自転車を漕いでいるのですが、サイコン代わりに腕に巻いて走ってみました。

とりあえず移動距離や速度はそこまでおかしくなく、ちゃんと衛星に見てもらえてるみたいです。
最初に衛星を補足した際、位置精度が700mとか出ていて「終わってる」と思っていたのですが、ちょっとしたら3~5mくらいで落ち着いたので良かったです。
信号待ち等で腕を少しでも動かすと移動時間に加算されてしまうので、移動時間と平均速度はあまりアテにならない数字になってしまうと思います。
あとは1歳半の娘と出かける時にベビーカーに取り付けて遊んでいます(笑)

BB弾の被弾で液晶が割れるという恐ろしい事例を聞いていたので対策しました。
LBTやEAGLEのケースに入れるのがスマートだと思ったのですが、年代が合わなさそうなので諦めました。
そこで、透明の下敷きを液晶の形状に切り抜き嵌め込んでいます。
不器用なので端部に隙間がありますが、接着等しなくても外れることなく嵌まってくれており、外観をそこまで損ねずBB防弾性UPできました。
1mmちょっとのPVC板でどこまで防御力上がっているかは不明ですが、まあ割れたら割れたで諦めようと思います。
ちなみにサバゲ実用性として、タイマー機能が中々良かったです。
液晶画面いっぱいにタイマーを表示できるのでG-SHOCK等のそれより数倍見やすく、ゲーム中の立ち回りを改善できました。
時間管理が楽に出来るようになったおかげで押し引きのタイミングが正確にでき、フラッグまで肉薄できるゲームが多かったです。
この日持ち込んだガーミン達です。
右のダミーはBucket Head氏が持ち込んだものですが、何処でも売っているダミーより本体の色合いがリアルでした。
バンドは実物を付けているとのことでした。
ダミーとは言え手を抜かない氏の拘りが垣間見れますね。
SUUNTO M9 COMPASS
旧型になります。

新型になったのは確か2014年か2015年頃だったと思うので、最新装備以外は旧型でないとオーパーツになってしまいます。
意外と高い取引相場で玉数もそこまで豊富ではないので、小物のクセに地味に難易度の高い装備ですよね。
全軍長い間使用していてミリフォト露出も非常に高いので、これからも需要と供給のバランスは悪化し続ける=値上がりし続けるのではないでしょうか?
コンパス周りでは、先日清水の舞台から飛び降りる覚悟で念願の「夢のお宝コンパス」を入手できましたので、後日特集記事を書こうと思います。
CASIO PROTREK PRG-40

2001年発売なので、2006年でもバリバリ現役だったと思います。
でかいし時間もズレますが、映画エリジウムに出てきそうな「レトロなハイテク感」が非常に気に入っています。
初期アフODAでの実用例もあると思われます。

ちなみにエリジウムのAKは一時期本気でスクラッチしようかと思っていましたが、なんとサードパーティから発売されましたね。


既製品が発売されてしまうと一気に醒めてしまうところが、自分はつくづく天邪鬼だなと思います(苦笑)
付けヒゲも出来のいい既製品が発売されたら、更なる高みを目指し始めるかもしれません。
以前床屋で切った自分の髪の毛を貰って付け髭の材料にしようと考えたことがあるのですが、友人に全力で止められました(笑)
M4
初期アフから数年経っている装備なのでM4も時間を進めようと思ったのですが、よく考えたら2006年はBLOCK1のままなので何も換える部分が無かったです(苦笑)
我が家のBLOCK2アクセサリ達は完全にホコリを被っています。
シュマグ
前々回のVショーでちょっと奮発してお高めの柄を調達していました。
劇中の隊員が巻いているのと似た柄です。
シュマグは何個あってもいいですね!
ヒゲ(GEN6)
前回のギアレボで頭固定用のゴムひもが切れてしまったので、いい機会だと思い固定位置を改修しGEN6となりました。
GEN6の大きな変更点は、頭を固定する紐を1本から2本に増強したことです。
これにより更に顔へのフィット感が増しました。
元々付けヒゲはヘルメット着用を前提として開発していたので、ヘルメットとの相性は抜群ですね。
ヘルメット+ヘッドセット+ヒゲのフル装備時は、かなり自然な仕上がりだと自画自賛してしまうレベルです。
INSIDE THE GREENBERETSのDVDを研究して更にこの時期の装備をブラッシュアップしつつ、2003~5年あたりの初期イラクODA装備も少しずつやっていきたいと思います。
初期アフも大物を手に入れましたので、年内1回くらいは初期アフで出撃したい次第です。
体1個ではとても足りませんね(笑)
先日のアメトークのスニーカー芸人で、佐藤隆太が「自分が履く暇が無いから、人に履かせてそれを眺める」と言っていましたが、「それいいな」と思いました(笑)
お読みいただきありがとうございました。
サバゲーバイキング

先日、ユニオン3フィールド同時開催の「サバゲーバイキング」にBucket Head氏、H氏と参加してきました。
バイキングと言ってもお昼ご飯が食べ放題というわけではなく、METユニオン、ユニオンベース、ヘッドショットの3フィールドが同時にゲームを開催していて、好き好きにフィールドを選んでゲームを楽しめるというものでした。

参加費は昼食代抜いて3000円でしたが、破格のコスパだと思います。
3ゲーム同時進行でも流石は老舗のユニオン、一切滞る事無くスムーズに各フィールドでゲーム回しをされていました。
スタッフも皆さん明るく聞き取り易い声で親切に対応してくださり、素晴らしいの一言に尽きます。
フィールドはご存知な方も多いでしょうし、3フィールドもあるので駆け足でポイントを書いていきます。
まずはユニオンベースです。
なんと言ってもフィールドの大外を囲うように延びる「山道」が特徴ですよね。
ここを登らずしてユニオンベースで遊んだとは言えませんね(笑)
ベース初体験だったH氏を連れて山道迂回ルートで攻めました。
山道は中央の砦から足場伝いに道が続くように変わっていました。
さらに斜面は一切のバリケードが無くなり、高台を取っても下からの撃ち上げに油断はできない造りになっていました。
実際我々も高台を陣取り敵全体を見下ろせる状況になりましたが、下からの思わぬ反撃でヒット者が続出しました(この時はほぼ無風だったのも大きいと思いますが)。
それでも撃ち下ろせる状況は圧倒的に有利ですし、このスケールの高低差はこのフィールドでしか味わえないと思うので、疲れますがついつい山道に足を運んでしまいます。
ちなみに「銃撃戦では撃ち下ろしが有利」というのは私は小学校5年生の時に映画「ザ・ロック」でエド・ハリスから学びました(笑)

ミリタリー好きなら99.999999%の方が見ているであろう名作中の名作ですよね!
シャワー室でのSEAL隊員達の悲劇は300回は繰り返し観ていると思います。


当時金曜ロードショーで録画したVHSが擦り切れる程観ました。
放映直後、仲良しの友人に「4039の家に遊びに行くと必ずザ・ロックの曲が流れている」と言わしめたほどです(笑)
あの金曜ロードショー初放映版の吹き替えが収録されたDVDが発売される日をずーっと待っているのですが、一向に出てきません。無念です。
サントラを町内中のCD屋を駆けずり回って探したのもいい思い出です。
今のようにアマゾンやヤフオク、youtubeが使えない時代は苦労したものです。
この映画以来ハンス・ジマーのファンになりました。

いつかこの映画の海兵隊装備をやらねばと思っているのですが、どうしてもこの

もしまだ「ザ・ロック」を観ていない方がいたら、イヤミではなく素直に羨ましいと思います。
初見の興奮、感動は絶対に初見でしか味わえません。
一度観てしまったら、二度と初見の状態には戻れないのです。
映画に限った話ではなく、何事も「初体験」というのは大きな価値があると思います。
これから世の中がどんなに便利になってもおそらく不変の価値だと思います。
なので、「あーこれ観たかったんだー」といって半分寝ながら機内映画で初見の映画を観てしまうのは、愚行としか言えない行為だと思います。
といっても私も誘惑に負けていつも初見映画を機内で観てしまい、その映画が面白かったら面白かった分だけ後悔するのですが(苦笑)
自分への戒めの為にここにぶちまけました(笑)
まあ映画が特別好きではない方からしたら、機内映画は適当にながら見できるこの上ない「いい暇潰し」だと思うので、結局はその人の価値観次第ですよね。
人生の時間は限られている割に世の娯楽は無限大に増殖し続けているので、本当に自分のしたいことは何か?を常に意識し取捨選択できるかが現代人に求められる最も大切なセンスなのかもしれませんね。
またもや得意の大脱線をしてしまいましたが、次フィールドの説明に入ります。
METユニオンです。
2年近く前に私が遊んだ時との大きな違いは、中央にキャットウォークが出来たことです。
上の通路もゲームで使えるようになっており、戦略性に深みが出ました。
キャットウォークを挟んで市外エリアと林&ブッシュエリアに分かれています。
市街地フィールドも色々凝ったオブジェや障害物が増えており、雰囲気が増していました。
METユニオンは平坦ですが変化に富んでいて広さもちょうどよく、交戦距離も位置取りやルートを考えれば近距離~遠距離まで様々に対応できるので、個人的にはゲームをしていて一番楽しいフィールドかもしれません。
ちょうど連携を取り易いような造りで、自然とチームで声を掛け合って「ラインを上げる」という感覚を体感しやすいからかもしれません。
個人的にはイチオシのフィールドです。
サバゲ初体験の友人知人を初めて連れて行くなら、私ならここかサバゲパークを選びます。
どちらも自分の周りの戦況を直感的に把握し易く、かつ交戦距離も程よい場合が多くどこから撃たれているかも分かり易いので「撃ち合っている感」を楽しみ易いと思うからです。
そして最後はヘッドショットです。
平坦で広大な敷地に、2階に登れる建物が20軒近くあるのは圧巻です。
まさに「街」です。
各建物の窓やその奥の暗がりに注意しながら、建物を一軒一軒制圧していくのはとても面白いです。
自分が2階に上がり、敵の足止めをしながら階下の味方に情報提供して攻め上がる支援をしたりと、色んな遊び方が出来るのも楽しいポイントです。
ただ全面同じような雰囲気なので、一日中ここでゲームをしていると飽きが来るのも確かです。
なので今回のように3フィールド選びながら遊べるサバゲーバイキングは大変ありがたいイベントでした。
ケータリングも充実しておりショップ出展もあり、参加者も程よく(体感150人くらい?でした)、純粋にゲームを沢山楽しみたいなら「サバゲ祭」よりもいいかもしれません。
そんなサバゲーバイキングに、私とBucket Head氏はUCPのODA合わせで臨みました。
完全に「双子コーデ」になりました(笑)
装備の特徴がまんま同じなので、ヒゲを付けている写真は自分でも一瞬どっちがどっちか分からなくなります。
イメージソースは現在研究真っ最中の「INSIDE THE GREENBERETS」です。


劇中のシーンとセーフティから見える風景がなんとなく似ていたので、テンションが上がって1時間くらいここでキャッキャ遊んでいました(笑)
よく見ると田んぼ感丸出しなので全然アフガンじゃないですが(苦笑)
Bucket Head氏は今回も小道具を仕込んできており、「小脇に抱えるのにちょうど良いダンボール」と
「洋物の地図」を用意していました。
おかげでアフガンの村々をパトロールしているナショジオODAっぽさが演出できました。
ちなみに地図はフィリピンのどこぞの島の地図なのはここだけのヒミツです(笑)
色々写真撮りましたが、このバックショットが今回一番お気に入りかもしれません。
Bucket Head氏はMBAVベースに胸ホルスター+3連M4ポーチ、脇はラジポ、ユーティリティポーチ、背中にMAP+MEDポーチというオーソドックスな構成でした。
腰足周りに何も着けていないところがナショジオODAらしさUPのポイントだと思います。
背中のMAPも敢えて中身をほぼ入れずペシャンコにしていますが、これも車両移動していた想定をするとリアルです。
実際のナショジオODAのMAPもスカスカっぽいですしね。

パックにはついついプチプチやシュマグ等「アンコ」をパンパンに詰めてしまいがちですが、場面を想定して敢えて空にするという上級テクニックだと思います。
さらに構成こそ基本的なものの、ポーチはDBTのキャメルタンやPPM、旧型BHI等シブいチョイスが勢ぞろいです。
直球のSFLCSは外して一味加えて来るところが彼らしいです。
凝っている装備は見ている側も楽しいですよね。
次回記事で詳しく書こうと思いますが、foretrex101もダミーながらよくある中華製ではなく、バンドは実物にしていました。
ホルスターも私が今超欲しいBHIの旧型プラットフォームで取り付けています。

ただ、MOLLE式では無くベルクロ式の方だったのでタイラップでMOLLEに括り付けています。
逆に現場臭くていいですよね。
彼のピンショットで私的ベストショットはこれです。
「村人へのお土産を入れた箱を笑顔で運ぶODAおじさん」です。
ハーツアンドマインズ感が溢れ出ていますね(笑)
今回は色々寸劇チックに写真を撮りましたので、次回の記事で載せようと思います。
私の装備詳細も次回記事でまとめようと思います。
H氏は3年間ほぼ何も変わらない装備です。
初めて買ったプレキャリ、メット、迷彩服(2種類)をずーっと着ています。
装備大好き人間2人にいつも囲まれているのに感化されない
まあ元々ミリタリーに興味が無く、その手のゲームもやらず、銃が出てくる映画やアニメ等も特段好きでない人なので、逆によく何年も一緒に飽きずにサバゲーしてくれているなと感謝しています。
今回、立てかけていたマルイの次世代SCAR-Hが倒れた拍子にストックロックボタンが折れてしまいました。
この部分の破損はあるあるのようですね。
これはマルイの設計というよりも、実銃のSCARの設計思想に起因しているところが大きいそうです。
SCARは無理な荷重が掛かった際、機関部への影響を避けストックが始めに壊れるようわざと脆く設計されているようです。
同じような話では、確かサファリランドのQLSもわざと壊れ易くしているようですね。

私の持っているVFC製の電動SCAR-Hも過去ストック部が簡単に折れましたので、確かな話なのかなと信じています。
H氏のサバゲー熱はだいぶ落ち着きを見せてきているので、この部品と一緒にサバゲーへの情熱も折れてしまわないか心配です。
これきっかけで「銃壊れちゃったし、もうやーめた」とならないよう、スペアパーツの手配や交換手順等、最大限バックアップしておこうと思います。
思い返してみると、ちゃんと晴れた日に屋外で一日通してバリバリゲームをやれたのは今年初めてかもしれません(笑)
定例会参加予定の日は狙ったように雨が降っており、あとはユルゲやギアフェス東北等、ゲームメインでは無いイベント参加も多かったので、ちょうど良い気候で久々に「サバゲらしいサバゲ」が楽しめて大満足な一日でした。
お読みいただきありがとうございました。
Mechanixグローブ年代考察

ギアレボ以降すっかり初期アフは休業中で、どっぷりUCPのODAに浸かっています。
泥沼野郎さんに命名いただいた「初期山アフ夫」の名が泣いてしまいますね(笑)
今目指している装備のイメージソースとしているのは、「Inside The Greenberets」に出てきた面々です。


今海外からDVDを取り寄せ中なので、届き次第詳細を考察しようと思っているのですが、ついつい荒い画質のyoutubeを眺めてあれこれ考えてしまいます。
今回は下画像のROB隊長が嵌めているグローブについて調査してみました。
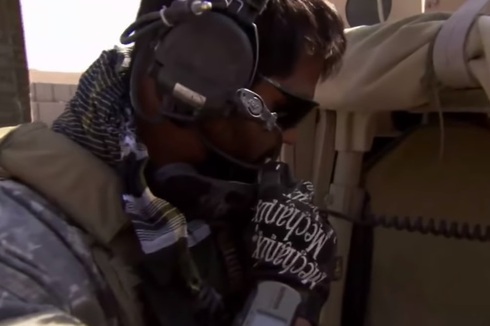
画像が荒いので詳細は不明ですが、誰が見てもメカニクスのブラックのグローブなのは確実だと思います。
モデルはおそらく基本モデルの「オリジナル」だと思います。

しかしここで問題が浮上します。
このグローブはしょっちゅうマイナーチェンジをしていて、しかも個体に製造年表記はない(はず)なので年代特定が困難です。
ROB隊長が嵌めているグローブの細かい仕様は高解像度の映像が手に入ったら確認すればいいので、それまでに「何年頃のオリジナルはこの仕様」というのを把握しておこうと思いました。
そこで今回もGoogle先生のもとを訪ね、ネットに転がっている断片的な情報をかき集めて点と点をつなげてみました。
本題に入る前に、今回Google検索において個人的な大発見があったのでご報告しておきます。
Googleで何かを検索して、検索BOXの真下にある「ツール」から検索結果を年月日で絞り込めることを知りました。

知ってる方からしたら「は?何を今更」だと思いますが、私は大感動いたしました(笑)
この機能が今回大活躍しました。
この機能を使えば時系列で情報を整理する場合に威力を発揮します。
今回で言えば2001年くらいから始めて半年くらいずつ検索期間を新しくしていき、新しい仕様のグローブの情報が出るのを確認する事で「ここでこの仕様が登場し始めた」といったようにモデルの時系列を整理していきました。
この機能を知っていれば、FSN95やForetrex101の発売時期を探る為にわざわざ10数年前のアウトドア雑誌を何冊も1ページ1ページ捲る必要は無かったかもしれません(苦笑)
まあそれはそれで楽しかったから結果オーライなのですが。
私は初期アフはじめ10数年前の装備をメインにやっているので、人一倍オーパーツ問題には真摯に取り組むのを信念として、今まで様々なアイテムの誕生時期を調べてきましたが、なんだか最近自分は探偵が天職なのではと思えてきました(笑)
まだ観れていませんが、「サーチ」という映画はひたすらPCで検索し続ける作品と聞いているので、激しく共感できる気がしてなりません(笑)

(私が知らなかっただけですが)Google先生の新たなる能力を引き出し、下記調査結果を導き出しました。
ちなみに以下は数あるMechanixのモデルの中で「オリジナル」に限った話ですので、予めご了承ください。
まず、2001年1月1日から検索して出てきた一番古い画像です。

2001年にアップされています。
かなり荒いですが、手首のタグに注目しました。
Mechanixの「 M」のロゴが白バックに黒抜きに見えます。
次です。

2003年時点で出てきた画像です。
タグのロゴが黄色くなりました。
そしてその下にごちゃごちゃと3行程白い文字が書いてあります。
ロゴの脇には無地の四角があります。
裏側のタブは黄色ロゴ+白文字で「GLOVES」とあります。
次です。


2005年3月時点でアップされていた写真です。
タグの黄色ロゴの下が白い文字で「ORIGINAL」のみになりました。
裏側のタブは「GLOVES」が無くなり、形状も変わっています。
先端の方に携帯電話の電波表示みたいな3本線が見えますが、ブラックアウトしています。
本来は黄色くなっていて消えてしまったのか?それとも最初から黒だったかは不明です。
カラーによって違う可能性もありますね。
次です。
2006年3月のものです。
「ORIGINAL」の文字が赤になり、横の四角が無地ではなく「Mechanix」が斜めに並んだ模様になりました。
下の製品画像と同じ仕様のものと思います。

後述で写真が出てきますが、裏側のタブはほぼ2005年時点のものと同じに見えますが、先端部の3本バーは黄色くなっていました。
次です。
2009年11月の写真です。
タグが無くなり、裏側のタブと一体化した樹脂製のバンドになりました。
ロゴ横の白い四角模様が印象的です。
下の製品画像の仕様と思います。
ちなみにこの仕様と1つ前の仕様を比較している記事もありました。
左が旧型、右が新型です。



最後です。

2012年8月の写真です。
白い模様は裏側に行き、バンドに蛇腹状の溝が入るのが特徴的です。
下画像の仕様だと思います。

私の認識ではこれが現行になります。
以上が今回の調査で判明した内容になります。
主な識別ポイントをまとめると
・2001年時点はタグが真っ白
・2003年時点でタグの「MECHANIX」ロゴが黄色くなっている
・2005年3月時点ではタグのメーカーロゴの下の文字が白い「ORIGINAL」のみになっている
・2006年3月時点では「ORIGINAL」の文字が赤くなる
・2009年11月時点ではタグが無くなり一体の樹脂バンドに変わり、表側に白い四角が付く
・2012年8月時点では手首部が蛇腹状になり、白四角は裏面に移動
大体3年に1回くらいは仕様チェンジしているっぽいですね。
なので2012年以降も私が認識ないだけで、2015年くらいに仕様が変わっているかもしれませんね。
私の拙い知識と知恵で調べた結果なので、色々間違いや抜けがあるかもしれません。
もし何か追加でご存知の方がいらっしゃったら、コメント等していただけると大変嬉しいです。
こうして調べると、全仕様集めたくなりますね。
2009年モデルはまだまだ市場にゴロゴロしているので、今の内に買っておけば後々高騰するかもしれませんね(笑)
逆にそれより前の仕様は一気にレアになります。
ただ、元々安いグローブなので玉数はまだまだ世にあるはずで、しかもミリタリー以外からの出品者(バイクや自転車)にとっては希少価値は低く「ただの古くて性能が低いグローブ」なので、出てくる時は相当安かったりします。
ところで2001年時点で存在していたということは、年代的には初期アフもOKということですよね。
使用例は私の知る限りでは思いつきませんが。
ちなみに2001~2005年くらいまでのアウトドア雑誌「BACKPACKER」を何冊か見ている限り、Mechanixの広告や記事は一切出てきていません。
バイク専門誌では出ていたかもしれませんので、もし出ていれば「バイク好きな隊員」という設定でMechanixのグローブと一緒にハーレーのキャップを被ったりすると、装備にストーリーが生まれてきそうですね。
実際ハーレーのキャップやTシャツ等のバイク関連のアイテムを着用している方はよくいる認識です。


最近はこうやって隊員個人の趣味趣向や家庭事情等のバックグラウンドまで妄想して装備を考えるようになってきました。末期症状ですね(笑)
もしかしたらある日基地のPXでMechanixのグローブの取り扱いが始まって、口コミ等で一気に全軍で流行りはじめたのかもしれませんね。
もしくはMechanixのセールスマンが軍使用の需要に目を付けて、色んな基地に売り込みにいって流行らせたのかもしれませんね。
気づいたらかなり脱線していましたが(笑)、今の私が知りたいのはナショジオODAのROB隊長の嵌めていたグローブの仕様ですので、上記調査結果でまあ十分と言えます。
ROB隊長の嵌めているのがオリジナルであるという前提において、時系列から考えると2009年11月に確認したよりも前の布タグのモデルで、その頃現役モデルだったと思われる赤文字ORIGINALか、その一個前の白文字ORIGINALあたりの可能性が高いと分析しました。
鮮明にタグが見えれば一発なのですが、如何せんyoutubeの解像度がひどいので、よく見える手の甲に並んでいる「Mechanix」の文字に注目しました。
大人しくDVDを待てばいいのに、我慢できず荒い画像で頑張って解析しました(笑)
劇中の画像
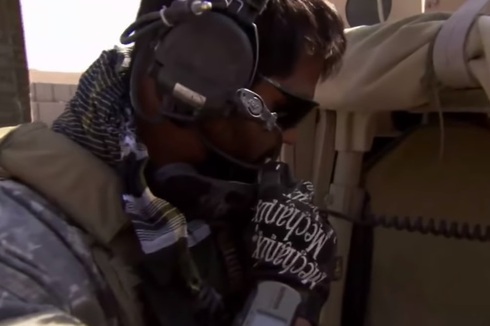
2003年確認のロゴ+3列文字

2005年確認の白文字ORIGINAL

2006年確認の赤文字ORIGINAL

手の甲のMechanixロゴ同士の位置関係から、2001年確認のロゴ+3列文字ではない事がわかりました。
白文字か赤文字ORIGINALのどちらかと思われますが、この2つの区別は上記画像からでは判別できませんでした。
DVD入手後、タグが見える瞬間を血眼で捜そうと思います。
これがオリジナル以外のモデルだったとするとまた厄介な事になりそうですが、今はオリジナルである事を信じて事を進めようと思います。
研究している最中、前回のギアレボでMUNAGE先生が古いMechanixを嵌めていたことを思い出しました。
今回の調査で2006年3月時点で見つけた赤文字ORIGINALっぽいですね。
今度お会いした時に、FSN95の件も合わせて色々尋問させていただこうと思います(笑)
サバゲーマーには身近な存在であるMechanixのグローブですが、こうしてちゃんと調べはじめると結構な「沼感」があることに気づかされました。
まあ薄々感づいてはいたので、今まで敢えてノータッチでいたのもありますが(苦笑)
デルタやSEALの諸兄はさらにおぞましい激レア絶版モデルを巡る「Mechanix地獄」に常に直面されていると思いますので、それに比べればGBのグローブ事情は「可愛いもん」どころでは済まされないくらい楽勝な問題だと思いますが。
デルタの「Mechanix地獄」は盟友Bucket Head氏に何度と無く聞かされていますが、先日インスタにその「地獄のグローブ」が2着も並んでいる写真が上がっていて度肝を抜かれました。

どうでもいいですが「地獄の」ってつけると無条件にこの方が頭に浮かびますね(笑)

彼はグローブに並々ならぬ執念を燃やしている「手袋フェチ」ですので、グローブに関する事は色々教えてもらっています。
持つべきものは友ですね!
ただ、今回はバケツ先生ではなく、独学でGoogle先生に色々教えてもらった結果をまとめてみました。
ただ人に聞いて「あーそうなんだ」で終わらせるより、こうして自分自身で考えて点と点の情報を線にして「知識を紡ぎ出す」方が達成感はありますよね。
そしてこういう体験も装備趣味における「旨味」なのだと思います。
知的好奇心を満たした後、お金を使って物欲を満たし、残るものは日常生活では何も役に立たない無駄知識と、同じく日常生活では意味の無いナイロンやBB弾散布装置のみなわけです。
一見して時間とお金の無駄しか見えませんが、それでハッピーな日々を送れているのですからある意味我々は勝ち組なのかもしれませんね(笑)
一切の無駄を排して、時間やお金に関して効率的な生き方を追求しても、それは「幸せ」には直結しないと私は考えています。
「家族と遊びにいきたい」「友達と飲みにいきたい」「20年前のばっちいナイロンを買いたい」「青アザ作りながら大人同士で鉄砲ごっこがしたい」という、お金や時間効率上は無駄な事を心の底から楽しめる事がすなわち「幸せ」なのだと私は思っています。
「有益な無駄」を謳歌する為に「余計な無駄」を最大限排していくのが、人生の正しい効率化でありベストな生き方だと私個人は思っています。
無駄をする為にせっせと仕事して家事して子育てして朽ちていく。
そしてその子も同じ事を繰り返して地球を蝕み続け、いつかは宇宙の無限の闇に飲まれていく。
そう考えると人間とは何とも空虚な生き物ですね。
よくもまあ手袋ひとつで「人間の虚しさ」まで考え至れるものだと自分でも呆れます(笑)
そんな悟りみたいな事を考えるのはこれくらいにして、古臭いグローブを必死こいて探して買ったりして、それを夜な夜なニヤニヤ嵌めたりして死ぬまで全力で無駄をし続けてやろうと思います!
お読みいただきありがとうございました。
GARMIN Foretrex101 予習

今回もナショジオODAネタです。
前回同様トップ画像にした「Inside The Greenberets」のROB隊長ですが、グローブはサバゲでもポピュラーなメカニクスのものですよね。

ただ、メカニクスは幾度となくマイナーチェンジされているので、年代別の特徴を現在勉強中です。
この方が着けている年代のモデルはおそらく特定できたので、あとはネットで出てくるのを待つのみです。
今回も前回に引き続き、GARMIN Foretrex101の事を書いていきます。

本題に入る前に、前回から分かったことがひとつあったので補足を書いておきます。
前回、Foretrex301と401が同時期の2009年に発売したっぽいと書きましたが、どうやらその通りのようです。
301と401の差は電子コンパスと気圧高度計の有無で、301にはどちらも無く、401はどちらも付いているようです。
本体色も全然違うので、ミリフォトでの識別は比較的楽そうですね。

401が緑です。
それでは本題に入ります、
実物は現在海を渡ってきている最中で、私の手元にはまだ下写真の「紙粘土を捏ねて色を塗っただけ」のようなダミーしかありませんが、届いたらすぐに使えるように予習しておこうと思いました。
今までダミーしか持ってなかったので、機能に関しては「今のGoogleマップの超劣化版みたいな感じが、初代たまごっちみたいな画面で手元で見れるんじゃね?」くらいの認識でいました。
なのでとりあえず手首かプレキャリかM4のストックあたりに、向きとか位置とかシチュエーションを特に意識せず、雰囲気で適当に装備していました。
今回の実物調達を機に、機能や操作をちゃんと理解して「こういう状況で使ってたのかな?」「だったらここにこう着けるのはアリだな」等、装備の
Foretrex101は発売当時かなりエポックメイキングなコンセプトだったらしく、ガジェット好きや登山愛好家、自転車乗り等から注目を集めていたようで、ネット上でも研究記事が多く残っています。
ミリタリー好きの食いつきはおそらくそこから1,2年はタイムラグがあり、ミリフォトでの露出が多くなってきて認識が広まってきてからだと思います。
実際、2004、5年当時にミリタリー趣味関連でForetrexについて書いてある記事はみつかりませんでした。
今はもっと多機能なスマートウォッチがどんどん世に出てきていますが、Foretrexはどう進化していくのでしょうね。
それとも淘汰されて過去の遺物になってしまうんでしょうか。
GARMIN自身が多種多様なスマートウォッチを発売しているトップメーカーですよね。

ちなみに我らが国産メーカーCASIOもアウトドア特化のスマートウォッチを作っています。

いつの日かこのようなスマートウォッチがミリフォトで散見されるようになってくるのでしょうか。
スマートウォッチはモデル更新が早いので、すぐ生産終了の旧モデル化してしまって調達に苦労するのが目に見えますね。。
頼むから兵隊さんにはロングセラーのG-SHOCKとかTIMEXをずっと使っていて欲しいところです(笑)
ちなみに岡山県警はカシオのスマートウォッチ(F20という機種)を導入しているようです。
参考URL:https://www.casio.co.jp/release/2018/0420_wsd-f20ab/
LE装備では既にスマートウォッチの波が来ているということですね!
日本の県警装備を「LE装備」と言っていいのかは分かりませんが(苦笑)
話を戻しますが、Foretrex101は色々な個人やお店のサイトで細かく機能や操作説明、実用例を紹介されていますので、それらでざっと勉強させていただきました。
「Foretrex101」と調べればごまんとヒットします。
下記に現状の私なりの理解と、実際の兵隊の運用を妄想します。
あくまでまだ現物を触ったことも無い&妄想癖たっぷりの人間の見解なので、正確性に関しては全く持って保証できませんのであしからず(笑)
まず、Foretrex101の持っている「能力」を突き詰めると下記3つに絞られるようです。
1.自分が地球上のどこにいるがわかる(衛星に見てもらう)
2.時間が分かる
3.それらの情報を一定時間隔で一定量記録できる
これだけです。シンプル・イズ・ベストですね。
そしてこの3つの「能力」を組み合わせて、アウトドアでの活動に有益な情報を出力する「機能」を持っているという理解をしました。
シンプルな能力なのに、出力できる情報は多種多様に及びます。
機能一覧も様々な方がブログ等でまとめてくださっていて非常に助かります。
詳細な機能の説明は先人方が素晴らしいまとめをしてくださっていますので、私の出る幕などありません。
以下は沢山ある機能の中で、実際に私自身が使ってみたいと思ったり、「へぇ」と思ったり、米軍兵士がアフガン等でこうやって使っていたのかな?という妄想をした機能について書いていきます。
現在地を緯度、経度として出力

まあこれが無いとGPSとして話にならないですよね(笑)
ちなみに画面は2~4分割までできるようで、どの情報を表示するかカスタマイズできるようですね。
上画像で言うと、上側が緯度経度を指しており、下は高度のようです。
緯度経度が分かれば、自分が地球上の何処にいるか座標でわかります。
あとは目的に合った地図と照らし合わせれば、どの国のどの町のどの住所にいるか?どの山のどの尾根にいるか?等の所謂「現在地」がわかりますよね。
両手が塞がっていてもすぐ手元で緯度経度を見られるというのは、アフガン等で車や徒歩で長距離行軍する際には重宝したのではないかなと思います。


高度を出力
下写真の下側で表示されています。

私は高度を読み取るには気圧計が内蔵されていないと出来ないと思っていたのですが、Foretrex101には気圧計は入っていません。
全然ちゃんとわかってませんが、複数の衛星からのそれぞれの距離情報から高度が割り出せるらしいです。
ただ、精度は気圧式の物より数m単位で悪いみたいです。
使い道としては、地図では載っていないような人工物の高さや、細かい地形の大体の立体的な位置関係をざっくり把握する際に使っていたかもしれませんね。
私の日常生活では「この場所ってこんなに高いんだ低いんだ」程度の使い道しか思い浮かびません(笑)
速度を出力

時間と位置を把握できるということは、速度も分かりますよね。
「今いるところ」「〇〇秒前にいたところ」の2点の距離を時間で割れば速度が出てきますよね。
Foretrex101は様々な条件の速度情報が出力できるみたいですね(最高速度や現在の速度、平均速度等)。
これは日常生活でデータ収集したら面白そうです。
まず徒歩は車と違い速度計がないので、歩く速度を数字で確認できるのはウォーキングやランニングの際のペースを整える判断材料にできそうですね。
自動車には無論速度計が、自転車にもサイクルコンピュータを着ければ速度表示が出ますが、どちらもタイヤの径と回転数から導いている数字のはずです。
なので、タイヤと地面の摩擦での滑りによる損失は考慮されていない、もしくは予め決められた係数が掛けられていると思います。
それに対しGPSは単純に座標変化(=移動した距離)と時間の割り算なので、物理的な速度計より正確な値が出るはずです(GPSの精度によりますが)。
実際、知人の自動車は高速道路走行で10km/hくらい備え付けの速度計と後付のGPS速度計で誤差が出ていました(備え付け速度計の方が遅い数字)。
それが分かるからなんだと言われると、「より法定速度ギリまでスピード出せる」くらいしか考え付きませんが(笑)
というか、同じ原理でGPSを用いた速度計もスマホのアプリで普通にありますね(笑)
目的地座標をセットし誘導できる

予め座標をセットし、そこに対して現在地から誘導をしてくれるようです。
今進んでいる方向とポイントの方向の差を認識し、矢印表示の形で行くべき方向を示してくれるようです。
ひとつ面白いと思ったのは、Foretrex101はコンパスは内蔵していない点です。
なので、自分が何処を向いているのかを知る術はないようです。
あくまで「進行方向に対し方角はこうで、目的地はこっち」としか伝えられないようです。
ここで思ったのは、「101とコンパスは一緒に見れた方がよさそう」です。
コンパス機能が無い101とSUUNTOのM9等のリストコンパスを一緒に身に着けていてもなんら不思議ではないですね。

逆に401は電子コンパス内蔵なので、401とリストコンパスを一緒に装備するというのは不自然かもしれませんね。
まあ見易さや信頼性から、機械式コンパスを併用していた可能性も十分ありますが。
通った場所と時間を記録、出力できる
これが分かると報告書作成の時に便利そうですね。
海外ドラマ「バンド・オブ・ブラザーズ」の第5話で、ウィンターズ大尉が戦闘報告書を色々思い出しながら書いていましたね。

あれは70年以上前の話なので完全に記憶頼みで書いていたっぽいですが、Foretrex101があれば記録していた時間と場所情報で記憶を補完できますし、証拠にもなりますよね。
「サボってませんよ!ほら、ちゃんとココ行ってるでしょ。」的な(笑)
今は更に時代が進んだので、任務によってはアクションカメラで一部始終記録していそうですよね。
実際にYoutube等でアクションカメラで撮影した本物の戦闘シーンが無数に見られますよね。
IED等が仕掛けられていた箇所や時間のデータ取りをして「このルートは警戒を厳に」的な情報共有もしていたかもしれませんね。
私の日常生活では「何キロ移動して、平均時速何キロだった」くらいの情報から健康管理に役立ちそうですね。
これもスマホで余裕でできちゃそうですが、がんばって101を使ってみます(笑)
PC上で地図と照らし合わせることもできるので、色々地図データとか用意すればさらに面白いかもしれません。
101に対応した地図データはまだ現役で、無料でダウンロードできるようですし。
ざっと機能一覧を予習して思ったことは以上です。
あとは実際に手にして、操作感を実体験した上で分かることや、装備にどう盛り込むのがリアルなのかの妄想を更に深めていこうと思います。
勉強すればするほど、現物の到着が待ち遠しくなってきます。
お読みいただきありがとうございました。
GARMIN Foretrex101

先日、一度閉鎖していたあるミリブロがいつの間にか復活している事に気づきました。
そのブログは私の装備趣味のバイブルとも言えるもので、時には一日何回も訪問して勉強させていただいていました。
数年振りに当時何度も読んでいた記事を読み返させていただき、懐かしいやら嬉しいやらで少し涙が出ました(笑)
私もミリブロガーの端くれとして、その御方のブログのように同じ趣味の同志のお役に少しでも立てるブログを書いていければと改めて発奮した次第です。
そんな奮起をしたそばから、今回も誰の役に立つのか分からないニッチな話をしていきます(笑)
今回も今私の中で怒涛の如く温度急上昇中の「ナショジオODA」に纏わる話です。

先日うっかり恋焦がれていたCIRASを手にしてしまったばっかりに、たがが外れてしまったようです(笑)
ナショジオODA、すなわち「Inside The Greenberets」のDVDが海を渡って来ている最中ですが、我慢できずついYoutube版の荒い画像に目を凝らしてしまいます。

ちゃんとした考察はDVDが届いてからにしようと思っていますが、今回、荒い画像でもはっきり分かるあるアイテムについて書きたいと思います。
トップ画像にしましたが、チームコマンダーのROB隊長の右腕に着いている機器です。

この趣味をやっている方々には抜群の知名度だと思いますが、GARMINのForetrex101ですね。

米軍はじめ各国の兵隊さんがForetrexシリーズをこぞって使用しています。




ハリボテも発売されていますよね。

このダミーは数年前から市場にある認識ですが結構品薄な時期があったりして、たまにオークションで中古が新品より高く取引されていたりして常時それなりの需要があるアイテムなのかなと思います。
実物もちょくちょく出品されていますが、諭吉さん出動は基本免れない相場です。
ミリタリー需要を知らない方が「こんなガラクタ誰が買うんだか」という感じで、たまに信じられない低価格で即決で出たりしますよね。
出品者は思わぬ食いつきにびっくりしたのではないでしょうか(笑)
現在、シリーズは既に701まで出ているようです。

私は現在101のダミーにお世話になっています。
真っ白の「紙感丸出し液晶」は流石にナシなので、盟友Bucket Head氏に教えてもらった、映画館でもらった3Dメガネのレンズを切って貼って液晶部をリアル化する手法を試しています。
ただ、私の作業がやっつけ過ぎてベコベコです(苦笑)
本体色も実物に比べて妙に明るすぎるのでごまかしで汚し塗装したりしましたが、どうにも好きになれません。
そこでメリケン湾を何気なく見渡してみると、船代入れても相当お安い価格でプカプカ浮いている出物を発見しました。

無論速攻で掬い上げ、現在入国待ちの状態です。
101君の来日を今か今かと待ちながら、彼について少しお勉強してみました。
今まで、Foretrex101は2003年末~2004年に発売されたというのが私の認識でした。
ただ、このソースは12、3年近く前に個人の方のブログに書かれていた内容を基にしていますので、私自身もイマイチ自信がないというか、確固たる証拠がなく気持ち悪いです。
そこで、先日のASOLO FSN95の調査の際にハマッた「昔のアウトドア雑誌しらみつぶし作戦」を実行しました。
対象はFSN95の時と同じ「BACKPACKER」です。

2003年末あたりから2004年に掛けてのバックナンバーを注意深く見ていると、2004年5月号で初めて下記広告が出てきました。


やりました!
FSN95に引き続き、またもやBACKPACKER誌のおかげで「動かぬ証拠」を手に入れました。
しかし喜ぶのも束の間、この広告で解せない事がひとつ浮上しました。
広告の本体の色が明らかに緑色で、Foretrex201にしかみえません。

「201ってことは101の後継なんでしょ?モデル更新なんて最低でも1年はしないだろうから、この広告が201だとしたら101はこの更に1年以上前に発売されてるってこと??」と、頭を抱えてしまいました。
困った時のGoogle先生です。
今までノーマークだったForetrex201について調べました。
すると、どうやら101と201は兄弟機種ということが判明しました。
101は乾電池給電で、201は充電式バッテリー内蔵とのことでした。
予備の電池さえあれば電池切れで使えなくなる心配がない101を現地の兵隊が好んで使ったのは想像に難くないので、兄弟でも201のミリフォト露出が少ないのは納得ですね。
上記の情報が正しければ、広告が201の写真だったとしても101も同時期に発売されたと考えていいと思いました。
さらに以上の情報を踏まえ、ダメ押しでGARMINの公式ページを見てみました。
101の製品説明ページには「The Foretrex 101 and its counterpart, Foretrex 201...」とあり、201のページには「The Foretrex 201 and its counterpart, Foretrex 101...」とあります。
兄弟機種ということが公式ページからもわかりました。
これも確固たる証拠と言っていいでしょう。
101ページ:https://buy.garmin.com/en-US/US/p/260
201ページ:https://buy.garmin.com/en-US/US/p/257
さらに公式ページ上で公開されている101と201のマニュアルを見てみると、どちらも末尾に「copyright 2004-2006」とあります。

これでダメ押しですね。
101も201も2004年に発売されていたことが確信できました。
ちなみに説明書は2006年に改訂されたので「2004-2006」と書いてあるようです。
更にちなみにこの説明書copyright作戦で、301と401は2009年に発売されているらしいということが判明しました。
301/401も同じ年の発売っぽいんですね。
どういう関係なのかまでは面倒になったので調べませんでした。
まだまだ市場には各モデル流通しているので、装備の年代等に合わせて拘って揃えたいところですね。
せっかく雑誌を漁ったので、BACKPACKERに載っていたGARMINの広告をご紹介しておこうと思います。
まず2002年5月号に載っていた広告です。

etrexですね。
etrexは細かく色々モデルがありますが、外装はほぼ同じです。
ちなみに下記ページに一昔前のGARMIN ハンディGPSの色々な機種の機能紹介がされていて非常に勉強になります。
http://www.soaring.co.jp/gps/garmin.htm
初期アフドキュメンタリー番組「Profiles From The Front Line」でもetrexと思われる機器を操作しているシーンが出てきます。

親指は画面左上のスティックを操作しているはずなので、スティック付きの「VENTURE」か「LEGEND」か「VISTA」のどれかだとは思います。
解像度が高ければ画面上にあるモデル名の印刷が読めるのですが。歯がゆいですね。
これらのモデルは時代で進化してモデル更新したのではなく、機能別のグレード分けで同時期に展開していたものだと推測しています。
この番組が撮影されたのはおそらく2002年夏頃と思われるので、この頃はetrexが現役だったのかもしれませんね。
etrexはミリフォトでもちょいちょい出てきますので、小道具としておすすめです。
ただ、MOLLEに引っ掛けたりクリップ等は無いので、魅せる装備にするには一工夫必要ですね。
2002年8月号にはこんな広告が出ていました。


GPSVという機種のようです。
無骨なデザインでかっこいいですね。
使用例は見たことがありませんが、特殊部隊の隊員等が使っていたとしても何ら不思議ではなさそうです。
次は2002年9月号の広告です。

Rinoというモデルのようです。
特徴的なアンテナの形状が由来でしょうか。
ちなみにRinoは2003年12月号にも広告が出ていました。

1年近く経っても1ページ丸々の広告が出ているなんて、人気機種だったのかもしれませんね。
2003年9月にも違うモデルの広告が出ていました。

Geko301というモデルです。
Gekoは広くバリエーション展開していてポピュラーな印象があります。
次は2004年8月号です。


液晶がカラーになってますね。
GPSMAP60Cというモデルのようです。
最後に2004年9月号です。

ガワはetrexそのままに見えますが、カラー液晶になっています。
ちょっと調べただけでも大量にGARMIN製ハンディGPSの広告が出てきました。
それぞれの機種に得手不得手があると思いますので、選択肢の自由が利く特殊部隊員は自分の好みや用途によって選んでいた可能性はありますよね。
そんな妄想をしながら昔の機種情報を調べ、オークションサイトを探すのも一興かもしれませんね。
高性能GPS内蔵のスマホが一人一台の今日び、昔のハンディGPSなぞ基本的にはガラクタ扱いで二束三文の場合が多いので、ちょっとした小道具として調達しても面白いと思います。
他にも今回の雑誌漁りで色々興味深い情報が掘り出されたので、折を見て都度紹介していこうと思います。
お読みいただきありがとうございました。
マーサイラス!

先日EAGLEのMAR CIRASを入手しましたので記事にしておきます。
MAR CIRASは私がグリーンベレー装備をやってみたいと思った頃は憧れの存在でした。
ご存知の方が殆どだと思いますが、CIRASはLANDとMARITIMEバージョンが有ります。
LAND

MARITIME

たとえポーチが満載されていてCIRAS本体がほぼ見えなくても、首元のグリーンのベルクロの有無で識別は超簡単ですね。
MARITIMEは省略してMARと書かれるのが一般的ですね。
特にMARの方は多くの特殊部隊が採用して、2000年代中盤のミリフォトでは非常に露出が多いです。



グリーンベレーも圧倒的にMARの方が使用例が多い印象です。
陸軍のくせにMARITIMEなんですね。不思議です。
まあ実際に私もLANDとMARどちらも着てみましたが、MOLLEの配置は圧倒的にMARの方が使い易いとは思います。
他にも要素はあるのかもしれませんが、いずれにせよLANDは少なくともODA装備では日陰者です。
ヤフオク等でも価格差がかなりありますが、安易に「CIRAS」だけで安いLANDに手を出すと、どうせそのうちMARが欲しくなるので注意が必要です。
今は時代が進みMBAVやRBAV、JPCやAVS等「花形」といえる代表格アーマーは数多くあり、また高品質なレプリカも大量にあり選択肢が多様化したおかげで、当時では考えられないくらい安価に手に入りました。
今回入手したのは2005年製のMサイズ、色はもちろんKHです。

タグから製造年月がわかります。

よく「青タグ」なんて言われていますが、どのような識別の役に立つのか勉強不足で分かりません。
文字がかなり掠れていますが、MFG DATEとサイズはちゃんと読める状態でいてくれました。感謝感激です!
この機会にCIRASについて改めて情報収集してみました。
私はてっきりCIRASはSFLCSとして支給が開始された物だと思っていましたが、違いました。
CIRASは2004年頃から支給が始まったようです。
対してSFLCSは2006年頃からのようです。
なので、SFLCSが支給されるまではCIRASにはあらゆるメーカーのポーチが着けられて運用されており、隊員毎に個性があり非常に魅力的です。



2004年まで支給が続けられていたと思われるSPEAR ELCSをはじめ、MOLLE2、パラクレイトやTAC-T、DBT、BHI等のポーチがごった煮状態です。
他にもACUが支給されているので2005年以降だと思いますが、MOLLE2ポーチを使っている隊員もいたりして興味深いです。

個人的にこれらの、SPEARが終わりSFLCSが支給されたあたりまでの「過渡期CIRAS」がかなりドストライクです。
なのでCIRAS入手を機にパラクレイトやTAC-T、DBT等のポーチを血眼になって集めている最中です。
ちなみにパラクレイトがMSA社に買収されて、タグに「MSAロゴ」が入ったのは有名な話だと思いますが、買収された時期は2006年だそうです。
なので、MSAタグの物は少なくとも2006年以後の物ということになり、年代考証に役立ちそうです。
このあたりは、ちょい古のデルタやCIFをやられている方なら常識なのかもしれませんね。
私はまだまだ浅はかなパラク知識しか無く、いそいそと勉強中です。
直近ちょうどASOLO FSN95も手に入れましたので、俄然2000年代中期ODA装備熱が上がってきました。
2006年以降のUCPを着てSFLCSてんこ盛りのODAももちろん大好きです。
ちょうどこのあたりのイメージソースといえばナショナルジオグラフィックが2007年に放送した「INSIDE THE GREENBERETS」が代表的だと思います。


先月号のコンバットマガジンでも特集されていましたね!
胸熱な記事でした。
この番組は10年近く前に盟友Bucket Head氏がケーブルテレビで録画したDVDを借りて見ましたが、この機に改めてちゃんと研究したいと思い、現在海外版正規DVDを輸入中です。

研究に先立ち、本番組で密着されたODA3124のパッチのレプリカを入手しておきました。

どうせ後で2000%欲しくなるので先に買っておいた次第です(笑)
今更ではありますが、今回のMAR CIRAS入手をきっかけにナショジオODA装備をしてみたいと思います。
嬉しいことに番組中の隊員もFSN95履きまくっていますし。
荒い画像ですがYoutubeでナショジオODAを眺めながら、現状のあり合わせで盛り付けてみました。

まだ足りないポーチが多く満足はいってないですが、概ねのイメージは実現できました。
ナショジオODAは基本ハンヴィーで移動しているためか、腰周り足周りに何も着けていないのが印象的です。

なのでホルスターはプレキャリに取り付ける必要が出てきます。
ホルスターをプレキャリに取り付けるプラットフォームで、この時期でよく見るのはBHIのナイロン式のプラットフォームです。

正式名称は「CQCストライクプラットホーム」というらしいです。
結構前から欲しくて探しているのですが、全然出てきません。。
レプリカが腐るほどあるプラ製のプラットフォームなら超楽勝なのですが。

こちらは「CQCホルスターMOLLEプラットフォーム」という名前らしいです。素晴らしく混同しますね。
チェストハーネスの件といい、BHIはマジでネーミングセンスが
ちなみに上記の旧型は2008年頭には生産終了し、そのちょっと前あたりからプラ製の物が発売開始されたようです。
なので2007、8年あたりまでの装備を再現する際は、このプラ製の方はオーパーツかもしれないので注意が必要ですね。
先日のギアレボでTJ1さんにお聞きしたのですが、サファリのホルスターもこのBHIのプラットフォームを使って着けている隊員が多かったそうです。
しかし私は全然見つけらず痺れを切らし、使用例は見た事がないのですがサファリランド製のプラットフォームを導入しました。

カイデックスの板に孔が空いていて、PALSに引っ掛けられる紐が付いているだけのシンプルなアイテムです。
これにレッグパネルから外した6004を取り付け、PALSに通しました。
このイマイチ洗練されてない野暮ったさがいい感じです(笑)
腰、足周りに装備を一切着けずにプレキャリに集約するとなると、大容量のCIRASといえど結構キツキツでした。
サバゲでの実用性も考慮すると、CIRASに取り付け必須なポーチは下記になります。
・M4マガジンポーチ(5本以上携行)
・M9マガジンポーチ(2本以上携行)
・ホルスター
・ユーティリティポーチ(IFAK設定の貴重品入れ)
・ラジオポーチ
・ダンプポーチ
・PTT
それらを干渉しないように組んでみた結果が上記の写真のような構成になりました。
下記のように、まるでパズルのように配置が決まりました。
ホルスターの位置が下の方になっていますが、よく見る胸の位置にしてしまうと、その下に置けるポーチが限られてしまいます。
緑のTAC-TのMAVポーチをダンプポーチとするのですが、これをサイドパネルに持っていくと腕が回らず空マガジンを入れるのにまごついてしまう為、前面にある必要があります。
しかしMAVポーチの上にホルスターが来ると邪魔になり、空マガジン処理にまごついてしまうため、ホルスター位置を下げた次第です。
ホルスターとダンプポーチで前面下は埋まってしまったので、左右サイドパネルと背面でM4マガジン、ラジオ、ユーティリティを賄わなければいけません。
そうなると中身を取り出せる位置にある必要があるマガジンポーチとユーティリティポーチが左右パネル、ラジオは背面にいくしかありません。
私は右利きなので、ゲーム中のマガジンチェンジを考えると左側にマガジンポーチを置きます。
CIRASの左右パネルは横4コマです。
4コマで5本以上収納でき、時代と部隊に合っているポーチを我が家で探したところ、SFLCSの200RD SAWポーチしかありませんでした。
このポーチであればM4マガジンが6本収納できます。
最悪4本携行でもゲームでそこまで不便はないのですが、実際のミリフォトを見ていると最低でも6本以上は収納できるポーチ構成(ダブル×3等)で構成している隊員が殆どなので、4本携行の装備はあまりリアルではないのかな?と思ったのもあります。
素早いリロードは難しいですが、基本遠距離戦を想定しているアフガンODA装備をモデルにしているのでまあ仕方がないところかなと。
サバゲでも実用的な装備を考えると、やはり市街戦やCQB等向けの短銃身のメインアームでオープントップマガジンポーチ、わき腹や背中がスッキリしている構成を再現するのがよさそうですね。
ユーティリティポーチは差し色とラジオポーチとの親和性を考えて、パラクレイトのGPポーチにしますが、まだ届いていないので暫定的にELCSを着けています。
先述しましたがラジオポーチもパラクレイトの物です。
一時は「高嶺の花」の存在でしたが、私はだいぶ落ち着いた頃に買いました。
今は更にお求め安くなってきていますね。今が買い時じゃないでしょうか。
SFLCSのラジポとは全然使い勝手が違いますので、隊員によって好みで使い分けていたのではないかと想像しています。
実際にパラクレイトのポーチはODAのミリフォトでも露出が多めな認識です。
アンテナはブレードアンテナをCIRASの肩部にぶっ刺しました。
これはCIRAS的には結構ポピュラーな収納法だと思いますが、アンテナの収納方法は個性の出せる箇所ですよね。
胸部にピストルマガジン×2とPTT、小物をくっつけて盛り付け完了です。
あとはカマボコ板付きのMICH2000にCOMTAC1、UCPに先述のODA3124パッチを貼り付けてオークリーのグローブを嵌めてFSN95を履いてBLOCK1のM4を持てばとりあえずナショジオODAの完成ですね。
まだまだ詰める箇所は多いですが、ひとまずこんな感じで久々に初期アフ以外のODA装備で次回のサバゲはいきたいと思います。
SFLCSはキットバッグまで買って結構集めていますが、今回を機に年代にも拘ってみようかなと思い始めました。
年代によって色も結構違いますしね。
幸いSFLCSは製造年月が書いてある場合が殆どなので識別はしやすいですし、最近だいぶ相場も落ち着いて来ているので色々見てみようと思う今日この頃です。
お読みいただきありがとうございました。