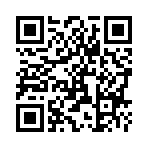スポンサーサイト
ハイザック 火力支援型

アフガンが大変な事になりましたね。
カブールの空港の様子はベトナム戦争終結時のサイゴンに重なりますね。




Zガンダムのジャブロー攻略戦時に、核の時限爆弾があると知り逃げ惑う連邦将兵達も全く同じ構図ですね。


まあこのシーンはベトナム戦争時のサイゴン退去の様子をモチーフにしたらしいので、似ていて当然なのでしょうが。
「ここにいたら確実に死ぬ」と思ったら、余程達観した人間でもない限り正常ではいられないのでしょうね。
私もその場にいたら、他人を押しのけてでも助かろうと藻掻くことになると思います。
タリバンと聞くと「厳格過ぎてヤバイ人たち」というイメージしかありませんが、今後どうなるんでしょうね。
個人的に興味深いなと思った考察記事を貼っておきます。
https://www.jiji.com/jc/v4?id=20210817world0001
きっと近い内に池上さんがTV特番で分かりやすく説明してくれると思うので、それ見て勉強しようと思います(笑)
タイムリー過ぎて不謹慎と言われちゃうかもですが、ミリオタ的にはタリバン兵の装備は少し気になりますね。
随分と西側チックな装備の人もいるようです。

右手に持っているのはU字スイングストックのAKだと思われますが、プレキャリにはSTANAGらしきマガジンが入っているのが謎です。
U字ストックでSTANAGマガジン対応のAKなんてあるのでしょうか?
AR系のライフルを携えている兵士も結構いるようで意外でした。


ちなみに一番後ろで右向いている黒ターバンの人は56-2式ですね。
ストックが特徴的なので判別が楽ですね。
PEQ2らしき照準装置をのっけている人もいました。
暗視装置まで使っているんですかね?上の写真の兵士はメットにNVマウント付いてますし。

それか我々が触るレプリカみたいに可視光レーザーのパチモンとかですかね。
ゴテゴテに盛られたAKも使ってたりします。

めっちゃ指トリガーですね(笑)
こうして大々的にメディアが入り込むと装備考証は捗りますが、直近サバゲで再現して着ていくのはかなりの勇気が必要ですね(苦笑)
では本題に入ります。
この度、ようやく1年戦争時代以外のガンプラを作りました。

昨年初夏頃にガンプラ復帰し、今まで30体以上作ってきましたが、ザクが全体の1/3、ジムが1/4、ドムグフで1/4を占めており、全て設定上1年戦争時に存在した機体しか作っていません。
ガンダムに至っては未だに1体も組んでいません(苦笑)
小さい頃は今よりはまだガンダム系も好きでキットもいくつか組んだことはあったのですが、今は全然食指が動きません。
今回もザクといえばザクですが、れっきとしたZガンダム世代の機体となります。
組んだキットは旧キットの1/100ハイザックです。
ガンプラ界隈ではしばしば「神キット」と崇められているキットです。
36年前に発売した旧いキットですが、今の時代でも通じる先進的な構造がふんだんに盛り込まれ、造形も古さを全く感じさせません。
どでかいバックパックが最高ですね。
フィンもしっかり可動します。
大人になって色んなMSのバックパックに非常に目がいくようになりました。
歳を取って異性の体の部位の好みが変わる話はよく聞きますが、MSの部位の好みも変わるものなんですね(笑)
ディテールも申し分なく、5本指独立可動や手首カバー、スリッパの前後独立可動等、現代のキット並に作り込まれたギミックに驚かされました。
可動も部分的には現代キットすら凌駕する驚異的な可動範囲を誇ります。
こんな股割り出来るキット、最新キットを含めても数える程ではないでしょうか。
邪魔な動力パイプがある割りには非常によく動きます。
スカートアーマーを別体化し、各関節部を少しだけいじればかなり動くポテンシャルは持っていると思います。
各関節も挟み込みながらPCで回転軸を保持する構造になっており、グリグリ動かしても削れてユルユルになってしまう事はありません。
足の付け根は現代キットでは標準的ですが、なんとロール軸があります。
35年以上前のキットに既にこの構造があったなんて本当に驚きました。
股関節の進化は、単純な軸差し→ボールジョイント→軸差し+ロール軸→軸差し+ロール軸+軸スイング、といった感じだと思いますが、このキットはボールジョイント時代に突入する前の発売のはずなので、完全に時代をすっ飛ばして先取りしていますね。
ちなみに足首もちゃんと関節が3軸(裏ワザ的に足首引き出しも入れれば4軸)あるので、無改造で綺麗なハの字立ちが可能です。
頭部はシンプルなモナカ構成で、モノアイはカバー状の部品にデカールを貼る方式になっています。

ここは流石に時代を感じたので、カバー部品は使わず脳天に軸を挿して回転するモノアイユニットを新造しました。
中身スカスカだったのでとりあえず艶消し黒で内側を塗り、下側に黒く塗ったプラ板で蓋をして真っ暗にしてごまかしました。
モノアイレールのディテールをスクラッチできる技術がある人がうらやましいです。
キットのカバーパーツは、UVレジン等でクリアパーツで複製すればそのまま透明のモノアイカバーとして成り立ちそうな構造です。
まさか当時そこまで見越した設計だったとしたら戦慄しますね(笑)
クチバシのダクトも左右で真っ二つで接着合わせ目消しでは対応しきれないので、一度くり抜いてプラ板で新造して置き換えました。
私は出来るだけ目立たない部分は手抜きしたがる性分ですが、頭部は細かい所も目が行きがちなのでここは少し手間をかけて作り込みました。
頭部以外はMGハイザックと並べても全く遜色ないというか、知らない人が見たらどっちの方が新しいキットか分からないレベルだと思います。
1200円でこのボリューム感と緻密感、噂に違わぬ名作キットだと体感しました。
ちなみにMGハイザックはこんな感じです。

顔の大きさはかなり違うので好みが分かれますが、その他は優劣つけがたい造形だと思います。
MGハイザックも隠れた名キットとして有名ですね。
今は品薄でバカみたいな転売価格が付いていて買う気起きませんが、いつかちゃんとした小売価格で手に入れて組んでみたいです。
ガンプラは基本的に絶版は無く、何十年前のキットでも再販を待てばいつか手に入るというのは希望があって良いですね。
旧い絶版初期アフ関連アイテムを集めている身からすると素晴らしい環境です。
箱絵もカッコイイですね!

全ガンプラ100円くらい高くなってもいいので、パッケージは全て手書きの情景風にして欲しいです。
MGは一部を除いていいですが、HGUCは発売当初から味気ないですし、プレバンは白黒印刷を即刻廃止して欲しいです。
何か深い意図があるのかも知れませんが、私のような凡人にはただのコストカットにしか見えずケチだとしか思えません。
店頭に並べないので豪華なパッケージで客の購買意欲をそそる必要が無く、質素なパッケージは合理的と言えば合理的ですが、商品が届いてワクワクしながら開梱して、出てくる箱がショボいのはやはり寂しいものがあります。
特にプレバン商品は買える時期が限定されるので、「とりあえず確保しとかなきゃ」で、永らく部屋に積んでおく方も多いと思います。
なので尚の事カッコイイ箱絵がいいなあと思うのですが、少数派なんでしょうかね。
ガンプラに限らず、中身が同じならパッケージは金を掛けず1円でも安い方が良いという向きは一定数あると思いますが、個人的にはパッケージ含めて「その商品」と思うので、ちゃんと力を入れて欲しいなと思います。
最近ではSDGsという言葉が流行っていますので、逆にしっかり作り込んですぐ捨てるのではなく、「商品の一部」として永く使えるパッケージにした方が時代の潮流に合う気がします。
その点、マルイのAKMはパッケージがそのまま銃のカバーに出来るようになっていて面白いなと思います。

話が脱線してしまいましたが、キットを見ていきます。
超優良キットなので、ゲート処理や合わせ目消しを丁寧にして素組みでも全然良かったのですが、せっかくなので手持ちの在庫パーツをやり繰りして、下記のようなちょっとしたオラ設定を付け加えました。
連邦宇宙軍所属機で、旧ジオン軍から接収したビームバズーカを装備し、中距離火力支援を担当する機体です。
ハイザックはグリプス戦役勃発前、対ジオン残党の不正規戦に対応する設計思想で開発された為に、大規模な艦隊戦向きの武装開発は重視されていませんでした。
しかしグリプス戦役が勃発し組織的な艦隊戦に対応できる武装が急遽必要となり現地改修された機体、といった妄想を発端にしたオラザックです。
ベースが超名作機のザクⅡなので、その遺伝子を継いだハイザックも、本来想定されていなかった武装運用もお手の物だったはずですね。
ちなみに、一応ハイザックも対艦用?兵器として2機1組で運用する大型メガバズーカランチャーが劇中で登場します。

自分の体よりも大きく、1機分のジェネレータでは駆動できないので電源用としてもう一機随伴が必要という、ちょっと運用が特殊過ぎる兵器です。
「電源用にもう一機必要」という野暮った過ぎる設定は個人的にかなり好みではありますが(笑)
本機はそれよりも低威力短射程ですが、単機で十分な柔軟性を持った運用が出来る、という位置づけで妄想しました。
この旧ジオン軍製ビームバズーカは、開発当時から巡洋艦の主砲並の火力を有するので、想定される運用上威力は十分と判断し、作動安定性のみチューンナップされ出力の増強は施されていません。
1年戦争期のMSよりも高性能のジェネレータが搭載されているハイザックが装備する事でチャージ時間の短縮が実現しており、単位時間あたりに発揮できる火力は大戦期のジオン製MSが扱うより増加しています。
ジオンの兵器にEFSFマークを貼るのって、なんか背徳感ありますね(笑)
鹵獲繋がりで余談ですが、高校生の頃ゲーセンである日突然「連邦VSジオンDX」で「鹵獲モード」が解放され、ドラえもんみたいな色のジオンMSを見た時は衝撃でした。

ちょうどHGUCアッガイを家に積んでいるので、今度作ってみようと思います(笑)

ビームバズーカはMGリックドムから持ってきました。
実は以前リックドムを作った際に、誤発注でリックドムが2機届いてしまいました(笑)
一機は制作済で、ビームバズーカはディテールダウンして旧キットのドムに持たせました。
「ドム→リック・ドム換装機」

「旧キット 1/100ドム」

もう一機は全然制作モチベが上がらなくて困っているのですが、とりあえずビームバズーカは今回のハイザックで供養できました。
バズーカのグリップがかなり太いので、握らせる為にハイザックの指関節を第一関節で一度切り離し、開かせて表情を付けて再接着しました。
手首って小さい部分ですが意外と全体の印象に大きく関わってくるので、いつもちゃんとしようと力を入れて取り組んでいます。
残念ながらキットの指の保持力ではとてもこの巨体を握って保持は出来ないので、グリップと掌はスーパーXで接着固定しました。
肩に担がせる為の改造は手首の傾きを大きくする為に袖口を少し削り込んだくらいで、ほぼ無改造でいけました。
この辺り、本キットの懐の深さを感じました。
バズーカ運用に邪魔な右肩シールド、左肩スパイクは外しています。
右肩はバズーカの保持安定と肩関節への負担を軽減させる為にショックアブソーバーを装着しています。
MGジム・スナイパーカスタムの余剰部品を使い適当にでっちあげ、ハイザックのシールド接続部をそのまま流用し接続しています。
デフォルト装備のハイザックは、一年戦争を戦い抜いた生粋の連邦パイロットにとって「いかにもザク然」とした外観が不快で、ザクの象徴でもあるスパイク等の装備を外す事は茶飯事だったかもと妄想しました。
今回の制作にあたり最初の構想時は、「ザク頭も嫌で頭部をジム改かジムⅡあたりに換装した」というのも面白いかなと思ったのですが、同じような考えを持っている方は私の他にもいたようで、ネットで下記画像を拾いました。
思っていたよりめちゃくちゃサマになっていて驚きました。
このセンス抜群で完璧と言える作品を見て満足したというか、これを越えられる自信が完全にゼロなのでジムヘッド案はボツにしました。
ハイザックはジオン系列MSの駆動形式である流体パルスシステムと、連邦系列のフィールドモーターシステムのハイブリットという設定です。
量産機で駆動方式を2種積むなんてなんかムダに贅沢じゃね?とは思いますが、その設定のおかげでジムヘッドでも納得が出来ます。
今回キットを制作するにあたり、ハイザックの事を色々調べて勉強しましたが、かなり面白い立ち位置のMSですね。
アニメの都合上、ガンダムと相対する敵役としては一つ目のザクが分かりやすいですが、Zガンダムは連邦軍内の組織抗争が舞台です。
なので連邦軍なのにザクがいる、という歪な設定する必要があったそうです。
戦後アナハイムエレクトロニクスがジオンの技術を吸収し、ザクⅡの生産ラインを活用し連邦技術と融合して生まれた機体、という無理があるんだか無いんだか絶妙な設定が付随しています。
カラーリングに関しては、ティターンズの正式カラーは元々のザクに似た緑色ですが、アニメ的な理由は「ガンダムの敵として分かりやすいから」ですが、(多分後付け)設定上は「ジオン残党に対して心理的効果を与える為」という、これまた無理があるんだか無いんだかな絶妙な設定があります。

この辺りの設定は後作品の0083に反映されているのかもしれませんね。
トリントン基地強襲時に、連邦のF2ザクを見たジオン残党兵ゲイリーが「連邦に下ったその姿、見るに忍びん!」と言って両断するシーンは有名ですね。

ジオン公国軍の象徴であったザクは、ジオン将兵にとっては一際特別な存在だった事を伺わせ、上記のティターンズハイザックカラーの裏付けとして読めなくはありません。
ちなみに連邦カラーはこれまた絶妙な色合いです。

ジムと同じ胴体赤、手足白にしないあたり、アニメの都合なんでしょうかね(似たような色のMSばっかりだと見栄えしない)。
目視確認が重要な戦況判断材料になる宇宙世紀の戦場をリアルに考えれば、当然似たような色で統一する方が良いとは思います。
そんなアニメの都合と陣営設定の歪みの狭間で生まれたハイザックに思いを馳せながら、制作に勤しみました。
バズーカを撃ち尽くした後や、不意の接近戦となった場合の自衛兵器として、ジム用の二連装ビームガンを腰に装備しています。
パイロットは1年戦争時から連邦軍のMSパイロットとして従軍し、ジム・スナイパーカスタムから本機に乗り換えている為、当時から使い慣れているビームガンを使用しています。
近接武器も使い慣れたビームサーベルを使いたいところでしたが、ハイザックの泣き所である「出力の関係で2つのビーム兵器の同時駆動は不可」という制約の為、泣く泣くヒートホークを装備しています。
この制約も「ザクなんだからヒートホークだろ」というアニメの都合の産物なんですかね。
ハイザックが生まれる5年以上前に既にジムとかゲルググがビーム刃を出しながらビーム兵器撃ちまくってるのに、ハイザックが出来ないなんて冷静に考えると不自然過ぎですよね(笑)
ヒートホークは1部品構成でがっつり肉抜き孔が入っていて、もうちょっと凝って欲しかった思いはありますが、キットの価格を考えれば十分な完成度だと思います。
MGハイザック1体分+数百円のお金でこっちは3体買えてしまいますからね。
ヒートホークは磁石を埋め込んで背面腰部に付けられるようにしました。
ただ、バックパックとの位置関係をあまり考えずに磁石配置してしまったので、干渉してしまっています(汗)
カラーリングもパイロットの意向で以前の愛機のスナイパーカスタムをオマージュしたものにしています。
本当は正式連邦カラーのハイザック色に塗りたかったのですが、あの絶妙な青紫色を出せる塗料が無く、泣く泣く諦め悩んだ末に「元スナカス乗りだったパイロット」という苦し紛れの設定をしました。
キット自体は頭部以外ストレート組みですが、ボリューミーなガチムチ体型は今の目で見ても十分イケてると思います(ほんの少し頭デカい印象ですが、好みの範囲かと)
MG並に部品数が多く、組み応えがありました。
後ハメは各箇所かなり悩みました。
というかほぼ後ハメ化できず、完全に組んだ後だとマスキング塗装も難しい箇所が多かったので、まずバラバラの部品単位で塗装した後組み立てて合わせ目を消し、合わせ目消しした部分だけマスキング塗装、という工程で凌ぎました。
各部の動力パイプも挟み込み構造ですが、これは嵌合部を一部切り取る事で簡単に後ハメ化出来たので助かりました。
動力パイプが後ハメ化できなかったら心折れてたかもしれません(笑)
缶スプレー基本塗装、細かい部分はエナメル筆塗りで塗り分けしています。
塗装→デカール→艶消しクリア→ウォッシング、スミ入れ→艶消しクリア→ドライブラシで完成です。
これが35年以上前に発売されていたとは、にわかには信じられません。
そして部品数の多さにびっくりです。片方の足首だけで16パーツもあります。
初期~中期のMGより多いのではないでしょうか。
説明書も詳細解説が付いて読み応えがあってお得感があります。
もちろん最新のキットに比べれば構成の古さや部品精度の低さを感じますが、発売時期を考えるとまさに「オーパーツ」と言っても過言ではないキットですね。
当時設計された方は天才か、もしくは未来人だと思います(笑)
現状品薄な感じですが、あまり人気は無いのかオークションサイト等に出ても定価+α程度が相場のようですね。
元々がバリューが超高いキットなので、数百円上乗せ程度だったら入手しても十分満足できるとは思います。
成形色分けも優秀なので、素組みでも十分見栄えするという点でも時代を超越した異様な完成度のキットだと言えると思います。
ある程度子供が大きくなったら、さりげなく見える所でガンプラ拡げて作ってみせて興味を持たせ引きずり込みたいですが、それで私のようにニッチなオタクになってしまうのもそれはそれで生きづらそうなので、悩む所です(笑)
いずれにしても、こんなに毎日自由気ままにガンプラいじっていられるのは、今の中国赴任が終わったら次は20年30年後だと思いますので、今の内に飽きるくらい触っておこうと思います。
お読みいただきありがとうございました。
1/35初期アフの世界

マルイのガスブロAKM、かなりイイ感じの出来のようですね。

現物はまだ見れていませんが、写真や動画でもマルイの本気度が伝わってきます。
久しぶりにワクワクするマルイのトイガンです。
実射性能はお墨付きでしょうし、耐久性も過去機種を見る限りGBBとしては非常に高いと思いますし、これから大量のカスタムパーツが出てくると思うと楽しみですね。
とりあえずまずはどこかが無加工で着く合板ストックを出してくれれば、というところでしょうか。
あとは手軽にCO2化出来るようになったら、マテリアルと(リアルさという観点においての)構造以外はほぼ完璧と言えるのかもしれませんね。
私はクリンコフが出る事を見越してAKMはスルーしようと思っていますが、どこかでうっかり現物を触ってしまったら買ってしまうかもしれません(笑)
もうすぐ発売の次世代MP5も新要素たっぷりですが、仕様は変に近代化させずオーソドックスな仕様となっていて好感が持てます。
マーケティング担当の方が変わったのでしょうか??

本体はもちろん、マガジンの外装もかなり期待できそうですね。
BB弾を散布するおもちゃにはしゃいで数万円も出せるのは、ある程度経済的に余裕のあるオジサンがメインでしょうから、90年代の銀幕で輝いていた銃をモデルアップする事は良い選択なんじゃないかな?と思います。
私は30代半ばですが、小学生の頃にテレビでダイハード1、2を見てMP5が大好きになりました。
チャーリーシーンのネイビーシールズあたりでMP5に惚れた方も多いんじゃないかと思います。
そんなオジサンホイホイともいえるMP5、しっかり売れてバリエ展開や往年の名銃リバイバルの流れが出来てくれると個人的には嬉しいです。
私はこのMP5は絶対買います。
今回AKMで得た外装再現度の信頼を、MP5で完全な物にしてくれているといいですね。
では、そろそろ本題に入ります。
通販サイトを漁っていると初期アフODA隊員の1/35キットが手ごろな価格でゴロゴロ売っていたので、買ってみました。






2002、3年頃の19thや20th SFGをモチーフにしているっぽいですね。
EVOLUTION MINIATUREというメーカーのキットです。
URL:http://www.evolution-miniatures.com/
日本にも正規販売店があったりして、一応世界的に流通しているメーカーのようです。
日本での販売価格を見るととても買う気がしない値段でしたが、こちらで日本相場の1/10以下で売っていた(1体数百円)ので、試しに買ってみました。
届いた状態がこんな感じで、パッケージも何もありませんでした。
ランナーを見れば分かりますが、キャスト(鋳造)キットですね。
いわゆるガレージキットと呼ばれる物です。
日本で一般的に流通しているタミヤのプラモやガンプラは、ほぼ全てインジェクション(射出成形)キットです。
キャストキットは所謂「鋳物」です。
原型から型取りした金型を合わせた状態にして一部穴を空けておき、そこから樹脂を注ぎ込んで金型を満たし、硬化した後に金型を開くと完成です。
型のイメージとしてはこんな感じです。

語源の通り、個人のガレージで作れてしまう程単純な加工です。
インジェクションは射出成形機という機械に金型をセットして、シリンダ内で熱で溶かした樹脂を射出機で金型に押し込んで満たします。
樹脂が冷えて固まったら金型を開いて成形品を取り出して完成です。


ガレージキットとは対照的に、とても個人レベルでは所有管理できない設備が必要です。
金型も相応の設計、加工技術と設備が無いと造れず、ガレージキットとは比べ物にならない程高額です。
世の中の様々な樹脂製品がこの成形法で作られていますね。
「スライド」と呼ばれる構造を追加すれば、単純な上下割りでは出来ないより複雑な形状も高精度で成形可能です。
上記の特徴から分かる通り、キャストの方が少量生産向き、インジェクションの方が大量生産向きになります。
キャストの方がインジェクションに対して、生産可能になるまでに必要な設備や時間、初期費用が安いですが、一個当たりを生産する手間暇は非常に大きいです。
なので、最初にお金は掛かるけど機械で1分に1個レベルで大量に作れるインジェクションキットに対して、キャストキットは1個1個手作りなので異常に高額になります。
純粋に造形や構造、体積だけ見たら、こんな単色でどこも動かないちっちゃいおっさんのフィギュアが、カラフルな数十のパーツで構成されて関節動きまくるガンプラの数倍の値段がするなんて何かの間違いだと思いますよね。
ただ、こんなニッチなおっさんの人形をガンダムのように何十万、何百万個作ったところで在庫の山必至なわけで、需要と供給を考えると高額なガレージキットで極少数展開するのが正解だと思います。
プラモに限らず、出来上がるまでの経緯(工法、商流等)をちゃんと分析すれば、その商品がどこにコストを掛けているのかの判断材料になりますよね。
話が逸れましたが、今回入手したキットがガレージキットにしては破格なのは、もしかしたら正規の製品から更に型取り複製したものだからかもしれませんね...。
数千円で原型となる製品を買ってくれば、あと必要な物は金型の材料と簡単な工具と成形材料と大人1人の人手のみで、慣れていれば1日2日もあれば量産開始できます。
多分20体も作って売れれば元手はペイするのではないでしょうか。
もちろん日本でこれをやったら完全に違法ですが(笑)
中国の法律は詳しくないですが、もちろんきっとダメでしょう。
これもその可能性はありますが、調べようがないのと、もう手に入れてしまったのでこれ以上深く詮索しても私に何も得は無いのでここまでにします(苦笑)
ちなみに日本の模型ブログやTwitter等でも、買ってきたガンプラの部品を型取りして複製している方をよく見かけますが、複製しても個人使用する分には合法という認識です。
私も過去、ガンプラではないですがANVISのグラウンドアダプターを実物をBucket Head氏に借りておゆまるで型を取り複製しました。



当時は今のように安価なレプリカが無く、出処不明の高価なレプリカか実物を買うしかありませんでした。
その時期に数百円の材料費で複製品が作れたのは大変ラッキーでした。
複数複製し、壊れた時の予備まで確保できました。
では、そろそろキットの詳細を見ていきます。
最近のタミヤ等の1/35キットをまじまじと見たことは無いですが、ディテールはまあいい線行ってるんじゃないでしょうか。
どうしようもないヒケやバリ、変形は無く、私の技術でも何とか修正できそうです。
問題は塗装ですね。
DCUやBALCSを着用しているので、1/35サイズでウッドランドや3C迷彩を筆塗りしないといけないという苦行が待っています(苦笑)
ただ、これらのフィギュアが身に着けている装備品はほぼ全て1/1サイズの実物を所有していますので、見本は完璧です。
中国にいる内に出来るところまでは進めて、各種装備の塗装等の細部の仕上げは日本に帰って実物をじっくり見ながら進めようと思います。
一体一体装備品をチェックしていきましょう。
まずはこの隊員です。

髭の感じといい、バンダナにゴーグルをはじめ各種装備といい、モロにODA961のcowboy氏がモデルでしょう。


ポーズまでミリフォトとほぼ一緒ですね。
ベストはイーグルのV1ベストかBHIのオメガベストを模していますね。
Cowboy氏はV1でいうNU仕様で右側下部はユーティリティポーチなのに対し、キットは通常のマガジンポーチ仕様ですね。
実物V1NU

氏のベストと言えば、サイドの調整部が初期型の紐式の個体をバックル式に改造しているのが有名な特徴ですよね。

残念ながらこのキットではそこまでは再現されていないようですが、ハトメが見えるので初期型を再現しているように見受けられます。
ここが再現してあったら神キットと言えたかもしれませんね(笑)
また、cowboy氏はベストの左側マガジンポーチにEAGLEのオープンピストルマガジンポーチを着けていました。

これも残念ながらキットでは再現されていないようです。
ハイドレーションホースをベストのポケットに突っ込んでいるのは再限度が高く素晴らしいディテールだと思います。

ハイドレーションは全面にMOLLEがあり、フラップの先端にタブが付いているのでBHIの物がモデルでしょうか。

ラジオポーチは造形が崩れている事もあり判別不能ですが、おそらく2000年代に登場しているTAC-TかBHIあたりの物だと思います。
無線機はアンテナの形状からPCR-148だと思います。
まあcowboy氏はミリフォトではハイドレーションはベスト内蔵のポケットに収納、ラジオはベストのマガジンポーチに入れている認識ですが、これはこれで自然なセットアップだと思います。
ホルスターはcowboy氏はEAGLEのMk.Ⅵの旧型ストラップ仕様を使っていましたが、キットはサファリの6004を模しているようです。

EAGLE Mk.Ⅵ

左足もELCSの3MAGポーチをカスタムした?詳細不明のポーチを使用していましたが、キットでは一般的なM4マガジンポーチを装備しています(おそらくBHIかEAGLE品)。


頭部は官給三角巾にBOBSTERのゴーグル、RACALのアーバンと完璧な再限度です。
顔も似てますね。
M4はCQBRレングスのバレルにクレーンストック、M900、TA01と、実際のcowboy氏のミリフォトに見るセットアップとは全然違います。
しかもハイダーがCAR15のように妙に長いです。
1/35のM4なら別キットでも多く出ていそうなので、ここは氏のセットアップに近いM4に持ち替えさせたいところですね。
手首を切り離すのが大変そうですが。
あとはベストの下にABAのソフトアーマーを着ていればかなり点数高いですが、このポーズでは見えないので問題ないですね。
少し鉄板とは離れているアイテムがあるものの、初期アフODA隊員の特徴を見事に再現していると思います。
次です。

DCUハーフパンツにM24と思しきスナイパーライフルを携えています。
商品画像の左下に実際の映像が貼ってありますが、これは初期アフドキュメンタリー番組「Profile From The Front Line」に出てきたMIKE大尉でしょう。



この時のMIKE大尉の装備と下記写真を混ぜたような感じのキットですね。

56式弾帯+BALCSという王道ファッションに身を包んでいます。
装備的にBALCSは作例の通りウッドランドに塗るのがリアルだと思います。
BALCSは側面バックルの形状や背面ウェビングの数もしっかり再現してあります。
丈の感じも完璧ですね。
56式弾帯の腰紐は残念ながら結んでしまっていますね。
皆さんご存知だと思いますが、当時流行りの初期アフファッション的にはここは結ばないのがトレンドでしたね(笑)



惜しいところですが、キットで垂れ下がっている様子を表現するのは難しそうなので仕方ないといったところでしょうか。
ハイドレーションは官給品を模していると思われます。
ブーツはOAKLEYのアサルトブーツっぽいデザインで、ナイスチョイスですね。
DCUパンツのポケットに物を突っ込んでいるのもリアルでいいですね。
成形色だと何だか分からないので作例を見ると青く塗られていて、ますます何なのか分からなくなりました(苦笑)

ハゲちゃびんなのは塗るのが楽で助かりますが、重ね着しているBALCSをウッドランドに塗るのは至難の業ですね。。
精進します。
他にもあの人のオマージュと思しき頭部のキットがあったりして中々面白いです。


全キャラ紹介するのは果てしない&同じような内容ばかりで飽きるのでこの辺で終わりにします(笑)
今後実際に制作に着手したらじっくりご紹介できればと思います。
どのキットもかなりよく初期アフODAの特徴を捉えており、ミリフォトをただ見るだけでは再現出来ないような所も再現しているので、関係者の方はかなり初期アフODAに精通していたんだと思います。
せっかく何体も揃えたのでヴィネットにする事が野望です。
じっくり腰を据えて、コツコツとプラモスキルを鍛えつつ取り組んでいきたいと思います。
お読みいただきありがとうございました。