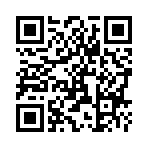スポンサーサイト
AK-47 ウェザリング加工
先日、自衛隊の新型小銃がお目見えしましたね。

SCARを彷彿とさせる近代的なフォルムで、89式から一気に進化した感がありますよね。
運用していく中で色々と改善点は出てくると思いますから、それに対応できるポテンシャルがあるかどうかが真価を問われるところだと思います。
M16系だってAK系だって、数多のバトルプルーフを潜り抜けて今の姿があるわけですからね。
日本は他国に比べて実戦の機会はほぼ無いとは思いますが、日本人らしく勤勉できめ細やかなフィードバックをして、世界に誇れる立派な「国産小銃」になって欲しいですね。
ちなみにメーカーである豊和工業は、玩具としてもこの20式小銃の意匠登録をしているらしいですね。
という事は、早々にマルイあたりから公式ライセンス電動ガンが発売されるかもしれませんね。
自衛隊の訓練用としての需要も既にあるでしょうし。
マルイの89式は以前所有していて、KTWの三八式歩兵銃は今も所有していますが、「日本人が作った日本人の為の小銃」ということもあって、どちらも初めて持った時から自然と体にフィットしました。
きっと20式もSCARやACR等に比べて、日本人の体格になじみやすいんでしょうね。
トイガン化されたら是非一度手に取ってみたいものです。
ところで読み方は「にいまるしき」でいいんでしょうか。
海自も採用したら、そっちでは「ふたまるしき」になるんでしょうかね?
そうなったらややこしいですね(笑)
それでは本題に入ります。
前回記事にしましたが、先日次世代コピーの電動AK-47を入手しました。


箱出しでは外観に不満がありましたので、ウェザリング加工をしてリアル化をはかりました。
トイガンのウェザリング加工は多くの先人達が挑戦しやり方を上げてくれていますよね。
かの所ジョージさんも各種雑誌やTV番組「世田谷ベース」で加工したトイガンを紹介されています。
プラモデルの技術も応用できますので、プラモ雑誌等も参考になりますよね。
砂や泥汚れを装備品に施す魔法の棒「タミヤウェザリングスティック」もプラモデル用品ですね。

今回、全快娘さんの記事を参考ベースにしました。
URL:https://zenkai.militaryblog.jp/e592345.html
全快娘さんのブログはエアガンや装備等、本当に色々な工作にチャレンジされていて面白いですよね。
初期アフ関連も物凄い数の記事があるので、初期アフファンなら一度は通った事があるのではないでしょうか。
更新が止まって久しいですが、今でも時折勉強させていただいています。
基本は下地作り→銀色塗り→黒色塗り→黒色剥がし、です。
ストックは私の買ったAKは木製ストックなので、全快娘さんの手法ではなく独学で加工しました。
まずは材料調達です。
中国の大手通販サイト「京東(ジンドン)」で塗料、工具を買い漁りました。

中国語を調べながら商品検索し、下記を揃えました。
・スプレー塗料(黒、銀、クリア)
・紙やすり(各種番手)
・木材用オイル(着色有り)
・刷毛
値段はどれも日本の半額以下といったところで、安いですが品質は不明です。
とりあえず無事材料は揃ったので、加工開始です。
乾燥に時間の掛かるストックから取り掛かります。
まずは紙やすりで一皮むきます。
#240から始めて、#400、#600、#1000と掛けていきます。
家具並みに仕上げるなら#80辺りから初めて最終的に#2000くらいまでやった方がいいのかもしれませんが、所詮AKなので適当仕事です。
ペーパー掛け後の写真は撮り忘れました。。
次にハンマーでへこませたりカッターで傷付けたり、ドライバーで細かい穴を空けたりとダメージ表現を加えました。
その後、オイルを全体に薄く塗り拡げます。
塗った後は余計な油分を布で拭き取ります。
数十分放置するとまた油分が滲み出てくるので、都度拭き取ります。
塗った直後はテカテカしていますが、何度か拭き上げしているうちに落ち着きました。
塗った直後
拭き上げ乾燥後
良い感じになりました。
傷や凹み、掠れも適度に加えつつ、オイル塗りを繰り返せばもっと深みにのある趣になっていくと思います。
木製ストックの仕上げはかなり簡単なので、非常におすすめです。
簡単なのに一気に雰囲気が増しますし、愛着も湧きます。
サバゲ等で傷が付いても、ささくれをやすりで均して上からオイルを塗り直してメンテすれば「歴戦の傷」となっていきます。
オイルを塗る度に深みのある色合いになっていきます。
日本では「ワトコオイル」が入手性、品質、価格のバランスが取れていると思います。

色展開もかなりあるので、複数色揃えてブレンドするとより深い質感になります。
匂いも良いですし、家具のメンテにも使えます。
仕上げをやり過ぎ、レシーバーとフロント部のウェザリング具合と大きく違ってしまうと不自然になってしまいます。
今回のウェザリングは不可逆加工なので、ひとまず1回処理した時点で終了とします。
レシ―バーの加工後にまだバランス的に使用感が足りないようであれば、様子を観ながら追加工します。
次に木製ストック以外の部分に手を付けます。
まずは銀色に塗装する前に「足付け」を行います。
車の塗装では常識的な加工のようですね。
紙やすりで表面荒らす事で、塗料の食いつきを良くする工程です。
ついでにボディ各所にある成形ヒケも均そうと思ったのですが、パテ盛りしないと均せないレベルのヒケなので諦めました。
同じくパテが無いので右側面にでかでかと入った「MADE IN CHINA」刻印も埋められませんでした(涙)
パテか硬めの瞬着があればこんな刻印余裕で消せるのに、悔しいところです。
#400から初めて、#600、#800までやって終わらせました。
プラモと違って細かいモールドやダレを気にしなくていいので、AKのような元が粗い作りの銃は余計な神経を使わず楽ちんです。
治具等使わず、素手でペーパーを持ってガシガシ擦りました。
トイガンは1/1ですが、戦車は1/35、ガンプラに至っては1/100や1/144が基本です。
スケールモデルは1mm削り間違えると、スケール上は3cm~14cmもおかしなことになる訳ですからね。
金属パーツも塗装を剥がし切るのが面倒だったので、適当に終了です。
中性洗剤で洗浄しカスと油分を除去、乾燥させた後、スプレー塗料を塗っていきます。
車用?の、おそらくラッカー系の塗料を調達しました。
スプレー塗装は焦らず、薄く塗り重ねていくのが基本ですよね。
家事や食事を一通り済ませた、一番精神が安定している休日の午後にやりました。
フロントアッシーは何気に細かい部品が多くてバラすのが面倒だったので、塗料が入っちゃまずそうな所をマスキングし、外観に出るところだけ塗りました。
銀色を塗った後、2時間程空けてクリア塗装、その後また2時間程空けて黒塗装しました。
クリアを吹いた目的は2つあります。
・銀色塗料がザラザラした質感なので、滑らかにしてツヤ感を揃える為
・後から黒塗装を剥がすのですが、勢い余って銀塗装まで剥がさないようにする為
黒まで塗り終わった時点の質感はこんな感じです。
思ったより良い感じの質感が出ました。
シリコンオイル等で油っぽさを足せば、新品の塗装仕上げAK(AKM以降のロシアンAK等)っぽい質感にできそうです。
MADE IN CHINA刻印とセレクター下あたりの壮大なヒケが残念ですが、埋める材料が無いので致し方なしです。
塗料が完全乾燥したら、メインディッシュの剥がし工程です。
様々な番手のペーパーやメラミンスポンジ(激落ちくん等)で黒塗装膜のみ削り落とし下地の銀色を露出させ、使用に伴う擦れや傷を表現します。
剥がし工程は細心の注意と、剥がす箇所のセンスが問われる作業です。
剥がしをする前に、実銃のAKの写真をじっくり観察していきます。



実銃写真を見てイメージするとしないとでは、出来上がりの「っぽさ」が各段に変わってきますので、重要な作業です。
また、一口に「使用感のあるAK」と言っても、AKはバリエーションによって表面処理が異なるので、使用感の出方が異なります。
そのあたりを書いていたらとても一記事のボリュームではなくなってきたので、今回は一旦ここで終了します。
次回、続きを書いていきます。
お読みいただきありがとうございました。
劣化した防水コートの除去
日本はお盆休み真っただ中ですね。
こちらは通常稼働中ですが、日本から電話もメールも来ないのでマイペースで仕事ができるので、これはこれでいい感じです。
国慶節休みまであと1ヵ月半頑張ります!
今回は久々にちょっとしたDIY小ネタになります。
先日記事にしましたが、先月香港に遊びに行った際にポーチをいくつか入手しました。
今回、左3つのELCSのレプリカポーチに手を加えます。
この3つのポーチですが、生地の質感はまるで本物同様で、縫製もしっかりしており非常に好感が持てます。
裏側のタグが無い事を見なければ実物と見分けるのも結構難しいレベルだと思います。
1個500円程度でしたので良い買い物でした。
が、なんとこのレプリカ、内側の防水コートまでちゃんと加工してあり、しっかり加水分解までしていました(苦笑)
見た目ではわかりませんが、触るとベタベタで特有の甘い臭いがします。
これではマガジンや小物を入れるのは嫌なので、今回このベタベタ除去トライしました。
ウレタン樹脂で防水コートを施している製品は軍用品のみならず、現代のアウトドアギアでも非常に多くみられます。
なので防水コートの劣化で悩んでいる人は旧装備ミリオタという極少数民族だけではないので、ネットで調べると簡単に対策が見つかりました。
作業は簡単で、ぬるま湯に重曹を溶かしてそこに漬け込むとベタベタが取れるそうです。
メカニズムはちゃんと調べてないのでよく分かりませんが、劣化したウレタンコートは酸性で重曹はアルカリ性なので中和されるそうです。
重曹なら今住んでいる街でもあるだろうと思い、近所のスーパーに赴き入手しました。
別にわざわざ高価な日本製じゃなくてよかったのですが、これしかありませんでした。
中国の地方都市でくまモンに出会うとは夢にも思っていませんでした。
材料はこれだけです。
ついでにミリ以外のアイテムも一緒に投入してみました。
グレゴリーの旧ロゴのパック達です。
彼らも内側が日焼けした皮膚がむけたようなボロボロ膜といやーな臭いを醸し出しております。
ベタベタはせずボロボロ剥がれてもこないので使用上問題はないのですが、臭いと見た目があまりよろしくないので改善トライです。
グレゴリーは旧ロゴの方が圧倒的に好きなので、まだまだ快適に使えるようにしたいところです。
幸い私の宿泊しているホテルにはバスタブがありますので、そこにお湯を溜め重曹を適当に溶かし、ポーチ達を漬け込みました。
写真撮り忘れてしまいましたが、1時間程度すると水が茶色く濁ってきました。
日本の自宅だったら確実に妻に文句を言われる光景でしたので、単身赴任してきてよかったです(笑)
途中お湯と重曹を継ぎ足しながら5時間程漬け込み、最後に流水で流して取り出しました。
外観はなにも変わりませんでしたが、ポーチの内側を触ってみると見事にベタベタが無くなっておりました。
これで気兼ねなくマガジンを収納できます。
3C SPEARも少しずつ増強できてきましたので、ようやく初期アフ3rd SFG装備も自由度を出せそうです。
グレゴリー達は真っ茶色になった膜が取れ全体的に薄くなり、一番気になっていた臭いは皆無になりましたのでひとまず成功です。
これでまだまだ快適に使えそうです。
こちらにいると触れるミリタリーアイテムが皆無で写真や画像を見るくらいしかミリ活動ができませんが、久々に現物を触って遊ぶことができ細かい内容ですが満足しました。
デモが落ち着いた頃にまた香港に足を運んで何か手に入れたいと思います。
お読みいただきありがとうございました。
初期アフ無線IC-F3S風 特小無線機運用

来年2月にとても楽しそうな貸切ゲームにお誘いいただきましたので、今からぼちぼち準備を始めようと思います。
ご本人も既に宣伝しているようですので、ここでも載せておきます。

「GEAR FREAKS GAME」、略して「ギアフリ」ですかね。
かっこいいポスターですね!ちゃっかりした人の仕事でしょうか?
今年50回以上(内2回は東北遠征)はサバゲをしていると思われる、正真正銘のサバゲジャンキーであるぽん太先生主催のゲーム会です。
「装備好きならではの、ちょっと凝ったゲーム会」がコンセプトのようです。
ご本人曰く「ギアフェスリスペクトのゲーム会にしたい」とのことでした。
ギアフェス(ギアログ)というと、ここ一年は系譜イベント「ユルゲ」の連続開催により「装備好き同士の交流メイン(=ダベり)イベント」というイメージがあるかもしれませんが、ギアフェス(ギアログ)は毎回ゲームシステムが非常に凝っていて、ゲームそのものもすごく楽しいです。
そのギアフェスのDNAをリスペクトし、ぽん太さんアレンジの「装備好きがゲーム重視でサバゲ&交流を楽しむ会」ときたら、春を待たずして、新年号を待たずしてヴァイブス大炸裂は免れませんね!
現在、絶賛プロジェクト計画中のようですので、もし気になる方がいらっしゃったらぽん太さんのブログ「ANNUAL LEAVE」やツイッターを随時チェックしてみてください。
宣伝はこのくらいにして、そろそろ本題に入ります。
ギアフリでは無線装備推奨らしいので、この機会に永らく放置していた初期アフ装備での特小無線の運用を考えました。
順番が前後しましたが、当然私は初期アフODA装備で参加予定です(笑)
私の手持ちのPRC-148はトライス様で特小&実コネクタ加工をしていただいているのですが、初期アフに合う特小加工済みのヘッドセットがありません。
上記写真のように実物RACALアーバンは持っているので、ショップに特小加工に出せば多分間に合うのですが、DIYでローコストで手軽なアイデアを思いついたので先にそちらを実践してみました。
初期アフODAはPRC-148の他に、分隊内通信用にソルジャーインターコムというシステムを運用しており、そのシステムの無線機がIC-F3Sでした。

キットにはIC-F3S専用ポーチも付属していたようです。
私も同型を持っていますが、メーカーや製造年は不明で果たしてキットの物なのかは分かりません。
まあぱっと見同じなのでよしとしています。
ちなみにコレにそっくりな見た目でIC-F33/44用の少し小ぶりなポーチもあるので要注意です。
このポーチだとIC-F3Sを入れるとバックルが閉まりません。
私は知らずにこっちを先に手に入れ、F3Sが入らなくて「専用ポーチなのに何故入らない!?」と、ハズキルーペのCMの渡辺謙ばりに絶叫しましたが、東北の心のアニキTJ1さんに教えていただき、無事F3Sサイズを手に入れ事なきを得ました。
F3Sは裸でBALCSに引っ掛けていたりする運用も多く目にしますが、ちゃんとこのポーチに入れて運用している例も見かけます。


ポーチに入れてしまえば、アンテナだけしか見えませんね。
なのでアンテナだけF3Sのものを出し、ポーチの中身は特小無線機を入れれば外観はF3S同様にできます。
アイデアは固まったので、後は工作あるのみです。
早速ダンボールとガムテープで切った貼ったし、予備のアンテナを使ってこんなモノを作ってみました。
私の持っている特小無線機はこれまた旧型のIC4008Wです。
詳しくは知りませんが、米海兵隊で同型(4008M)を運用していたようですね。

海兵隊装備だったら、「20ch」の印刷を消せばサバゲ用無線機そのままで実物装備となるわけですね。
うらやましい限りです。
4008WはF3Sに対してかなり小型なので、先ほどの「詰め物」と一緒にポーチに入れることでF3Sポーチイン時の外観に似せることができました。
ちなみに本物をポーチに収納した時はこのようになります。
ほぼ同じ外観にできました。
これでポーチの蓋を閉めている限りは、F3Sが入っているように見えますね。
次にヘッドセットです。
ヘッドセットはソルジャーインターコムキットにTELEXのスティンガーが入っていたようです。
三叉配線で特徴的な形状のヘッドセットです。

私も実物を持っていますが、断線していたものをとりあえず形だけ結線しただけのものなので、当然不動品です。
実用復旧化は不可能と判断しています。
そこで、得意の妄想発動です。
彼らグリーンベレー隊員はヒゲもロクに剃らずに、国から支給された品を勝手に切ったり縫ったり塗ったりしちゃう不良なわけですから、キット同梱のヘッドセットを使わないのもお茶の子さいさいでしょう(笑)
まあまじめな話、スティンガーはクセのある使い心地でしかも結構嵩張るので、毛嫌いした隊員はいただろうと思いました。
実際にODA隊員が着用しているミリフォトはほぼ見たことないレベルですしね。
そしてF3Sのコネクタは日本で出回っているICOM特小無線機と同じで、一般にも広く普及しているもののはずです。
したがって、「スティンガーがどうにも使いづらく、自前でICOM用のヘッドセットを調達した」という設定とすれば、市販のICOM用ヘッドセットで代用しても不自然ではないと考えました。
国内大手の通販サイト等で「っぽい」ヘッドセットを探してみようと思います。
最悪の場合、無線は原則聞けるだけでもギアフリでは用は足せそうなので、実用重視でなるべく目立たなくて聞きやすいイヤホンで行くのもありかなと思っています。
年末のバタバタソワソワからの正月ボケで、2月なんてあっという間に来てしまいますので、今の内から少しずつ装備構想を練っていこうと思います。
こうして目指す目標(イベントごと)があり、それに向けて装備を考えている時がなんか一番ワクワクしますよね(笑)
お読みいただきありがとうございました。
初期アフODA御用達 ABAアーマー
本題に入る前に、前回までの考察のおまけを書きます。
前回、下記写真のM4の照準器はおそらくPVS-17だというコメントをMUNAGE師匠からいただきました。

そこで色々調べてみると、この現場で撮られたと思われる写真が出てきました。

まずM4に注目です。これはPVS-17と断言してよさそうですね。
そしてこの方と思しき人物が前回考察した映像に写っています。

塗装されたM4、塗装されていないデカイ照準器、M203,ストックへのスリングの着け方、グレネーダーベスト、カスタムDCU、素頭にアーバン等の特徴が一致します。
また、写真のようにヘッドライトを着けている状態と思われるシーンもあります。

右側の中腰の人です。額の部分が反射して光っているように見えます。
そして顔のアップも映りました。

輪郭やほうれい線、ヒゲの生え方あたりから同一人物と判断しました。
M4の特徴や素頭にアーバンのところから、M4を構えた画像も同一人物と思われます。
背景的にも似たような場所であると想像できます。
さらに間接的な要素としては、この現場にはカメラマンが同行していたのが映像に写っていることです。

カメラマンが同行取材していたとなれば、上記のようなカメラ目線でポーズを取った写真の1枚や2枚はあって当然だと考えます。
むしろ芋づる式にもっと出てくると思ったのですが、私の調査力では発見できませんでした。
写真が出てくれば以前考察した番組「Special Operations Force: America's Secret Soldiers」のように一気に考察を深められると思うので、引き続き調査を進めていこうと思います。
それではそろそろ今回の本題に入ります。
数年間探していたアイテムを曲りなりにも遂に手に入れられたので、記事にしておきます。
初期アフODA装備例が多数あるABA製のアーマーです。

肩部の四角いベルクロ面が特徴的ですので、判別しやすいですね。
型番は似たような形状が沢山あるようなので何とも言えませんが、おそらく「OC-3」というものだと思います。
今回、私の手に入れた個体は型番の記載がありませんでしたが、形状的にはミリフォトとほぼ同じように見えます。
バックカバーの首元のアール形状等が少しだけ違う気がしますが、そんな些細な形状なぞより大問題があります。
残念ながら私は初期アフODAのタンカラー着用例は見た記憶がありません。
インナー無しですが新品コンディションで超安かったので勢いで買ってしまいました(笑)
そして色を黒くできる勝算も一応ありました。
ポチッた後、プランAとプランBの2重の作戦を準備し、アーマーが海を渡ってくるのを今や遅しと待ちました。
下記作戦の詳細です。
プランA 染色
DIY染料の代名詞「ダイロン」を用いての染色です。

今回染色は初チャレンジでしたが、タンカラー→黒なので可能性は十分にあると踏みました。
ネットで分量を見てみると、黒くしっかり染めるのは1袋あたり125g必要なようでした。
アーマーはカバーのみで約300g強ありましたので、3袋あれば十分です。
近所の手芸店で探したところ、ブラックが2袋しかなかったので、1袋はディープブルーを買いました。
100均でバケツ、トング、泡立て器を調達して準備完了です。
プランB 塗装
染色で黒くしきれなかったり、素材によって染まらない箇所があった場合は「染めQ」を使おうと考えました。

「染め」とありますが、原理としては塗装のようです。
粒子が細かく塗膜を形成しないため、染めたような仕上がりになるようです。
全面染めQ仕上げも考えましたが、耐久性と加工面積、コスト面でまずダイロン染色を選びました。
実践
モノが届いたので、いよいよプラン実行です。
まずはプランAのダイロン染色から実行します。
汚れは無く新品同様だったので、変な染めムラ等は起きなさそうです。
邪魔なだけで染料を無駄に吸ってしまうパンツイン用のベロは速攻で切り落としました。
PACA等でもこの部分は放出品で切り落とされている場合が多い印象ですが、先日考察した「Taleban Patrol」ではベロが出ている隊員もいました。
ベロ施術後洗濯し、脱水までした状態でダイロンと食塩を溶かした熱湯にぶち込みます。
あとは40分ほどひたすらトングで混ぜ続けた後、よくすすぎ、陰干しして完了です。
ベルクロ部は元々黒かったかのように完璧に染まりました。
生地部は黒というよりはグレーで、かなり色褪せた感じと見ればそう見えなくも無い感じです。
ミリフォトでも生地部はベルクロに比べて若干明るい場合が多いです。
砂汚れが付き易い生地なのか?それとも洗濯等で色落ちしたのでしょうか?
いずれにせよ、あともうワントーンは暗くなってくれるとありがたいところです。
上記2箇所は青要素は全く見えてこなかったですが、ゴムバンド部はうっすら青くなってしまいました。
かなり使い込んで色褪せたと思えばそう見えなくもないですが、このままではちょっとみすぼらしいです。
プランAでまあ70%は満足できる仕上がりになりました。
あと30%をプランBで補います。
ベルクロはこの時点で100点満点なので、生地とバンドを染めQで黒くします。
満足の行く黒さが出るまで染めQを重ね塗りしました。
速乾性があり失敗しなくていいですね。
少し値が張りますが、大変気に入りました。
ほぼ1本丸々使って完成です。
生地の質感をほぼ変える事無く、しっかり黒くすることができました。
遠目で見れば元から黒かったようにしか見えません。
やればできるもんだ。感動です!
シワの部分等、所々塗装が入り込まず色が薄い部分がありますが、どうせこの後わざと使用感を出す為に汚したり剥がしたりするので、むしろ手間が省けました(笑)
あとは耐久性ですが、色々な方のレビューを見る限り中々のもののようです。
染めQ自体はすぐに手に入る物なので、色落ち等したら買い足して追加工していけば問題ないと思っています。
あとは砂の多いフィールドで使えば汚れも着いていい感じになると思います。
早速次のサバゲで着ようと思います。
お読みいただきありがとうございました。
PMCのお勉強&ジョークグッズDIY

ギアフェス東北の帰りのバスでBucket Head氏とハート・ロッカー話をしてから、ふつふつとPMC熱が進行しています。
2000年代中盤あたりのPMC装備は、初期アフODAに通ずる「現場感」的なラフさがあると思います。




一口にPMCといっても玉石混交だったようで、ブルジョアな装備と特殊部隊出身者のような経験豊富な社員で構成された会社もあれば、銃を触ったことも無いような人を面接一発で即採用して、貧乏臭い装備で運営する会社もあったそうです。
いい加減なPMCの中にはきっと、デッドプール的なノリでピーターみたいな人も採用していたのではないでしょうか(笑)
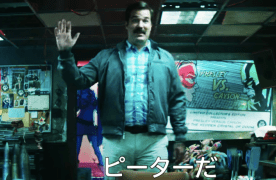



当然サービス提供額もピンキリだったわけですが、顧客も政府の要人から、下請けの下請けのそれまた下請の建設業者のような所まで千差万別だったようなので、安かろう悪かろうなPMCも需要があったようです。
まだまだ勉強途中ですが、そのあたりの企業ランクも想像しながら装備を構成すると、リアルな感じを出していけるのかな?と思っています。
ちなみに「ハート・ロッカー」のPMCも装備していた中国の56式小銃は安かったようで、実際のPMCも結構使用していたようです。
AK系は製造国によって相場が大きく違ったそうですが、本体も弾も全体的に安価だったようです。
ハート・ロッカー劇中の56-1式。

56式を携える本物PMCコントラクターだそうです。

軍隊と違いPMCは利益を出す事が目的の企業なので、経費がかなり考慮されて装備が選ばれていたという視点は、私がいつも目指している軍隊、とりわけ精鋭の特殊部隊装備においてはほぼ意識しないので新鮮に感じました。
装備に「ケチってる感」を出すことで、所謂「サバゲーマー装備」に見られないPMC装備としてのリアリティに一役買いそうですね。
何にせよ、大好きなリアルソードの56式が堂々と使える装備として「貧乏PMC」は個人的にかなりストライクなカテゴリになりつつあります。
PMC装備を志してから、56-2式が欲しいものリストの上位にぐいぐい食い込んできています。

ちょっと前まで超絶かっこ悪いと思っていた「スコップの柄ストック」が今の私には輝いて見えます。
恋は盲目といったところでしょうか(笑)
世間一般的には「かっちょ悪いことこの上ない」という評価と思われ、リアルソードのモデルの中では比較的安価に取引されているのも魅力です。
手にせず廃盤になったら一生後悔すると思うので、早めに手に入れておこうと思う今日この頃です。
あとはアメリカ以外の出身という設定等を考慮すれば、G3やFALなんかも違和感なさそうですので、米軍装備では持てなかった銃が選択肢に入ってきて夢が広がりますね!

ちなみにこの方はG3を持っていますが米国人だそうです。
前回の記事で少し書いた「シャドウ・カンパニー」のDVDも無事に入手し一度見ましたが、お金のないPMCは社用車は普通のSUV等に自作の装甲版を付けていたそうです。
DIYで鉄板を張り合せて工面すると、コストが10分の1で済むという話が出ていて面白かったです。



内容は非常に興味深い話ばかりでしたが、如何せんひたすらインタビューでしかもみんな早口なので、一回見ただけでは字幕を追うのが精一杯で全然咀嚼しきれませんでした。
劇中の装備映像分析も含め、時間を掛けてゆっくり楽しもうと思います。
そんなPMC研究を進めている傍らで、ユルゲ3向けにジョークグッズを1個作ってみました。
前回の記事にも書きましたが、PMC社用車の後部にはよく警告看板が貼ってあります。


今回、100均の材料でこれを作ってみました。
モデルにしたのは映画「ルート・アイリッシュ」で出てきたこの看板です。

材料は下記を調達しました。324円也。
・家具デコレーションステッカーシート
・水性マーカー(赤&白)
なぜステッカーなのか謎だと思われるかもしれませんが、要は「白くて折り目が無く、マーカーで書ける」物ならなんでも良かったのです。
当然裏返して使います(笑)
45×35cmという丁度良いサイズで、裏面は画用紙より少しツルッとした紙で、素晴らしい質感です。
このステッカーを作った人も、まさか裏面にでかでかと「DANGER」なんて落書きされるとは夢にも思わなかったことでしょう。
画像を参考に、全体のバランスを見ながら鉛筆でアウトラインを描いていきます。
その後、マーカーでなぞって色を塗っていきます。
英語の下にあるアラビア語?なんてどっちから読むかも知りませんので、完全に「絵」という認識で描いていきます。
今回の作業のお供はラジオ番組「伊集院光 深夜の馬鹿力」です。

私は通勤時間や入浴時間等に芸人のラジオ番組(ジャンクやANN)を聴いているのですが、今回の塗り絵のような「頭は使わないけど目と手は集中しなければいけない」作業とラジオの相性は抜群ですね。
伊集院光さんに笑わせてもらいながら、1時間弱で出来上がりました。
シートだけではコシが足りないので、裏面にダンボールを貼り合わせて完成です。
少し文字バランスが悪いですが、まあジョークグッズですし自分の中では及第点とします。
最後にタミヤのスプレーで砂汚れを再現し完成です。
車の後部にナンバープレートが隠れるように配置すれば、私の車がオンボロということもありいい味が出そうです。
(以前記事で少し書きましたが、91年式のゴルフ2です)
ちなみにネットで画像を調べていたら、この看板を模したアクセサリーを見つけました。


誰が買うのか知りませんが、とりあえず何でも商品にしたもん勝ちですね(笑)
ユルゲはゲーム面がゆるい分、色々な方とお話ししたりこういう物で遊ぶ時間がしっかり取れるので、個人的には非常に楽しいです。

今回はフリマ的な催し等もあるようなので、どのような進化を遂げるのか楽しみです。
暑い時期は体力的にゲームばかりやっていられませんので、夏×ユルゲは相性がいい気がします。
早々に梅雨明けはしましたが、当日は天気に恵まれるのを祈るばかりです。
お読みいただきありがとうございました。