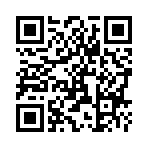スポンサーサイト
PMCのお勉強「潜入!イラク危険地帯」

本題に入る前に、今話題のスターウォーズのスピンオフ連続ドラマ「マンダロリアン」を鑑賞しました。

本編シリーズで登場しているボバ・フェットやジャンゴ・フェットと同じ部族のキャラが主人公の冒険活劇です。
当ブログのプロフィール画像を見ていただければ分かると思いますが、私はスターウォーズ大好きです。
小学2、3年生の頃、WOWOWで録画した旧三部作(EP4~6)をVHSが擦り切れるまで何度も繰り返し観ていました。
高学年になった頃特別篇が公開されましたが、最寄りの映画館ではやっておらず電車で錦糸町まで行く必要がありました。
親に連れて行ってとせがみましたが、結局一度も見に行かせてくれなかった事は今でも根に持っています(笑)
スターウォーズとガンダムの影響でミリタリー好きになって理系に進んで、今の私があると言っても過言ではありません。
兵器とテクノロジーは最高に知的好奇心をそそりますよね。
本作ですが世間の評判通り、単刀直入にとても面白かったです。
エンディングに流れるテーマ曲が超クセになります。
全8話ノンストップで見てしまいました。
ストーリーや演出は王道西部劇&時代劇的な、割と既視感ありまくりです。
まんま「七人の侍」の回もあります。
ですがスターウォーズはそれでこそ良いのだと再認識しました。
スターウォーズで大切なのは、拡がりを感じる世界観と魅力的なキャラクターがちゃんと生きている事なのだと思います。


変に奇をてらった設定や無駄に二転三転する展開、世相に合わせた含みを追求するのは、殊スターウォーズにおいてはノイズといっても過言ではないと私は思います。
無限に想像力を掻き立てる世界で魅力的なキャラクター達が王道展開でカッコよく活躍すれば、グッズが出てファンは嬉しいしディズニーも儲かるしで万々歳なわけですね。
スターウォーズというコンテンツがお金を生み続ける限り、ダークサイドは何度でも蘇りディズニーによる宇宙戦争ビジネスは続くはずです(笑)

過去作のオマージュやネタを出す所謂「ファンへの目配せ」ですが、本作はいい塩梅というか、浅い~超コアな人しか気づかないレベルのものまでバランスがいいです。
「The Holiday Special」という、スターウォーズ黒歴史なTV作品のネタを散りばめてきていたりして、気づいたファンは嬉しいでしょう。
思わずSNSで「俺これ気づいたぜ!」と自慢したくなり、拡散効果も狙っているのかもしれませんね。
この作品の唯一の難点は、現在配信がディズニーデラックスというサービスのみに限定されていることです。
待っていればアマプラやネトフリ等でも配信されるとは思いますが、ディズニーデラックスは初月1ヵ月無料なので、今まで未契約であればマンダロリアンだけ観て一ヵ月以内に解約すれば無料で鑑賞できます。
ただ、これでハマってシーズン2が始まったら我慢できずに結局有料で契約と、まんまと某マウス卿の手の平で踊ることになりますが(笑)
私はシーズン1を観終わって無料期間で契約を切りましたが、シーズン2が配信された直後に確実にマウス卿にひれ伏す事になると思います。

本作の高評価でディズニーもスターウォーズの作り方のコツを覚えて、良作(と良グッズ)を量産してくれるとありがたいですね。
では、そろそろ本題に入ります。
先日テレビでナショナルジオグラフィックチャンネルを見ていると、興味深い番組がやっていたので記事にしておこうと思います。
2000年代中ごろのイラクにおけるPMCの密着取材特集です。



放映されたのは2007年のようです。
おそらくUCP柄のポーチが一瞬映るので、取材したのは2005年以降の可能性が高そうです。

後述しますが、ナジャフの戦いについて触れているので2004年4月以降なのは間違いないでしょう。
番組の構成上、色々な年代の映像を織り交ぜている可能性も高そうですが。
少なくとも全て放映された2007年以前の映像ということは間違いないでしょう。
本当はPMCではなくPMSCがちゃんとした呼称だと思いますが、本ブログでは一般的に通りが良いと思われる「PMC」と呼称します。
邦題は「潜入!イラク危険地帯」という
ちなみに原題を調べてみると「Inside:Iraq's Kill Zone」でした。
まあまんま直訳といえばそうですが、「潜入!」というあたりが胡散臭くてイイですね(笑)
イギリスのアーマーグループ社とハートセキュリティ社に密着し、いくつかの任務に同行しています。
比較的安全な任務を選んだのだとは思いますが、いつ武装勢力から攻撃されるか分からない非常に危険で貴重な取材だと思います。
日本で比較的簡単に見られるPMC資料となる映像ソフトとしては「SHADOW COMPANY」がありますが、それよりも実際の現場の緊張感が伝わってくる内容でした。

任務同行の一部始終が流れるので、具体的で非常に勉強になりました。
個人的にPMC入門書と思っている「戦場の掟」ですが、この番組を見てから読んだ方がより情景や背景がイメージしやすくていいなと思いました。

同行した任務は輸送(物資、要人)やコンボイの護衛ですが、任務によって「ハイプロファイル警護」と「ロープロファイル警護」と呼ばれる、対称的なアプローチがあり興味深かったです。
まずハイプロファイル警護について書きます。
車載機関銃や重装備、装甲車両で敢えて重武装をアピールして「俺らに喧嘩売ったら痛い目見るぞ」と抑止力全開で威圧しながら街中を通行する形式です。


抑止力に加え実際に攻撃された際の対応力に優れ、一般車をどかしながら止まらず通行できますが、目立つので当然襲われる確率自体は高くなります。


ハイプロファイル警護で同行したひとつの任務の目的は、医療品をグリーンゾーンから数キロ離れた前線基地に運ぶという補給任務でした。
当時のバグダッドは道がそこかしこでしょっちゅう封鎖されていたようで、予定通りのルートで進めない事が多く、同行した任務でも車列が道に迷っていました。
道に迷って危険地帯で減速したり立ち往生したところを襲撃されるケースが多かったようです。


もうひとつは夜間に隣町に建設資材を運ぶコンボイを護衛するというもので、こちらは帰り道に銃撃を受けるという緊迫した場面があります。


夜間は視認されづらくゲリラの監視も薄くなりますが、一般市民は外出禁止令が出ていたので、夜間の車列=ゲリラにとっては襲撃対象という事が明確なので、一長一短だったようです。
また、コンボイの運転手のようなどこの馬の骨とも分からない雇用者は、ゲリラ側に情報を売っている危険性も高かったそうです。
実際このコンボイでも疑わしい行動をする運転手が出てきます。


一方PMCに雇われているイラク人は、自分が外国軍の関係組織に雇われていると知られるとゲリラに殺されてしまう為、絶対に顔は晒さないようにしていたようで、番組中に出てくるイラク人スタッフは漏れなくモザイクが掛かっていました。



イラク現地人PMC装備を再現する場合、顔全面隠しは必須ですね。
ハイプロファイル警護を想定した装備をする場合は、こんな感じのがっつりゴテゴテ装備にするとサマになりそうですね。

次にロープロファイル警護についてです。
目立たない装備、防弾加工は施してありますが一見して一般車両に見える車両で、アーマー類も服の下に着こんで、銃はなるべく見えないように携行して一般人に紛れて目的地まで到達する手法です。



一見して一般人と同じなので察知されづらく、察知されない限りは安全です。
しかし渋滞に巻き込まれると停止している時間が長くなりますし、もし情報が洩れていたら一巻の終わりです。
番組で同行したのは政府要人をグリーンゾーンから役所に護送するというものでした。
政府施設の前には大抵ゲリラが監視をしており、そこの前で停まった=要人が乗っている事を示唆してしまうので、危険な瞬間No.1だそうです。
万が一襲撃された際はスモークを焚いて降車し、安全な所まで退避すると言っていました。

スモークグレネードを持つとPMC装備としてのリアリティが増しそうですね。
あと、細かいところですがForetrex101も携帯しているようでした。

Foretrex101は2004年春には発売されていたと思われます。
以前考察記事を書いています「GARMIN Foretrex101」
色々なアイテムの年代を知っていると、ミリフォト等の年代考察に大いに役立ちますよね。
また、Foretrex101は特殊部隊装備でも大活躍なので、こうして流用できるアイテムはありがたいです。
ある任務前の準備シーンでは、プライマリの弾薬を420発(30rd×14本)も携帯するという言及がありました。


もちろん任務によって違うと思いますが、この辺りも装備を考える上で参考になりますね。
どの装備でもそうですが、携行弾数を考察することは結構大事な要素だと思っています。
ゲームユースだけ考えてマガジン数(マガジンポーチ容量)を決めると、リアルとは離れてしまう恐れがありますよね。
その辺りを工夫して、サバゲでも使えてリアルな装備を追求するのが楽しいと思っています。
会社内の工房も登場し、装甲車の改造や社内ガンスミスへインタビューもしています。



まるでエアガンのカスタムのようにAKのバレルをギリギリまで短縮化している一幕があります。



やり方はLCTやE&Lの電動AKのバレルカットと大差無さそうで驚きました(笑)
PMC装備では軍隊装備よりも自由度の高いカスタムエアガンを使えそうですね。
かといって何でもいい訳では無く、その時現地でどのような銃が入手できたかや、会社のランクを想像し予算に合った銃種は何か等、軍隊装備では考慮しない点も考慮する必要がありますね。
また、上述の通り任務の想定も選択する銃の要素に大きくかかわってきます。
ロープロファイルな服装(小型アーマーの上からカメラマンベスト等)なのに光学機器満載&ドラムマガジンのARやAKを持っていたら、ちぐはぐになってしまいますね。
ちなみに、車両移動で固定ストックのAKを使っているシーンがありましたので、私の56式小銃もPMC装備として無くはないのかなと思いました。


PMC装備は勉強するほど奥が深そうです。
他にも、重大事件である2004年4月に発生した「ナジャフの戦い」についても触れており、当時のイラクでのPMCの存在がどのようなものであったかを解説しており、中々見ごたえのある番組でした。



ナジャフの戦いはyoutube等で実際の戦闘動画がいくつも見られますので、興味あれば検索してみてください。
ところどころおなじみのロバート・ヤング・ペルトン氏もインタビューで登場し、番組に説得力を添えています。

最後に、取材に応じた一社であるアーマーグループ社ですが、1981年に元SAS隊員が創立した古株PMCのようでした。
番組中、社員の日給は600USDと言及されていますので、高ランクのPMCなのだと思います。
元英軍特殊部隊上がりの方が中心だったのかもしれませんね。
アフガンのアメリカ大使館にて、戒律で飲酒が禁じられているムスリム現地人に酒を飲むようアルハラをしてスキャンダルになったそうです。
ちなみに番組でインタビューされていた社員の働く動機は下記のようなものでした。


働く動機は人それぞれだと思いますが、自分の才能を活かして世の為になればと思っていた方もいたということですね。
PMCというと悪名高い某社の横暴な態度や事件、それから発した映画や漫画、ゲームの影響で、とかく「悪者、不良、金の亡者」寄りなイメージを持ちがちだと思うので、ちょっと印象が変わりますよね。
この番組ではないですが、下記はアーマーグループ社員の2007年アフガンでの訓練時の写真のようです。

G36を持っています。
サバゲで持てる銃の選択肢が拡がりますね。
腕時計は先日記事にしたSUUNTOのVECTORでしょう。


先日の記事「SUUNTO VECTORマイナーチェンジ考察」
おそらくこの方の個体もベゼルと6時側側面のSUNNTOのロゴ印刷が綺麗さっぱり無くなっていますね。
SNS等で、Crye的なコンシャツコンパン上下にレプオプスコアにレプJPC的なプレキャリを着て、かわいい女の子のアニメキャラのパッチを胸に貼って、クリスベクターのような銃を持って「PMC装備でサバゲ―してきました」みたいな投稿を見かけると、微笑ましくなります。
自分は微笑まれる側にならないよう、地道にPMCの勉強を続けながら装備を構築していきたいと思います。
お読みいただきありがとうございました。
初期アフミリフォト考察⑲ 初期アフカメラ その3

最近、日本に帰任したらどの車に乗ろうかよく考える時があります。
私の車遍歴はまだまだ浅く、結婚して家を建てた後、30歳手前にして初めて自分の車を買いました。
(実家の車で運転したのは日産ブルーバード→ホンダストリーム→トヨタカローラスポーツ)
私の初めての自分の車は、91年式のフォルクスワーゲン(以下VW)のゴルフ2でした。

18万キロオーバーの大ベテランでしたが、納車してから中国に赴任するまでの約3年間、走行できなくなるような大きなトラブルは無く楽しく乗りました。
めぼしいトラブルはエアコンの送風機構の軸が曲がって異音が出たのと、クーラントがちょい漏れした、マフラーに穴が空いたくらいでした(いずれもお店からは症状が出る前に交換を勧められましたが、ケチって異常が出るまでほっといた私のせいです)。
そんな素敵なカーライフを共に過ごしたゴルフ2ですが、赴任に際して手放しました。
買った時も、乗っている途中の整備も、売った時も神奈川県にあるゴルフ2専門店「スピニングガレージ」にお世話になっていました。

とても丁寧で信頼のおける整備をしていただき、旧い車ですが安心して乗っていられました。
パーツ在庫が豊富で流通ルートも強いようで、旧い車にも係わらずパーツ交換等で何日も待たされることは皆無でした(基本持ち込み即日)。
工場で整備してもらっているところを見学して、仕組みを色々教えてもらったりしたのも楽しかったです。
最近ふとお店のホームページで在庫車両一覧を見てみたら、元愛車が売りに出されていました。


フロントグリルは4つ目に換装されていますが、説明文からも紛れもなく私が乗っていた車です。
偶然SNSで元カノの写真を見た感覚に近いようなものがありました(笑)
次はどんなオーナーが手にされるのか分かりませんが、末永く元気に走り続けて欲しいものです。
ゴルフ2は年式相応の装備の不便さはあったものの、運転自体はとても楽しく十分実用範囲でした。
よくVWの車は「剛性がある」と言われますが、確かに一本芯が入ったようなカッチリした走り心地で、いつまでも運転していたくなるような気持ちよさがありました。
が、如何せん妻からは「振動がー」「音がー」と不評でした(苦笑)
子供も2人に増えましたので、次はファミリー寄りにしなければと思いつつも、道に溢れている現役国産ザ・ファミリーカーの中の1台に溶け込むのは面白くないなと思います。
ランクル(100あたり)やハイエース等の堅牢な国産ロングセラーの車体を、自分好みにがっつりカスタムしながら一生乗り換え無し覚悟で永く乗る、というのも憧れます。
ですが我が家の用途ではオーバースペック&予算的に厳しそうなので、ちょい旧式の安くなった輸入ミニバンを鉄チンホイール換装&メッキパーツをブラックアウトしてチープアップ、あたりで子供が大きくなるまでやり過ごすが妥当かなと思っています。
ゴルフ2でVWの質実剛健さに魅力を感じたので、次はゴルフ派生ミニバンのトゥーランのバリエーションである、クロストゥーランあたりをベースにチープアップカスタムしたいなと目論んでいます。
イメージとしてはこんな感じです。

2012~2014年式なので古すぎず新し過ぎず、日本での販売台数も少なく「皆知ってるVWだけどマイナー車種」という、初期アフに通ずるニッチ加減も魅力的です(笑)
サバゲやキャンプにはよく行きますが本格的なオフロードはまず走らないので、ちょこっとSUV感を纏ったただのミニバンで今の私にはちょうど良さそうです。
そんな妄想が止まらない今日この頃ですが、本題に入ります。
初期アフミリフォト考察シリーズです。
今回も隊員の携帯しているガジェットに注目しました。
トップ画像にもしましたが、下記写真が今回の題材です。

この写真が初期アフグリーンベレーであると考えた根拠は下記になります
・家、子供の感じがアフガンっぽい
アフガンの文化や風習、人種に精通しているわけではないので、あくまで他のミリフォトで見た感じや一般的なイメージのレベルです。
・右の背中が写っている隊員がOTV+TLBVにベースボールキャップ+シュマグ

2002年~2003年頃の初期アフグリーンベレーでよく見るセットアップです。
背中のポケットのフラップでOTVだと判別できますね。

TLBVは単体写真と見比べて判断しました。

・右奥の隊員もおそらくキャップ+OTV着用
肩に見えるドットボタンらしきものがOTVのFLC固定用のループのドットボタン(が外れた状態)と思われます。


・左の隊員のお腹の出具合
完全に偏見ですが、この腹の形はまあまあなおっさんだと思われます(笑)
3CのSPEARの類が見えないので、おそらく19thか20thの予備役SFGだと思っています。

というわけで初期アフグリーンベレーかどうかの確固たる確証はありませんが、少なくともDCUにOTV+TLBVという装備から2000年代初頭の米軍であることは濃厚だと思います。
そんな写真ですが、左の隊員が手にしている機器に注目しました。

カメラですね。
過去2回初期アフミリフォトのカメラ考察をしましたが、これも特徴的なカタチをしているのでいけそうです。
過去記事
「初期アフミリフォト考察⑭ 初期アフカメラ」
「初期アフミリフォト考察⑱ 初期アフカメラ その2」
大きな特徴は左手で持っているレンズ部分が回転できる構造です。

これはかなり探しやすいというか、初見で心当たりがありました。
コンデジ時代幕開けのきっかけとなったと言われるCASIOのQV-10です。

1995年発売です。
今のコンデジでは当たり前ですが、世界初の液晶画面が付いたデジカメです。
液晶画面が付いたおかげで、撮ってその場で確認できるという機能がエポックメイキングとなり、爆発的にヒットしたそうです。
また、Windows95の登場による一般家庭へのパソコン普及期にマッチし、撮った写真を簡単にPCに取り込めるという機能も人気を後押ししたようです。
画素数は超絶低く、SDカードや無線接続こそ無いものの、基本的な使い方は今のデジカメと同じであり、25年前に既に基本は確立されていたんですね。
しかしそのコンデジも平成の終わりと共にすっかり衰退し、時代を感じます。
もう数年もしたら、映画やドラマ等でコンデジを使っているシーンが出ると、今でいうガラケーやポケベルのように「うわ、コンデジとか懐かしー!」と言われる時代が来るんでしょうね。
QV-10は未来技術遺産に制定される程の名機なので、ネット上に資料はたっぷりあります。
以前の記事でも書きましたが、カメラ周りのネット情報はミリタリーの比にならないくらい量が豊富で質も高いです。
これらの画像とミリフォトと見比べてみます。
回転するレンズ部はもちろん、右手で掴んでいる部分の形状等からもQV-10である可能性が高いです。
ただ、以前のOLYMPUS μであったように、この種の製品は同じような形の機種がいくつも発売されている可能性があります。
そこで、2002年頃までのCASIOのQVシリーズを片っ端から調べてみました。



同じようにレンズ部回転機構のカメラは複数ありましたが、ミリフォトのレンズ周りの黒い部分の面積から、下記に絞り込みました。

QV-10

QV-10A

QV-11

QV-10AはQV-10の中身をマイナーチェンジした程度、QV-11はQV-10Aのコストダウンバージョンのようです。
比較レビュー記事等いくつか見ましたが、外装は色が若干違う程度で全く同じ形状でした。
この解像度のミリフォトから判別は不可能ですね。
なので次は販売時期から考察します。
発売時期はQV-10が1995年、QV-10Aが1996年、QV-11が1997年です。
性能はどれもほぼ同じでQV-11が他の2機種より数万円安いコストダウンバージョンなので、QV-11と考えるのが自然ですね。
写真を見つけただけですが英語版パッケージは存在するので、きっと北米でも売っていたと考えられますね。

QV-11(10も10Aも)は外部メモリーはなく、内部メモリーでモードによりますが約100枚保存が可能なようです。
一回のパトロール任務であれば十分事足りそうですね。
ちなみに、内蔵記憶容量は2MBだったようです。
今のデジカメじゃ1枚すら保存できませんね(笑)
プレステ2は8MBのメモリーカードが3500円したのは今でも覚えています。
今3500円出せばその3万倍以上の容量の記憶媒体が買えると思うと、この20年の劇的な進化を感じますね。
駆動方式は単三アルカリ電池4本でカタログ上は2時間連続再生、100枚撮影できたようです。
汎用的な単三電池を使っているので、おそらく現地でも容易に調達できたと思われます。
少し時代と電池は違いますが、Foretrex101も単四電池を使用しており簡単に調達&切れても現場で即座に電池交換して連続使用できたので、その兄弟機種で充電式のForetrex201よりも圧倒的に使用例が多いのだと思います。


充電式って一見便利に思えますが、充電中は使えなかったり、劣化しても交換できない事が多く意外と不便だと個人的には思います。
写真としての質はフィルムカメラの方が上だと思いますが、単三電池さえあれば無限に撮影できるというのは有用だったと想像できますね。
また、撮影したその場でどのような写真が撮れているか確認できたのもかなり重宝したのではないかと思います。
加えてフィルムの交換や現像も不要で、PCに繋げれば即座にデータとして取り込めたのもかなり便利だったと思います。
そう考えると実用性のあるチョイスだったのかもしれませんね。
ただ、2002年前後でQV-11となると結構な旧式だったと思います。
画素数は25万画素ですが、2000年頃のデジカメは200万、300万画素が当たり前になっていたようです。
それに上述したデジカメの利点はQV-11に限った話ではなく、他の後発のデジカメでも言える事です。
なので、当時でも既に性能が一周り低かったQV-11をわざわざ持っていたという所が妄想が捗りますね。
デジタルガジェットやカメラに興味があるなら、もうちょっと新しいカメラを持ち込んでいると思います。
そこで、アフガン派遣前に近所のモールの電器屋かホームセンターあたりでワゴンセールになっていたQV-11をとりあえず買って持ってきた、と妄想しました。
もしくは親戚か近所の友達から出征に際し「これで写真いっぱい撮ってきて」的な感じで渡された、という妄想も映画みたいでいいですね。
こんな感じで自分の装備もアイテム1つ1つにストーリーを持たせることで、より深みが増せると思っています。
最後に、例によって市場調査をして皆様の物欲を刺激して終わろうと思います(笑)
国内オークションを物色してみると、中途半端な古さが幸いしてか、かなりお安く手に入る状況です。
QV-10、10A、11共にちゃんと動く品で2000円も出せば買えそうです。
レンズキットなど、オプションパーツの類も安価に流通しています。

ちゃんと可動して役に立つアクセサリとして、装備のポーチを埋めるにはもってこいなおもちゃになりそうですね。
私は以前、同じく初期アフカメラであるOLYMPUSのμをタダ同然で購入しましたが、フィルム代、現像代がバカにならないので沢山撮るのは気が引けます。

QV-11ならエネループ4本さえ用意すれば、ランニングコストほぼゼロ円で当時っぽい写真がばんばん撮れそうなので、こっちもかなり欲しくなってきました。
ただ、今のPCのハードとOSがQV-11(とドライバ)に対応しているか?確認する必要はありそうです。
ちょっと調べた感じ、ソフトはまさかのフロッピーディスクに入っているようです(苦笑)

誰か中身をネット上にアップしてくれている事を祈りたいですね(笑)
帰国できる目途がたったら購入検討したいと思います。
お読みいただきありがとうございました。
SUUNTO VECTORマイナーチェンジ考察

コロナの影響で飲み会や出張がめっきり無くなり、家にいる時間が増えたのですが、Call of Duty MWはちょっと飽きてきたので今違うゲームをせっせとやっています。
World of Tanks(以下WoT)というゲームです。

オンラインで15対15で、主に2次大戦周辺頃の戦車で戦うゲームです。



高校生の頃、PSソフトのパンツァーフロントが大好きだったので、当然このゲームもドハマりしました。

当時「パンツァーフロントでプレイヤー対戦できたら最高だろうなあ」と夢見ていたので、まさに夢が形になったようなゲームです。
ファミコン現役時代から、多感な時期に激動の進化をリアルタイムで味わえている世代なので、ゲーム史的には本当にいい時代に生まれてきたと思います。
元々はPCゲームで2011年4月にサービス開始、PS4版は2016年1月にリリースされ、今も現役の息の長いゲームです。
私はPS4版リリース直後にデビューし、今もやっています。
がっつりハマる時期もあれば、数か月ログインすらしない時期もありますが、この1ヵ月くらいはがっつり期間真っ最中です。
WN8でようやくユニカムが見えてきたので、とりあえずユニカム目指して頑張ろうと思います。

「WN8」というのはWoTにいくつか存在する「プレイヤーの技量指標」みたいなものの一つで、プレイヤーの個人戦績から自動的に算出されます。

ドラゴンボールで言う所の「戦闘力」みたいな感じです。
「ユニカム」というのはこのWN8が2450~2899のレンジのプレイヤーの称号で、人口分布としては上位0.1%に入ります。
ラテン語で「唯一無二」みたいな意味らしいです。
既に熟成されつくしておりゲームシステムの完成度は非常に高く、どのFPSともロボ対戦ゲーとも異なる独特の操作感、戦術が病みつきになります。
グラフィックや挙動、音、超マニアックな車種等、戦車への愛が滲み出ているので、戦車好きなら間違いなくやって損は無いと思います。
近年、戦車にまとわりつくようになってきた「女子高生イメージ」ですが、このゲームにはそんな「萌え」的な要素は皆無です。
乗組員は劇画調のおっさんばかりです。

少し課金すると声やビジュアルをカスタマイズできますが、劇画のおっさんを別の劇画のおっさんに変えられるだけです(笑)
ポリコレに配慮してか、いつからか女性乗組員の選択もできるようになりましたが、もれなく劇画で「萌え」の欠片すらない安心設計です。

私としては戦争モチーフのゲームは、こういう硬派な方が大好物です。
同じシステムでも、ガールズ&パンツァーみたいな雰囲気だったら絶対プレイしてないと思います。
PS4版リリース直後にガールズ&パンツァーのⅣ号戦車が配布されましたが、乗っていたのはちゃんと劇画な独軍おっさんで安心しました(笑)

基本無料なのも素晴らしいです(私は4年間で3000円も課金してないと思います)。
今まで7500戦やっていますので、インターバルやロード時間含め1戦7分と見積もると、900時間近く遊んでいることになります。
3000円を900時間で割ると、1時間あたり3.3円で遊べているという駄菓子屋も真っ青のコスパですね。
ちなみにこのゲームの総ダウンロード数は、PC版を含めると軽く1億は超えているみたいなので、一人当たりが超微課金でも塵も積もればでしっかり利益を生んで、質の良いサービスを維持できているのでしょう。
無料で気軽に始められますが、ガチでやり込むなら攻略wiki等を熟読して、各種戦術要素や各車種の諸元(装甲配置や機動力、主砲の弾種、貫通力や威力、弾薬庫やエンジンルームの位置等)を頭に叩き込んで戦場で立ち回る必要があり、奥はどこまでも深いゲームです。
今まで私がプレイした対戦型オンラインシューティングゲームの中では、間違いなく一番の完成度だと思います。
つい戦車話が長くなりましたが、そろそろ本題に入ります。
最近無性にウォッチ熱が上がっているので、また腕時計の事を書きます。
今回は珍しくCASIOではない時計の話です。
ミリタリーファンにはおなじみのSUUNTO VECTORについてです。

たまには装備でG-SHOCK(CASIO)以外の腕時計も選択肢に入れたいと思い、候補を探していたところ、VECTORの存在を思い出しました。
初期アフの頃から登場しています。


2000年代中盤以降も使用例はかなりあると思います。
ナショジオドキュメンタリーの「INSIDE THE GREENBERETS」でも着用していると思われる隊員がいます。

各種オークションサイトで見てみると、程度によりますがお手頃な価格で出回っています。
ただこれも息が長い製品にありがちな、年代によるマイナーチェンジがいくつもありそうです。
調達するにしても「数年前に生産終了した」くらいの知識しかなく、どれを選べばオーパーツにならないか分からなかったので、この機会に色々調べてみました。
大変ありがたい事に、「特殊部隊という響き」で既にVECTORの年代について考察記事を書かれておりますので、まず基礎をここで勉強させていただいた上で、私なりに肉付けしてみました。
軽くネットを調べてみると、発売年は1998年、ないし1999年という情報がいくつか出てきました。
生産終了は2015年のようで、2016年に「FINAL EDITION」という限定モデルが発売されたようです。

とりあえず最終形はこれで間違いなさそうですね。
ご丁寧に「FINAL EDITION」って入ってますし。

約15年の超ロングセラーモデルだったという事ですね。
少し調べてみたら当然マイナーチェンジしていました。
変遷を順を追って書いていこうと思います。
但し、今回ベゼル部の形状仕様のみに注目して変遷をまとめてあります。
ベゼル以外の仕様変更やソフトの変更、各年代のカラバリ展開は一切考察していませんのでご注意ください。
特にカラーはかなりの数が出ては消えているようなので、形状だけでなく「この年代には存在しない色」というオーパーツ判定が出てきそうです。
カラー展開については今後気が向いたら考察を進めようと思います。
まずは初期モデルを見極めるべく、いつもの「BACKPACKER誌しらみつぶし作戦」を実行したところ、1999年2月号に初めて広告が登場しました。


これが私が確認できた最古と思われる情報です。
おそらく本国フィンランドはじめ特定の地域では1998年の秋頃発売し、その他の地域ではタイムラグがあって1999年初頭頃に発売になったのではと想像しています。
まあいずれにせよ、9.11時点では確実に存在していた事になりますね。
ただBACKPACKER誌はわかりませんが、通常日本の雑誌は実際の発売月と「〇月号」の差が2ヵ月くらいあるので、1998年12月に発刊されていた可能性もありますね。
そうなるとアメリカでもVECTORは1998年には売っていた可能性が高そうです。
次に、同じ1999年の2月にオーストリアのどこかの旅行会社?のチラシにVECTORが載っていました。


ネットって本当に何でもありますね。
こんなモノまで拾えるとは思ってもみませんでした(笑)
では、ベゼルの特徴を見ていきましょう。
BACKPACKER誌

全体的にツルっとしていて、NとSの部分は湾曲し、外周に小さな突起がいくつも有ります。
印刷は「NEWS」と、NSの外側、WEの内側に線が引いてあります。
オーストリアのチラシ

一見同じですが、よく見るとベゼルの内周側に目盛りが振ってあります。
WEの内側の線は有りません。
同じ時期の画像のはずなのにいきなり仕様が違います...。
仮にBACKPACKER誌発刊が1998年12月だとして、チラシが1999年2月だとしても2ヵ月しか違いが無いです。
そんな短いスパンでマイナーチェンジが入るとは考えづらいです。
他にも1999年当時のVECTORの画像を漁りましたが、個人が撮影したような写真でBACKPACKER誌と同じ目盛り無しはありませんでした。


他の広告画像では、BACKPACKER誌以外でも目盛り無し仕様は確認できました。

このことから、おそらく広告用の画像を撮影したサンプルはまだ最終仕様ではなかったのではと想像しました。
広告用サンプルが完成した後に急遽目盛り印刷有りの仕様に変わったが、広告は差替える時間が無くそのまま掲載された、という感じです。
私は某メーカーに勤めていますが、結構こういうことはあります。
幻の「目盛り無し」仕様が市場に存在する可能性は無きにしもあらずですが、現時点では「ツルツルベゼル+NEWS+目盛り」が最初期モデルだと判断します。
次にネットを時系列順に探っていると、2001年秋にベゼル形状が異なる写真が出てきました。


先代に比べ非常に凸凹しているので一発で見分けが付きますね。
2020/12/4追記
某ネットオークションで2001年8月に購入したと思われる個体を発見しました。



出品情報からもおそらくこの個体に付属していた説明書である事は間違いなさそうなので、2001年8月時点でこの凸凹ベゼル仕様は世に出ていた可能性が濃厚だと考えます。
次に、2004年秋には再び初代同様のツルっとした形状に戻っています。

初代との見分け方は、NEWSが消え代わりに数字印刷が入ったところで、これも非常に分かりやすいですね。
以降、2014年の生産終了までベゼルの仕様に関しては変わっているように見えません。
私が写真で見る限りその他の部分も何も変わっていないので、早くに完成されたデザインだったということですね。
2020年の今の目で見ても洗練されているように思います。
まとめます(陸特装備目線)。
・初期アフとしては「ツルツルベゼル+NEWS+目盛り」の初期モデルが無難。
・凸凹ベゼル仕様は2001年秋登場なので、初期アフ的にもまあOKだがオーパーツのカラーはあるかもなので注意。
・初期イラクでは初期か凸凹ベゼルが該当。
・ACU登場以降は「ツルツルベゼル+数字」の後期モデルが自然。ただしこれもカラーによってはオーパーツになるので注意。
ネットでブログ等で個人所有の使用個体を見ていると、ベゼルの印刷、ケースの「SUUNTO VECTOR」の印刷がいずれもただの平面への印刷の為、すぐに剥げてしまっています。
オークションで出回っている中古個体もロゴや数字の印刷が剥げている物が多いです。


新品の高級感あるシボも見事に削れてテッカテカの個体が多いです。
使用環境や頻度によると思いますが、1、2年も使用すると印刷もシボもすっかり剥げている傾向があります。
大事な会社名と製品名を掲げたロゴや、機能上必要な数字印刷が1年そこらで剥げてしまうのは、名のある時計メーカーの製品ではあまり考えられないような気がします。
ちなみにロゴについては気になる人もやはりいるらしく、自作デカールを作成されていた方もいるようでした。


個人製作でオークションでほんの少し出品されていただけのようですが、結構需要ありそうですよね。
私も普通に欲しいと思いました。
また、風防も樹脂製の為、かなり傷が付きやすかったようです。
アウトドアでの比較的過酷な条件での使用が前提で設計されたはずですが、(機能ではなく美観を保つ意味での)耐久性は低い構造です。
日本では「フェスやキャンプに着けていきたいオシャレウォッチ」的な売られ方が多かった記憶があるので、この美観耐久性の低さは日本ユーザーのニーズには相反していたかもしれませんね(それでも人気だったようですが)。
神経質なまでにモノを大事に扱う日本人にとっては、なかなか精神衛生上良くない設計ですね(笑)
腕時計としてみたら「雑な外装設計だな」と思いますが、VECTORは腕時計ではなく実用ツールとしての「リストコンピュータ」として設計されたのかもしれませんね。
あくまで装飾品である腕時計とは、コンセプトがそもそも大きく違うのかもしれません。
よく比較されるCASIOのPRO TREKは「時計メーカーが作ったアウトドアウォッチ」で、VECTORは「コンパスメーカーが作ったリストコンピュータ」であって、見た目や機能は通ずるものがありますが、全く違う設計思想の基に産まれたのかもしれませんね。
そもそもSUUNTOは時計屋としての技術は未熟でしたでしょうし。
電池交換もVECTORはユーザーが自分自身で簡単に出来るようになっているという点も、腕時計としたらかなり大胆で常識外な仕様ですね。

ちなみに同じくらいの時期に発売され、同じく気温や気圧、方位センサーを搭載しているPRO TREKのPRG-40は、なんと4つも電池が必要です。

PRO TREKは電池交換無しで数年は使用でき、その代わり交換は専門店等で行うという設計思想なのでしょう。
もしかしたらVECTOR発売当時のSUUNTOは時計店という販売チャネルがなく、VECTORは時計店でのアフターサービスを受けづらいと想定し苦肉の策で「自分で電池を換える」という仕様にしたのかもしれませんね。
こんな感じで調べているうちにどんどん物欲は膨れ上がったので、早速品定めです。
日本でも人気でロングセラーだっただけあって球数は多いですが、上述のような仕様なので総合的に状態が良い個体は多くないです。
中には状態が良いものもありますが当然高価で、使うとすぐに剥げたり傷つくと思うと食指が伸びません。
当然壊れたら修理もできませんしね。
そんな中、初代モデルがチープカシオ並の激安&当時の説明書付きで出品されていたので、思わず即決してしまいました。


使用感がかなりあり、ロゴとWE印刷がいないですが、電動ガンのマガジン1本くらいの価格だったので贅沢は言えません。
説明書の類は年代考察資料として有用な場合が多いので、私にとってはかなり大きいオマケです。
元々やつれている上に安かったので、サバゲで気兼ねなく使えて好都合です。
それに現場で1年も使われればこれくらいにやつれていそうな感じもしますし、初期アフ装備的にはリアルと言えるかもしれませんね。
上の方で写真載せましたが、色も初期アフドキュメンタリー番組「Special Operations Force: America's Secret Soldiers」で隊員が装着していたと思われるブラックです。


無事、初期アフウォッチレパートリーが増えました。
まだ現物は日本の実家にあり、状況が状況なのでいつ帰国して確認できるか分かりませんが、中々良い買い物をしたと思います。
現物確認できたら、また詳細を記事にしようかなと思います。
お読みいただきありがとうございました。
初期アフリストコンパス 再考編

この記事で当ブログの記事数が200記事になりました。
2017年の5月に始めたので、平均で1ヵ月6記事弱書いている事になります。
平均1週間に1記事以上書いていたとは、自分でも驚きです。
昨年中国在住になってからはペースが落ちましたが、これからもなるべくコンスタントに続けて行こうと思います。
コロナウイルスの影響で、ネトフリやアマプラの「話題の映画」的なカテゴリに感染モノがちょいちょい並んでいます。
映画通の盟友Bucket Head氏のすすめもあって、邦画「復活の日」を観てみました。

生物兵器として開発したヤバい致死性でヤバい繁殖力のウイルスが事故で外界にバラまかれ、ウイルスの活動できない南極に残った1000人弱以外の人類は死滅してしまい...。という内容です。
いかにも昭和な演出&ご都合主義な展開はまあご愛敬として、めちゃめちゃ金の掛かったシーンの数々は、今のCG成熟期で肥えた目で見ても見ごたえ十分です。
本当に南極で撮影し、本物の潜水艦やら大型船舶も出てきます。


40年前の映画ですが、俳優、製作陣もアラサーの私ですら知ってるような超有名人ばかりで豪華です。
主役の草刈正雄は今でも超渋カッコイイので、40年前の20代の若々しい御姿は推して知るべしですね。

パンデミック物としてはハリウッド映画「コンテイジョン」とかの方が何倍もリアルなストーリーですが、もし今流行っている新型肺炎が致死率100%だとしたら世界はどうなっちゃうんだろう、と想像してしまいました。
長尺ですが話としては意外と
それでは本題に入ります。
ODA961の初期アフミリフォトに登場しているSilvaのリストコンパスについてです。





最近腕に巻くガジェットの事ばかり書いていますね。
過去ミリフォトから考察し自作し、最終的に新品を手に入れたSilvaのリストコンパスについて、今回新たに考察を進めましたので記事にしておきます。
過去の経緯は下記リンクからご覧ください。
「初期アフ リストコンパス問題」
「初期アフリストコンパス 加工編」
「初期アフリストコンパス問題 解決編」
「初期アフリストコンパス問題 解決編PART2」
先日、何気なくネットを徘徊していると下記写真を発見しました。


SUUNTOのM9コンパスですが、金属製の留め具が付いています。
M9と言えばベルクロ留めが一般的ですよね。

SILVAのコンパスの同じくベルクロ留めしか確認できていません。
たしかナイロンが気になる年頃なんです(仮)。のリコさんも「ベルクロじゃないやつ」をお持ちというコメントを以前いただきました。
現行がベルクロなので、この留め具付きはベルクロ仕様の前にあったと考えるのが自然です。
以前私は、「先にSILVAがこのコンパスを製造販売していて、何かの理由で製品権をSUUNTOに譲渡されたのでは?」と考察しました。
しかし、そうなるとこの留め具仕様のM9の存在が矛盾してしまいそうです。
そこで、これをきっかけに再度このコンパスについて調べを進めてみました。
今回調査して新たに分かった事を書いていきます。
まず、このSilvaコンパスのモデル名が判明しました。
「424」という型番で売られていたようです。
いくつかの販売サイトで確認したので、おそらくあっていると思います。

(残念ながらどのサイトもかなり古く、当然販売はしていませんでした)
次に、海外のとあるフォーラムででこのコンパスの出自についての言及を発見しました。

下記、画像の文章抜粋です。
Silva USA/Silva Canada: Johnson Outdoors has owned the soleright to market Silva brand name compasses in North America (this includes Canada) since 1998.
The original Swedish-made Silvas are no longer sold in the U.S. or Canada, except through gray-market channels.
At first, Johnson Outdoors sourced many of its Silva-branded compass models from Suunto.
However, this practice largely ceased several years ago (some discontinued models may still be around,
like the Silva 424 wrist sighting compass which Suunto made based on their M-9 wrist compass).
ちなみに同じような内容を他のフォーラムでもいくつか見かけました。
以前の記事でも、北米のSilvaの商標はJohnson Worldwide Associate(1999年よりJohnson outdoorsに改編)が持っていたと書きましたが、この記述ではJohnson Worldwide associateは1998年からだとあります。
この内容はwikipediaにも記載がありますね。
また、Johnson OutdoorsはSUUNTOのモデルをSilvaブランドとして展開していたとあります。
例として、424コンパスはM9コンパスを基に作られていると触れています。
この言及が正しければ、やはりM9が先に誕生していて、1998年から数年間は北米向けのみにSilva424が並行生産されていた事になります。
私はこの内容は正しいと考えました。
その裏付けとして、下記項目があります。
1.金属留め具M9の存在
最初に書いた通り、ベルクロ留めのSilvaコンパスより明らかに古いと思われる金属留め具のM9も裏付けになります。
このことから、先にM9があった可能性が高いです(Silva424の金属留め具バージョンもあるかもしれませんので、断定はできませんが)。
2.金型とFINLAND刻印
以前記事で書きましたが、M9とSilvaの各部の金型由来と思われる形状(バリやヒケ、成形傷)からも、同じ金型で作られていた可能性が高いです。
M9


424


そして、リコさんのコメントでは、所有されているM9の中には足裏の「FINLAND」刻印が無い個体も存在するとのことでした。
先述の金属留め具バージョンも「FINLAND」刻印は無いように見えます。

この刻印は凸刻印なので、後から金型を掘れば比較的容易に付け加えられます。
なので、Silvaよりも先に「FINLAND」刻印無しバージョンのM9が存在した可能性が高いです。
そして、先ほどのフォーラム文にこんな事が書いてありました。
Suunto-made Silva compass packages usually state 'Made in Finland' or have a Finnish flag on the package.
ここから、Johnson outdoorsがSilva424を北米で発売する際に、MADE IN FINLANDを強調する為にSUUNTOに依頼して「FINLAND」刻印を追加させたのかも、とも想像しました。
3.文字板の出っ張り
M9、424共に、文字板の裏側に出っ張りがある個体と無い個体が存在します。
左M9、右424。両方出っ張りあり。

424。出っ張り無し。

あと写真はありませんが、リコさん所有の個体で出っ張りの無いM9があるそうです。
最新のM9には出っ張りがありますので、どこかの時期で金型に出っ張り(金型上は凹み)を追加したのだと思われます。
そうなると、M9も424も出っ張り追加の時期を跨いでいた=同時に並行して作られていたと考えられますね。
4.Silva刻印
しかし、「M9が先に存在し、途中一時期Silva424が並行して同時に作られていた」と結論付ける為には、ひとつ引っかかる点がありました。
これも以前の記事で言及し、Silvaが先に存在したのでは?と私が考察した基になった要素です。
金色に輝く「Silva」刻印です。


拡大して見ると凹んでいるので、金型で成形時に刻印を付けているのであれば金型は凸になります。
先ほどの「FINLAND」は金型凹なので後加工可能ですが、凸加工は非常に困難ですし、したとしても痕跡が見えるはずです(入れ子線等)。
したがって、もし成形時に刻印を入れていたとなると、先に「Silva」刻印があってそれを途中で削除したと考えないと矛盾してしまいます。
上記フォーラム文や留め具、FINLAND刻印を鑑みるとこの刻印の矛盾だけ解せません。
そこで、刻印は成形では無く、成形後の後加工で入れている可能性を探ってみることにしました。
すると「デボス加工」なる刻印手法が見つかりました。
クレジットカードや銀行カードによく用いられる加工で、製品に熱を掛け箔を押し付けると同時にその部分を凹ませるという加工手法のようです。

Silva424もこれと同じかはわかりませんが、成形後に刻印が施されていると考えると全て合点がいきます。
さらに、リコさんのコメントでは、私の個体とリコさんの個体ではSilva刻印の形状が少し異なるようです。
射出成形後の後加工であれば比較的バラつきが大きいと想像できるので、両者を見比べればこれもひとつの裏付けになるかもしれません。
以上が今までの考察を含めた最新の私の考察です。
長々書きましたが、最後に簡潔にまとめておきます。
・このコンパスのモデル名は「424」
・M9が先に存在し、1998年以降の一時期Silva424が並行生産され、北米に展開されていた
というわけで、頑張ってSilva424を探さなくても、9.11以降の装備であれば旧型文字板SUUNTOで問題無しだと思われます。

旧型文字板SUUNTOも既に生産終了していて年々プレミア価格が上がっていくのは必至なので、手にするなら今の内だと思います。
あとはどの時点で留め具が無くなりベルクロ仕様になったか分かれば完璧ですね。
これからも引き続き研究を続けたいと思います。
現在、「BACKPACKER」誌の98年付近のバックナンバーを片っ端から読み漁って424かM9が出てこないか探しています。

まだこの内容に対しては収穫無しですが、副産物的に色々なアイテムの情報を入手できているので、また別の機会に記事にしようと思います。
ちなみに前回の「パスファインダー騒動」の発端となった広告は、このコンパスを調べていた時に見つけた副産物です。

知らない事は詳しい友人知人に聞いて教えてもらうのは一番の近道ですが、自分で頭を抱えて試行錯誤して寄り道して深堀りしたりして、情報が枝分かれして知識が咲いていくこの感じが私は何より楽しいです。
また、こうして自分自身で導き出した知識はかけがえのないものだと思えます。
今はネットで基本どんなことでも調べる事が出来ると思いますが、どう調べるか?調べて出てきた点と点で線をイメージできるか?はまだまだ人それぞれの思考力や記憶力に依存していると思います。
今回は今まで知らなかった新たな「点」がいくつか出てきたことで、今まで描いていた「線」が変わりました。
ネットや書籍で知り得る単一的な情報はあまり有意義な知識ではなく、あくまで知識を紡ぐ「道具」であることが多いと思います。
日々便利になる道具を活かして、より有意義な知識を紡いでいけるようこれからも精進しようと思います。
お読みいただきありがとうございました。